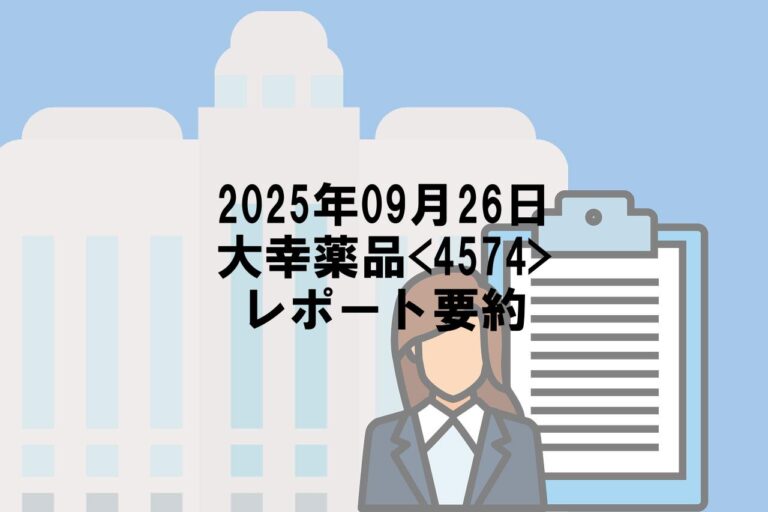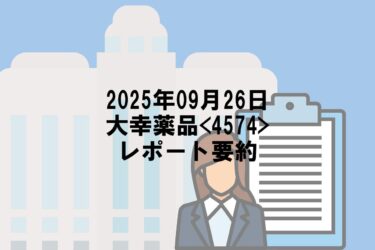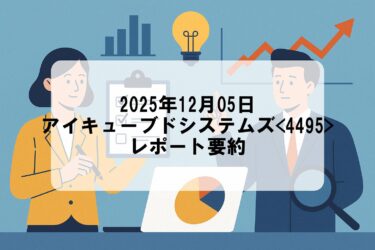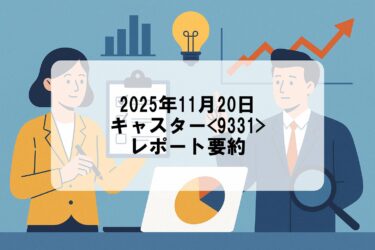大幸薬品〈4574〉は、「正露丸」や「クレベリン」などで知られる医薬品・感染管理製品の老舗メーカーです。
2025年12月期中間期は、医薬品事業の設備更新や出荷減少の影響で減収減益となりましたが、「セイロガン糖衣A」の投入や感染管理事業の底打ちなど、次の成長に向けた動きも見られます。
また、二酸化塩素ガス製品に関する新JSA規格の制定が追い風となり、品質標準化による消費者信頼向上が期待されます。
2025年09月26日に掲載された大幸薬品<4574>のレポート要約
元レポートは下記の通りです。
大幸薬品<4574>レポートPDF
出典元:FISCO
大幸薬品(4574)企業調査レポート
概要
大幸薬品株式会社(証券コード: 4574)は、主に医薬品事業と感染管理事業を展開し、特に「正露丸」や「クレベリン」といった製品で広く知られています。
本レポートでは、2025年12月期中間期の業績動向や今後の展望、さらに二酸化塩素ガス製品に関する新たな規格の影響について分析します。
業績動向
減収減益の背景
2025年12月期中間期における大幸薬品の業績は、売上高が2412百万円(前年同期比15.7%減)、営業利益が46百万円(同90.3%減)、経常利益が20百万円(同96.1%減)、親会社株主に帰属する中間純利益が279百万円(同63.4%減)という結果となりました。
これらの減収減益は、医薬品事業における設備更新と出荷の減少が主な要因です。
売上の内訳
– 医薬品事業
売上高は2206百万円(前年同期比16.9%減)でしたが、業績は計画通りの進捗を見せました。
「正露丸」の供給制限が影響したものの、「セイロガン糖衣A」の新製品投入が増収に貢献しました。
– 感染管理事業
売上高は203百万円(前年同期比同額)で、前年同期並みの推移を維持しています。
コロナ禍後の市場縮小が影響しているものの、出荷や返品は減少傾向にあります。
利益の推移
売上総利益は1320百万円(前年同期比21.3%減)で、医薬品単価の改定や数量減、原価上昇が影響しました。
一方で、販管費は1273百万円(同6.5%増)となり、広告宣伝費の増加が要因となっています。営業利益は46百万円(同90.3%減)となり、全体の利益は厳しい状況が続いています。
今後の展望
医薬品市場の動向
国内止瀉薬市場は前年同期比で9.2%の成長を見せており、大幸薬品の市場シェアは48.2%と高い水準を維持しています。
この市場の拡大は、同社の業績回復に寄与する可能性が高いと考えられます。
海外展開の課題
海外売上高は508百万円(前年同期比37.9%減)と減少しており、製造スケジュールの調整が影響しています。
特に香港、中国、台湾の需要は旺盛ですが、流通在庫が低水準であるため、今後の出荷計画が重要となります。
感染管理事業の回復
「クレベリン」シリーズの除菌市場については、コロナ禍後の市場縮小が下げ止まりつつあり、出荷や返品の減少が期待されます。
この感染管理事業の再成長が、今後の業績を支える鍵となるでしょう。
大幸薬品の2025年12月期見通しと業績分析
2025年12月期の業績予想
大幸薬品は2025年12月期において減益を予想しています。主な要因は、供給体制の安定化施策に伴う売上原価の増加です。具体的な予想は以下の通りです。
– 売上高:6300百万円(前期比0.1%増)
– 営業利益:215百万円(前期比65.9%減)
– 経常利益:200百万円(同70.9%減)
– 当期純利益: 300百万円(同66.6%減)
売上高はほぼ横ばいですが、コスト増加により全体的な利益は減少する見込みです。
事業別詳細分析
医薬品事業
医薬品事業の売上高は5745百万円(前期比0.6%減)を見込んでいます。
国内需要は堅調で、前期の値上げ効果が残りますが、「正露丸」の製造設備の移設・更新により、一時的に生産量が減少します。海外市場では、中国・香港・台湾での需要が続く見通しです。
感染管理事業
感染管理事業の売上高は550百万円(前期比8.1%増)を見込んでいます。
最近の繁忙期には業績の底打ちが確認されており、「クレベリン」の成分である二酸化塩素の有効性に関するエビデンス強化とマーケティング施策を計画中です。
コストと利益の見通し
売上総利益
売上原価の増加要因として、修繕費等の関連費用が330百万円、原材料費・資材費の上昇が130百万円が挙げられます。これにより、営業利益は減益を見込んでいます。
販管費
効率的な費用投下とコストコントロールを引き続き実施し、前期並みの水準を維持する想定です。
二酸化塩素ガス製品のJSA規格
はじめに
2025年9月、日本規格協会(JSA)が二酸化塩素ガス製品の試験方法に関する新たな規格を発行しました。
この新規格の導入により、業界全体における品質向上が期待され、各メーカーの製品性能比較が容易になります。
新たな規格の概要
新規格の正式名称は「JSA-S1021 二酸化塩素ガス製品-浮遊ウイルス低減性試験方法・浮遊ウイルス低減効果-大型試験チャンバー法」です。
この規格により、従来の独自試験方法からの脱却と標準化が図られ、消費者が製品の性能を比較しやすくなることが期待されています。
同社の新たなマーケティング施策
新規格の発行を受けて、大幸薬品はマーケティング戦略の強化を検討しています。
特に、消費者需要の増加が見込まれ、適合マークの表示が可能になることで、業務用製品のラインナップを強化する方針です。
株主還元の方針
2025年12月期の配当について
大幸薬品は安定した成長性を維持しつつ、内部留保を確保することを基本方針としていますが、2025年12月期の配当予想は未定です。
業績進捗や財務状況を見極めた上で判断する方針です。
結論
大幸薬品は医薬品事業と感染管理事業において一定の安定性を見込んでいますが、原価上昇の影響を受けているため、利益の減少が懸念されます。
また、新たに発行された二酸化塩素ガス製品の試験方法に関する規格は、業界全体の基準を統一し、消費者の選択肢を広げることに寄与します。今後の業績進捗に注目が集まります。
■ この企業を含む【5.医薬品セクター株まとめ】はこちら
5.医薬品セクター株最新動向
無料で株価チャートや決算データ、アナリストコメントなどを確認でき、企業分析の精度を高められます。
松井証券「マーケットラボ」徹底ガイド|無料機能・使い方・米国株版・他社比較まで解説
ここから確認
2025年03月17日に掲載された大幸薬品<4574>のレポート要約
元レポートは下記の通りです。
大幸薬品<4574>レポートPDF
出典元:FISCO
大幸薬品のビジネスレポート:2024年の業績分析と将来展望
業績動向と医薬品事業の成績
2024年12月期は大幸薬品が4期ぶりに利益を達成した年でした。特に医薬品事業が好調で、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が前年比で増加しました。
国内売上高は増加し、「セイロガン糖衣A」や「正露丸クイックC」の供給体制が強化され、売上を伸ばしました。一方で、「正露丸」は供給不足で売上が減少しましたが、市場シェアは回復傾向にあります。
感染管理事業の課題と財務状況
感染管理事業は国内外で低調であり、売上が減少しました。暖冬の影響や小売店頭展開の遅れが課題となっていますが、除菌市場でのシェアは回復の兆候が見られます。
大幸薬品は安定した財務基盤を維持しており、自己資本比率が高水準で、有利子負債も抑制されています。金融機関との資金確保に関する契約も順調に進んでいます。
2025年の展望とトピックス
2025年12月期は需要が堅調である一方、先行投資により減益を予想しています。医薬品事業の売上高は微減で、感染管理事業は苦戦が予想されます。
大幸薬品は中期的な医薬品供給量増加プロジェクトを始動し、「正露丸」の供給量増加プロジェクトも進めています。感染管理事業では浮遊ウイルス・菌測定の規格づくりを目指し、JSA規格の制定を予定しています。
株主還元方針と将来展望
2025年12月期の配当は未定ですが、内部留保の確保と安定的な配当を維持し、株主還元を基本方針としています。
業績進捗や財務状況を見極めて、将来の成長に向けて着実なステップを踏んでいくことが大幸薬品の方針です。
大幸薬品は医薬品事業を中心に成長を続けており、将来展望も期待される企業です。
業績の改善や事業展開の取り組みが、株主や投資家にとって注目すべきポイントとなっています。今後の動向にも注目が集まりそうです。
■ この企業を含む【5.医薬品セクター株まとめ】はこちら
5.医薬品セクター株最新動向
松井証券の「マーケットラボ」は、銘柄分析・チャート・四季報・スクリーニングまでを無料で使える高機能ツールです。 本記事では、松井証券マーケットラボの使い方、機能一覧、米国株版との違い、そして他社ツールとの比較までを徹底解説。 初[…]