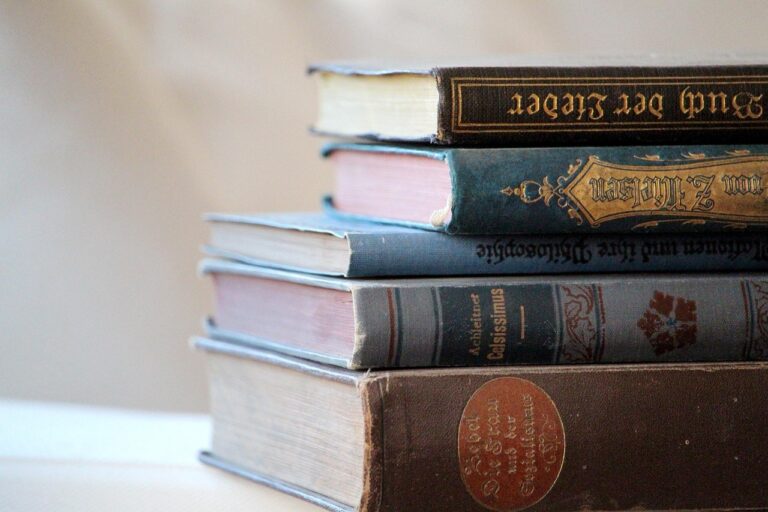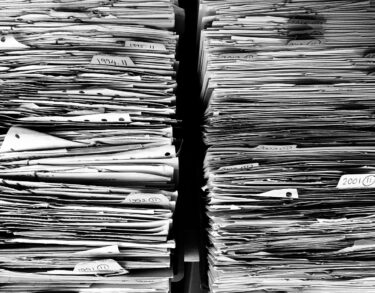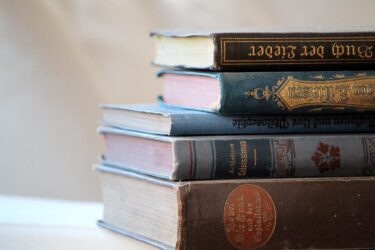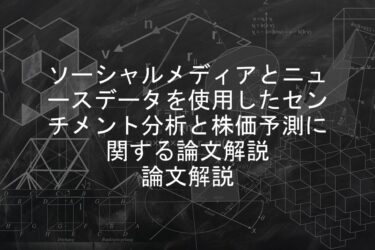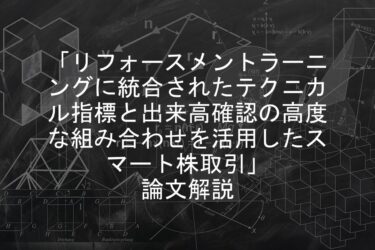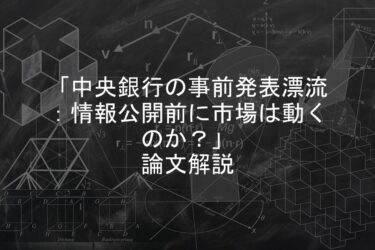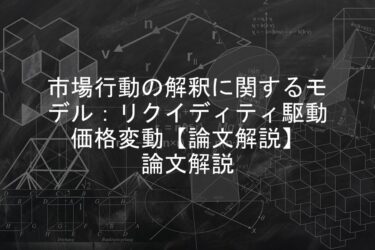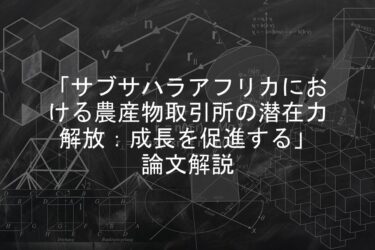論文:Why Decentralized Exchanges Are Not “Exchanges” Under the Securities Exchange Act of 1934
(なぜ分散型取引所(DEX)は証券取引法上の『取引所』と見なされないのか)
を分かりやすく解説・要約しました。
出典元:SSRN(2025/04/05掲載)
第1章 導入 ― DEXと証券取引法のずれ
1.1 分散型取引所(DEX)の台頭と構造的特徴
分散型取引所(Decentralized Exchange, DEX)は、従来の証券取引所のように中央の運営主体を持たず、スマートコントラクトによって売買の執行・清算が自動で行われる仕組みを持っています。
この仕組みでは、ユーザーがブロックチェーン上のプログラムと直接やり取りを行い、仲介者の介在なしに取引が完結します。
この非中央集権的アプローチは、
-
透明性(すべての取引履歴がブロックチェーン上で公開される)
-
耐検閲性(特定の主体が取引を拒否・停止できない)
-
アクセスの平等性(グローバルに誰でも参加可能)
といった利点をもたらす一方で、法的責任の所在が極めて曖昧であるという難題を生み出します。
1.2 1934年証券取引法(Exchange Act)の前提構造
1934年に制定された証券取引法(Exchange Act)は、大恐慌後の金融安定化を目的に策定されました。
当時想定されていた「取引所(exchange)」とは、
-
組織的に管理される市場であり、
-
明確な運営主体(organization / association)が存在し、
-
監督・開示・ルール設定の責任を負う構造が前提とされていました。
つまり、同法の根本的な想定は「中央集権的な取引所モデル」にあります。
そのため、取引が自律的なコード(スマートコントラクト)によって完結するDEXのような構造は、法の想定外の存在となります。
1.3 DEXをめぐるSECの対応と論争
近年、米国証券取引委員会(SEC)は、Uniswap などのDEXが証券取引法に定義される「取引所」に該当するかを巡り、「Wells Notice」(行政処分前の正式通知)を発行しています。
SECは、取引所定義の範囲を拡大し、アルゴリズムやプロトコルによって投資家を結びつける仕組みも監督下に置こうとしています。
しかし、著者は次のように指摘します。
DEXは確かに取引を仲介するが、「誰が運営者か」を特定できず、誰も登録義務を負えない。
したがって、現行法上「取引所」とは呼べない構造的欠陥がある。
1.4 中心的な問題提起
本論文の核心は、次の二点に要約されます。
-
なぜDEXは法的に「取引所」とみなされないのか
(→ 条文上の定義・解釈・制度的前提の不一致) -
DEXを適切に規律するために、どのような法改正・監督枠組みが必要か
(→ 既存の「取引所」カテゴリーに無理に当てはめるのではなく、別カテゴリーを設ける提案)
1.5 導入部の主張の意義
著者が強調するのは、単なる法の空白ではなく、法体系の設計思想そのものがDEXと整合しないという根本的なズレです。
-
Exchange Act の「取引所」は「人による監督・組織的運営」を前提。
-
DEX は「コードによる自律的取引・責任の分散」を本質とする。
このため、従来の法体系では、
→ 「取引の意思決定主体が曖昧」
→ 「違反行為の責任追及ができない」という構造的問題が発生します。
著者はこれを踏まえ、結論として次の方向性を示します。
既存法の拡大解釈ではなく、新しい監督カテゴリーを立法で整備すべきである。
1.6 この章の位置づけ
この導入章は、以下の3つの役割を果たしています。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 問題の可視化 | 「取引所」定義とDEXの実態の間にある制度的ギャップを明確化 |
| 分析の方向性提示 | 条文解釈・制度運用・政策提言の三層構造で議論することを予告 |
| 論文の射程設定 | Exchange Act に限定し、SEC監督・立法対応を中心に検討する |
1.7 本章のまとめ
-
DEXは、ブロックチェーン上の自律分散的金融市場として急速に拡大している。
-
しかし、1934年証券取引法が想定する「取引所」モデルと整合しない。
-
この制度的ねじれが、規制の空白・責任の不在・監督不能という新たな問題を生んでいる。
-
著者は、既存の枠を拡張するよりも、DEXに即した新たな「調整型監督(Calibrated Oversight)」を立法的に整備すべきだと主張する。
第2章 「取引所」定義の法的分析 ― なぜDEXは該当しないのか
2.1 「取引所(Exchange)」の法的定義
米国証券取引法(Securities Exchange Act of 1934)第3条(a)(1)では、「取引所(exchange)」を次のように定義しています。
An exchange means any organization, association, or group of persons which constitutes, maintains,
or provides a market place or facilities for bringing together purchasers and sellers of securities.
(取引所とは、有価証券の売り手と買い手を結びつけるための市場またはその施設を構成し、維持し、または提供する組織、協会、もしくは人々の集まりをいう)
つまり、法的には「取引所」とは――
-
組織・団体(organization, association, group)であり、
-
証券の買い手と売り手を集める(bring together)市場や施設を「構成・維持・提供」するもの、
と規定されています。
この定義が意味するのは、「取引所」は必ず運営する主体を前提とする制度だということです。
2.2 DEXは「組織・団体」ではない
著者が最初に指摘するのは、DEXには組織的な運営主体が存在しないという点です。
-
Uniswap や Curve などの主要DEXは、スマートコントラクトによって自動運営されており、
日常的な意思決定や取引執行に関して、中央の法人・団体が介在していません。 -
DAO(分散型自律組織)がプロトコルの改修やパラメータ調整を行うことはあっても、
それは「特定の組織が市場を構成・維持する」行為とは性質が異なります。 -
多くのDEXでは、誰もが流動性を提供し、誰もが売買を行えるため、
「組織」よりも「オープンソースの金融インフラ」に近い。
このため、Exchange Actの定義の最初の要件
「any organization, association, or group of persons(組織・団体・人の集まり)」
には該当しないと論じています。
2.3 DEXは「市場(market)」または「施設(facility)」を提供しない
次に著者が焦点を当てるのは、「market place」や「facilities」という概念です。
伝統的な証券取引所(NYSEやNASDAQなど)は、明確に定義された市場空間とシステムを提供し、
その内部で「価格発見」「取引マッチング」「清算管理」が行われます。
一方、DEXは――
-
取引そのものがブロックチェーン上の分散ノード間のスマートコントラクト上で成立するため、
特定の「市場施設」を維持しているわけではありません。 -
取引はパブリックなコードの呼び出しとして機能しており、
DEXプロトコルは「市場を構築・提供」しているというよりも、
「自己実行的な数式(例:AMM曲線)」を公開しているにすぎません。
著者はこの点について次のように述べます。
DEXは市場のように見えるが、実際には「市場を構成する主体がいない」。
プログラムが市場的な結果を生み出しているにすぎず、Exchange Act上のfacility(取引所の施設)には当たらない。
2.4 DEXは「買い手と売り手を集める(bring together)」仕組みではない
さらに決定的なのは、「取引所」の核心要件である
bringing together purchasers and sellers of securities(買い手と売り手を結びつけること)
という機能の欠如です。
-
DEXは、ユーザー間のマッチングを行うのではなく、
自動化された流動性プール(Automated Market Maker, AMM)を通じて取引を成立させます。 -
売り手・買い手の間に直接的な相互作用は存在せず、
ユーザーはプールとスマートコントラクトに対して取引を行います。 -
この構造上、DEXは「市場参加者を結びつける」わけではなく、
価格関数を通じて取引を自動生成する仕組みと位置づけられます。
つまり、DEXはExchange Actが想定する「取引所の中心的機能(市場マッチング)」を満たさないのです。
2.5 「証券取引所の機能」を果たしていない
最後に、著者は機能的観点からも、DEXが伝統的取引所とは異なることを明確にします。
| 観点 | 伝統的取引所 | 分散型取引所(DEX) |
|---|---|---|
| 運営形態 | 法人組織(登録・監督下) | スマートコントラクトによる自律運営 |
| マッチング | 売買注文を中央の板でマッチング | 価格関数(AMM)により自動執行 |
| 清算・保管 | クリアリング機関を通じて行う | 即時オンチェーン清算 |
| 規制責任 | 取引所が一元的に負う | 運営主体が存在せず責任の所在が不明 |
| 情報開示 | 監査・報告義務あり | コード公開による透明性のみ |
このように、DEXは表面的には「市場のように機能している」ものの、
法律が想定するExchangeとは異なる構造と責任分担の原理で動いていることが明らかになります。
2.6 第2章のまとめ
著者は、Exchange Act の定義に基づく条文解釈を通じて、DEXが取引所と見なされない4つの理由を整理しています。
-
「組織・団体」ではない — コードとコミュニティによる自律的運営
-
「市場・施設」を提供していない — ブロックチェーン全体が場となる
-
「買い手と売り手を結びつけない」 — マッチングではなく自動流動性
-
「証券取引所としての責任構造を持たない」 — 管理主体・登録義務の欠如
これにより、DEXを現行の「取引所」カテゴリに当てはめることは、
法理上・制度上ともに無理があると結論づけています。
第3章 登録制度の限界 ― なぜDEXは従来の規制フレームワークに適さないのか
3.1 「登録取引所制度」とは
1934年証券取引法(Exchange Act)は、registered national securities exchange として活動するすべての取引所に対し、
SEC(米国証券取引委員会)への登録義務を課しています(第5条)。
この登録制度の目的は以下の3点に整理されます。
-
市場の公正性確保(Fairness)
上場・取引ルールが一貫しており、不正取引を防ぐこと。 -
透明性(Transparency)
発行体・仲介者・投資家に関する情報を適時開示すること。 -
責任主体の明確化(Accountability)
取引所が自らの監督責任・報告義務を負うこと。
この制度は「中央運営者が存在する市場」を前提に設計されているため、
DEXのようなコード駆動型の分散市場には、根本的に適用しづらい構造を持っています。
3.2 DEXと登録要件の不整合
著者は、Exchange Act における登録要件が DEX にどのように適用不能かを、
条文・制度設計の観点から4つに整理しています。
(1) 登録主体の不存在
登録を行うには、「法人格」または「代表主体(responsible entity)」が必要です。
しかし、DEXでは、
-
取引執行はスマートコントラクトが自動処理する。
-
DAO(分散型自律組織)がガバナンス投票を行うとしても、法的主体とは見なされない。
-
開発チームや創設者が登録申請者として行動すると、DEXの自律性を否定することになる。
したがって、「誰が登録すべきか」自体が定義できないのです。
(2) 上場・審査の不在
従来の取引所は、上場前に発行体を審査し、
会計・開示要件を満たす企業だけを受け入れます。
しかし、DEXでは、
-
トークンはスマートコントラクトを通じて自由に発行・流通可能。
-
審査・承認手続きが存在せず、プロトコル上で誰でも上場に相当する操作が可能。
-
これにより、登録制度が求める「上場管理責任」が成立しない。
(3) 監視・報告義務の非現実性
SEC登録取引所は、内部統制・コンプライアンス・取引監視を実施し、四半期・年次で報告を行う義務があります。
しかしDEXは、
-
取引履歴はブロックチェーンに自動記録されるが、 「監督者」や「報告者」が存在しない。
-
不正行為のモニタリングを中央で担う主体がいない。
-
実務的誰がSECに報告するのかという責任の所在が空白。
(4) 取引参加者へのアクセス制御の欠如
登録取引所は、認定ブローカー・ディーラー経由でのみアクセスを許可するなど、参加者管理(membership control)を行います。
しかしDEXでは、
-
ウォレットさえあれば誰でも取引可能。
-
匿名性が高く、居住地・資格・金融免許などを確認できない。
-
これにより、既存のアクセス管理フレームワークが完全に崩壊します。
3.3 SECの対応とその限界
近年、SECはDEXやDeFiに対する「取引所定義拡張」を試みてきました。
具体的には、Rule 3b-16の改正案(2022–2023)で、
「取引所」の定義を以下のように広げようとしています。
Any communication protocol or system that brings together orders for securities.
すなわち、「通信プロトコルやシステムであっても、証券取引を促すなら取引所に該当する」とする解釈です。
しかし著者は、これには二つの致命的問題があると指摘します。
-
過剰適用(Overreach)
DEXだけでなく、メッセージアプリやコードリポジトリなど、
単なる技術プラットフォームまで「取引所」に巻き込む危険がある。 -
法的実効性の欠如(Unenforceability)
仮に適用したとしても、登録主体の不存在により執行不能となる。
つまり、「定義を広げる」ことではなく、
DEX専用の新たな法的カテゴリー(Regulatory Class)を構築すべきだという結論に至ります。
3.4 登録制度の本質的ギャップ:中央集権 vs. 自律コード
著者は、現行制度の「構造的前提」を次のように整理しています。
| 制度的前提 | 登録取引所モデル | DEXモデル |
|---|---|---|
| 運営主体 | 法人格を持つ取引所 | 分散コミュニティ/DAO |
| 運営原理 | 規制遵守・監督・報告 | スマートコントラクトによる自動執行 |
| 中央管理 | 存在(取引監視・上場審査) | 不在(コードにより自律的) |
| 責任の所在 | 明確(登録取引所) | 不明(開発者かユーザーかDAOか) |
このギャップが埋まらない限り、登録取引所制度をそのままDEXに適用することは、法的にも技術的にも不可能と著者は結論づけています。
3.5 第3章のまとめ
本章の結論は明快です。
「Exchange Actの登録フレームワークは、中央管理を前提とする。
一方、DEXは自律コードに基づく非中央化システムであり、 両者の制度的前提が根本的に異なる。」
そのため、著者は次の政策的方向性を提案します。
-
DEXを既存の「取引所」カテゴリーに押し込むのではなく、Code-Based Market Infrastructure という新しい法区分を創設する。
-
その上で、報告義務・透明性・AML/KYCなどを分散型アーキテクチャに適合させて再設計すべき。
この提言は、単なる技術論にとどまらず、「法が中央集権を前提とした時代」から「コードが制度を担う時代」への転換を象徴しています。
第4章 調整型監督 ― DEXのための新しい法制度
1. なぜ「調整型監督(Calibrated Oversight)」が必要なのか
著者は、現行の法律をそのままDEXに当てはめるのは構造的に無理があると指摘します。
なぜなら、証券取引法は「人間が運営する市場」を前提に作られているからです。
一方、DEXはコードとブロックチェーンで自律的に動く仕組み。
ここでは「誰が監督するか」よりも、「どうやって透明性を担保するか」が重要になります。
そのため、従来の登録制ではなく、技術に合わせた柔軟なルール設計が必要になります。
それが「調整型監督(Calibrated Oversight)」という考え方です。
2. 調整型監督の基本コンセプト
著者の提案するCalibrated Oversightは、「すべてを規制する」のではなく、「リスクに応じて調整する監督方式」です。
ポイントは次の3つ
-
責任を分散的に定義する
→ DEXには中央管理者がいないため、
開発者・DAO運営者・流動性提供者など、関与者ごとに“限定的な責任”を割り当てる。 -
透明性(Transparency)を法的義務にする
→ スマートコントラクトのソースコードや流動性プールの情報を公開し、
SECなどの監督機関が「監査可能」な状態にする。 -
リスクベース規制(Risk-Based Regulation)
→ 取引規模や証券性の度合いに応じて、
規制のレベルを変える(例:小規模プロトコルは軽微な報告義務のみ)。
3. 具体的な監督モデルの提案
著者は、DEXに対して次のような3段階の監督モデルを提案しています。
(1) コード開示・監査の義務化
-
スマートコントラクトのコードを公開し、
第三者監査機関が定期的に安全性と機能をチェック。 -
ソースコードに「悪意ある機能(例:抜け道、自己取引)」がないか確認。
(2) トークン分類とリスク区分
-
各トークンを「証券型」「ユーティリティ型」「決済型」などに分類。
-
証券型(投資性が高いトークン)のみ、追加的な情報開示義務を課す。
-
小規模のコミュニティ・トークンは免除または軽い報告で済む。
(3) 自動化された報告・監視メカニズム
-
ブロックチェーン上のトランザクションデータを自動的に集計。
-
SECなどの規制当局がAPIを通じて監視できるようにする。
4. SECと議会への提言
著者は、SECと議会に対して次の2つのアクションを提言しています。
-
Exchange Actの条文を改正し、「コード主体の市場」を定義に加えること。
→ DEXを無理に“取引所”扱いせず、新しいカテゴリーとして明確化。 -
技術監査・透明性基準の整備を急ぐこと。
→ プロトコルがどのように運営されているかを法的に定義し、
開発者・ユーザー双方の責任範囲を明確にする。
このアプローチは、「イノベーションを殺さずに安全性を確保する」ことを目的としています。
5. DEXの監督をめぐる政策的ジレンマ
著者は最後に、「過剰規制」と「放任」のどちらもリスクが高いと警告しています。
| 規制アプローチ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 強い規制(取引所と同等) | 投資家保護が強化される | 技術革新が阻害される |
| 放任(ノーガード) | 技術発展が自由 | 詐欺・マネロン・不正が横行 |
「調整型監督」はこの中間点に位置づけられます。
法的な明確性を確保しつつ、ブロックチェーン特有の自律性を尊重するバランスをとるのです。
6. 本章のまとめ
-
現行法では「責任のない市場」は想定外。
-
DEXには中央がないため、人ではなくコードとデータを監督対象にする必要がある。
-
著者の提案する「調整型監督」は、リスクに応じて柔軟にルールを変える新モデル。
結論として、著者は次のように述べています。
「DEXを規制対象から外すのではなく、既存の法体系をアップデートして透明性を基礎とした新たな監督構造を設計すべきである。」
第5章 結論 ― 法制度の再設計と未来展望
1. 1934年証券取引法の限界が浮き彫りに
著者がまず強調するのは、1934年の証券取引法(Exchange Act)が「中央集権的な取引所モデル」を前提に作られたという事実です。
当時は当然、
-
売買を仲介する組織(NYSEなど)
-
規制を受ける運営者
-
責任を負う取引所メンバー
が存在していました。
しかし、DEX(分散型取引所*はこれらの構造を根底から変えてしまいました。
DEXには「管理者」も「会員」も存在せず、
スマートコントラクトが取引を自動執行し、清算まで完結させます。
つまり―
「法の想定していない主体が市場を動かしている」
このギャップこそが、現行法ではDEXを「取引所」と定義できない最大の理由です。
2. 既存法の単純拡張では解決できない
SEC(米国証券取引委員会)は、「Rule 3b-16」の定義を拡張してDEXを射程に入れようとしています。
しかし、著者はそれを誤ったアプローチだと指摘します。
理由は以下の3点です。
-
責任の所在が特定できない
→ DEXは運営者不在のため、「登録義務者」が存在しない。 -
運営よりもコードが主体
→ 設計そのものが自律的で、法的主体(person, organization)が関与しない。 -
透明性確保の手段が異なる
→ 従来は開示書類(10-K, 8-Kなど)で透明性を担保したが、
DEXではオンチェーンデータとコードがその役割を果たす。
したがって、既存法を無理に拡張するのではなく、
「新しい法的カテゴリーを設計すべき」
というのが論文の主張です。
3. 著者の提言 ― Code-Based Regulationへの転換
論文の核心的提案は、「人ではなくコードを規制する」という発想への転換です。
具体的には
-
各DEXのスマートコントラクトを登録・認証する制度を導入。
-
透明性と安全性を確保するために、コードの第三者監査を義務化。
-
改変や不正が行われた場合は、ブロックチェーン上で自動検知・報告
つまり、規制の単位を「企業」から「コード」に移すわけです。
このアプローチは、
AI・自律システム・自動車の自動運転など、コードが人の代わりに判断する領域にも通じる構想です。
4. 政策的含意 ― SEC・議会・開発者それぞれの役割
著者は、DEXを取り巻く3つの主体が担うべき役割を次のように整理しています。
| 主体 | 求められるアクション |
|---|---|
| SEC | 「Exchange」の定義を再構築し、分散的市場に対応する監督モデルを策定する。 |
| 議会(Congress) | 証券取引法を改正し、「自律型市場(Autonomous Market)」を法的に位置づける。 |
| 開発者・DAO | コードの透明性・安全性・ガバナンスを強化し、自己監督的な仕組みを構築する。 |
これら3者の連携によって、
「法とテクノロジーの非対称性」を解消することがDEX時代の課題だと結論づけています。
5. 将来展望 ― DEX規制の新しい方向性
著者は、最終的に次のような未来像を描いています。
-
中央集権型と分散型が共存する市場構造
→ DEXは補完的な役割として、伝統市場の流動性を支援。 -
ブロックチェーン・ガバナンスによる自己規制の確立
→ DAO(自律分散型組織)が自ら透明性・安全性を担保。 -
RegTech / SupTechの導入
→ 規制当局もAI・ブロックチェーン技術を活用し、 オンチェーンデータをリアルタイムに監視。
「未来の取引所は、組織ではなく、コードとデータでできている」
著者は、そうした市場像を前提に、法制度がテクノロジーを敵視するのではなく、適応するべきだと結論づけています。
6. まとめ ― 法律と技術の「歩み寄り」
-
現行の証券取引法は、中央集権的な人による市場を前提にしている。
-
DEXは自律分散的に動作するコードによる市場。
-
この構造差から、現行法では「取引所」として扱うことができない。
-
よって、法の定義・監督の仕組みを再設計する必要がある。
著者は次のように締めくくっています。
Law must evolve to meet code — not by forcing code into old definitions
but by writing new ones that reflect the autonomy and transparency of digital markets.
(法律はコードに合わせて進化しなければならない。
旧来の定義に押し込むのではなく、デジタル市場の自律性と透明性を反映した新しい法を作るべきだ。)
用語解説 ― 専門用語をわかりやすく整理
1. DEX(Decentralized Exchange/分散型取引所)
ブロックチェーン上で自律的に動作する取引システム。
中央の管理者や運営会社を介さず、スマートコントラクト(自動契約プログラム)が取引を執行・清算まで完結させる。
代表例:Uniswap、SushiSwap、PancakeSwapなど。
特徴は「自律」「匿名性」「グローバルアクセス」。一方で、法的責任主体が不明確という課題がある。
2. Exchange Act(1934年証券取引法)
アメリカで制定された金融市場の根幹法。
株式や証券取引所を監督するために設計され、中央集権型の取引所(NYSEなど)を前提にしている。
この法律では、「取引所」とは、
「証券の売り手と買い手を一箇所に集め、取引を実現する組織的施設」
と定義される。
つまり、組織が運営し責任を負うことが前提。
これが、運営者不在のDEXが「取引所」と見なされない理由でもある。
3. Rule 3b-16(取引所の定義拡張ルール)
SEC(証券取引委員会)が定める「取引所」の補足定義。
2022年以降、このルールを改訂し、「通信プロトコル」や「自動売買システム」も“取引所”に含める動きが進んでいる。
ただし、DEXのように完全に分散化した仕組みは対象範囲が曖昧で、論争が続いている。
4. Smart Contract(スマートコントラクト)
条件が満たされたときに自動で実行される契約コード。
DEXでは、売買注文・価格決定・清算などの全プロセスがスマートコントラクト上で完結する。
人間の裁量が介在しないため、透明性が高い一方で、バグや悪意ある設計に対する責任の所在が不明確になりやすい。
5. Calibrated Oversight(調整型監督)
論文のキーワード。
「一律の規制ではなく、技術特性に応じて精密に調整された監督制度」を意味する。
DEXのような分散型システムには、中央管理者を前提とした旧来のライセンス制ではなく、
コード監査・オンチェーン監視・透明性保証といった新しいアプローチが必要、という考え方。
6. DAO(Decentralized Autonomous Organization/自律分散型組織)
ブロックチェーン上の投票・ガバナンスを通じて、中央の経営者なしに意思決定を行う仕組み。
DEXの多くはDAO形式で運営されており、トークン保有者が方針を決定する。
ただし、DAOも法的には「組織」として認められていない国が多く、規制設計上の空白が存在する。
7. RegTech/SupTech
金融当局・監督機関がテクノロジーを使って市場を監視・分析する仕組み。
RegTech(Regulatory Technology)は民間企業側のコンプライアンス技術、SupTech(Supervisory Technology)は当局側の監視システムを指す。
DEXのようなオンチェーン市場では、これらの技術が監督に不可欠とされている。
最終総括 ― 「コードが市場を動かす時代」の法の役割
分散型取引所(DEX)の登場は、「市場の主体が人間からコードへ移る」という歴史的転換をもたらしました。
これに対し、1934年制定の証券取引法は、「人間が運営する取引所」を前提としているため、現行制度ではDEXを取引所として定義・規制することが難しいのです。
著者が主張するのは明確です。
「旧来の法律にコードを押し込めるのではなく、コードを前提にした新しい法を設計すべきである。」
つまり、
この議論は、単に暗号資産やブロックチェーンだけの話ではありません。
AI、自動運転、ロボティクスなど――
「コードが意思決定を担う時代」において、責任・監督・倫理をどう再設計するかという普遍的な問いでもあります。
法律はテクノロジーの進化に追いつく必要があります。
そして今、DEXはその最前線に立っています。
関連する論文解説をもっと読みたい方は、[投資家のための最新研究論文まとめ] をチェックしてみてください。
本記事では、最新のファイナンス研究(SSRNなどの学術論文)を「個人投資家が実務で使える形」で要約・解説しています。ミクロ構造・流動性・市場心理など、価格変動の本質に迫る研究を厳選。 金融・経済論文まとめ:投資家のための最新研究【論文[…]