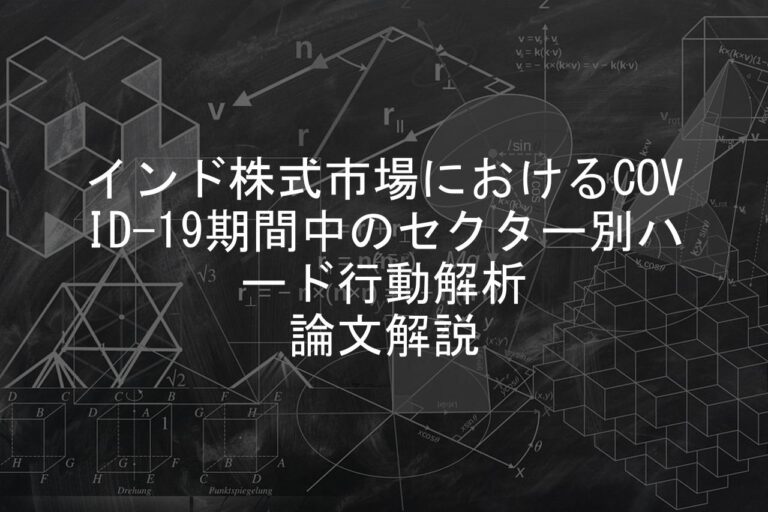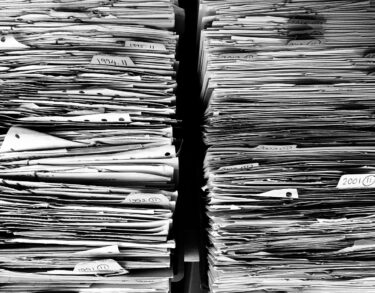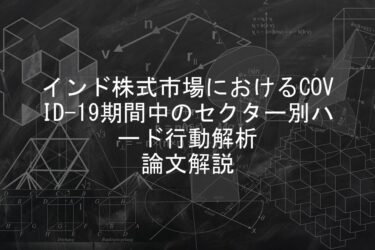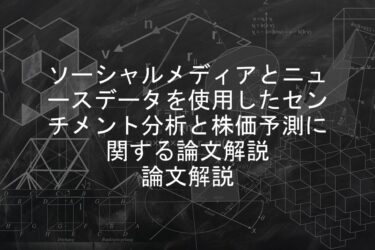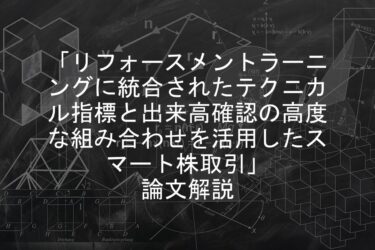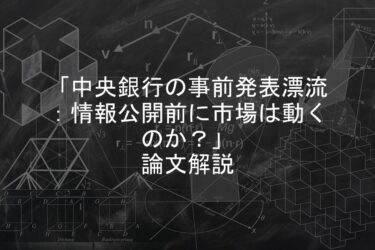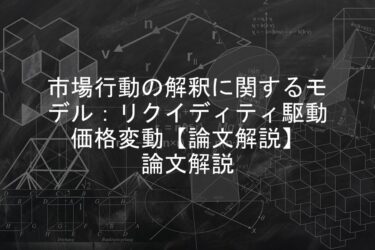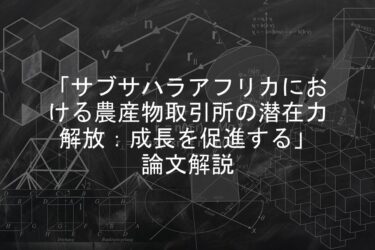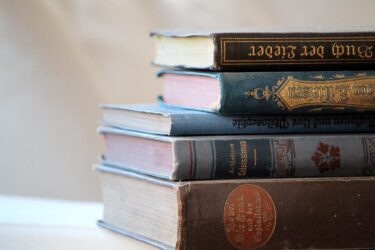論文:Sector-Wise Herd Behaviour In The Indian Stock Market During Covid-19
(新型コロナ禍におけるインド株式市場のセクター別羊群行動)
を分かりやすく解説・要約しました。
出典元:SSRN(2024/11/15掲載)
【論文解説】COVID-19下のインド株式市場:セクター別にみる群れ行動の実態
1. はじめに ― なぜ「群れ行動」が問題になるのか?
金融市場における群れ行動(Herd Behaviour)とは、投資家が自らの判断ではなく、他者の行動を模倣して意思決定する現象を指します。冷静な分析よりも「みんなが買っているから自分も買う」といった心理で動くため、バブルや暴落を助長する要因になると考えられています。
今回取り上げる論文 は、COVID-19パンデミック下のインド株式市場を対象に、セクターごとに群れ行動がどのように現れたのかを分析した研究です。
2. 研究の目的と分析手法 ― 「極端な市場環境」で投資家はどう動くのか
この研究の根底にある問いは、「市場が危機的状況に陥ったとき、投資家は合理的に振る舞えるのか?」 という点です。
通常、市場は効率的であるとされ、株価はすべての利用可能な情報を反映すると考えられています。しかし、パンデミックや金融危機といった極端な状況下では、この効率性が崩れ、投資家が「群れ行動」に走る可能性があります。
研究者たちは特にインド市場に注目しました。理由は以下の通りです:
-
新興市場特有の投資家構造:インド市場は機関投資家だけでなく、個人投資家の存在感が大きく、心理的要因が価格に強く作用する可能性がある。
-
COVID-19の衝撃:急速な感染拡大と経済封鎖(ロックダウン)は、企業活動や消費に直撃し、投資家心理を一気に不安定化させた。
-
セクター間の非対称性:例えば製薬(ファーマ)は追い風を受けた一方、自動車(オート)や消費財(FMCG)は需要の停滞に直面。この違いが「群れ行動」の度合いにどう現れるかを比較できる。
分析モデル
研究では、群れ行動の有無を測定するために金融実証研究で定番の以下のモデルを用いました。
-
Christie & Huang(1995)モデル
市場全体のリターンが大きく動く局面で、個別銘柄のリターンが市場平均にどの程度「収束」するかを確認。
→ 群れ行動が強いときは、銘柄ごとの動きが平均に近づきやすい。 -
Chang, Cheng & Khorana(2000)モデル
こちらはより一般化されたアプローチで、CSAD(Cross-Sectional Absolute Deviation:横断的絶対偏差) を用います。
CSADとは「個別銘柄の収益率が市場平均からどれだけ乖離しているか」を測る指標。
→ もし群れ行動がなければ、市場の平均リターンが大きくなるほど、銘柄間の分散も大きくなるはず。
→ 逆に、平均に収束していく傾向が強ければ、それは投資家が「他人に倣って動いている」サインと解釈できる。
データ範囲と対象
研究対象は、インド株式市場を代表する主要5セクター(FMCG、オート、ファーマなど)に属する106社の株式データ。さらに、インドを代表する指数である NIFTY50 を含め、セクターごとの比較も行いました。
このように、単に市場全体を見るだけでなく、「セクターごとの違い」に焦点を当てた点が本研究の特徴です。なぜなら、パンデミック下ではすべての産業が一様にダメージを受けるわけではなく、医薬・消費財のように相対的に強い分野もあれば、自動車・製造業のように需要が蒸発する分野もあるからです。
3. 主な研究結果 ― パンデミックは投資家心理をどう変えたのか
COVID-19以前 ― アンチ・ヘルド行動の存在
パンデミック前の平常時においては、いくつかのセクターで「アンチ・ヘルド行動(Anti-Herd Behaviour)」が観測されました。
これは、投資家が「他人と同じ行動を取らない」「むしろ逆に動く」傾向を意味します。
-
市場平均が上昇しても、特定の投資家は逆に売る
-
市場平均が下落しても、むしろ買い増す
COVID-19後 ― 群れ行動の顕著化
一方で、パンデミックが発生すると状況は一変しました。感染拡大やロックダウンによる不確実性が高まる中で、投資家はリスクを取らず「他人の行動に追随する」傾向を強めました。
特に群れ行動が顕著に現れたのは次の3セクターです:
-
FMCG(生活必需品)
「生活に必須の商品を扱う企業は安全」と考えられ、多くの投資家が一斉に買いに走りました。結果として、同セクター銘柄の動きが市場平均に強く収束しました。 -
自動車(オート)
実際には需要減で業績が落ち込みましたが、「皆が売るから自分も売る」という連鎖が起き、群れ行動が増幅。ネガティブ方向での追随行動が観測されました。 -
製薬(ファーマ)
パンデミックの恩恵を受ける可能性が高いとされ、投資家はこぞって製薬株を買い集めました。「みんなが買うから自分も買う」という典型的なポジティブ方向の群れ行動です。
投資家心理の変化
-
平常時 → 自律的で逆張り的な投資行動も見られる
-
危機時 → 「判断を他人に委ねる」追随行動が支配的になる
この結果は「平常時は効率的に見える市場も、危機になると一気に非効率に傾く」という、行動ファイナンスの核心を裏付けていますね。
4. 研究の意義 ― 危機下で「市場は人間的になる」
① 平時と危機で市場の性格が変わる
-
平時は、投資家どうしの見解が分かれやすく収益の分散=CSADが大きくなりがち。
-
危機時は、不確実性が跳ね上がり「様子見→追随」の連鎖が起き、CSADが市場リターンの絶対値に対して非線形に縮む(Chang 等の枠組み)。
→ つまり、危機は多様な意見を消し、同じ方向に向かせる力を持つ。
② 群れ行動は価格を割高にも割安にも動かす
-
FMCG/ファーマのような「守り・テーマ銘柄」では過度の買い集中→バリュエーションのゆがみ。
-
オートなど景気敏感では悲観一色→売られ過ぎ。
→ 群れが強いほどリバース(反転)局面のボラティリティが増幅する。
③ セクターごとの資金の集まり方を読む重要性
-
同じ市場でも、ディフェンシブ/景気敏感/政策関連で群れの出方が違う。
-
実務では「どのセクターに資金が雪崩れているか」を、CSAD+出来高+資金フロー(ETF フロー等)で多面的に把握する必要。
④ 行動ファイナンスの実証補強
-
「恐怖・不確実性→追随」のメカニズムをセクター別に分解して示した点が新味。
-
危機が来るたびに市場が非効率化する“条件”を特定することで、危機時の投資ルールを設計しやすくなる。
5. 今後の研究課題 ― 測り方を増やし、状態に応じて読む
① 指標の拡張:価格×量×フロー
-
CSADに加え、出来高(異常出来高・回転率)、ETF/ミューチュアルファンドのフロー、オプションのプット/コール・スキューも併用。
-
価格の収束だけでなく、資金の“偏りを直接観測する。
② 状態依存(Regime)を明示
-
マルコフ転換やTVP(時間可変パラメータ)で、平時と危機時でパラメータが切り替わるモデルを推奨。
-
分位点回帰(Quantile)で、下落相場(左裾)における群れ強度を特定。
③ マイクロストラクチャに踏み込む
-
板厚・スプレッド・オーダーフロー不均衡を投入し、追随が価格形成のどの段で強まるかを把握。
-
投資主体(個人/機関)別の売買代替指標が取れれば、誰の群れかまで識別可能。
④ クロスマーケット比較とイベント設計
-
他国・他市場(先物/オプション)とのスピルオーバーを検証。
-
政策発表・ロックダウン・ワクチン報などのイベント窓を明示し、事前・直後・フォロー期間で群れの時間構造を測る。
⑤ 機械学習の支援活用
-
ブースティング/ランダムフォレストで群れ強度の説明要因をスクリーニング。
-
ただし、過学習と取引コストの評価を必ず同時実装(ウォークフォワード+HAC誤差等)。
用語解説
CSAD(Cross-Sectional Absolute Deviation)
株式市場全体の平均リターンから、各銘柄のリターンがどのくらい散らばっているかを測る指標。
分散が小さいと「みんな同じ方向に動いている=群れ行動がある」と判断できる。
マルコフ転換モデル
市場が「平時」と「危機時」のように異なる状態(レジーム)を行き来すると仮定して、それぞれの状態で異なるパターンを推定する統計モデル。
時間可変パラメータ(TVP)モデル
時間の経過に応じて分析パラメータが変化するモデル。市場環境が常に変動することを前提にしている。
分位点回帰(Quantile Regression)
平均ではなく「下位◯%のデータ」に焦点を当てた回帰分析。
例えば「相場が大きく下落している局面」で群れ行動が強まるかどうかを測定できる。
マイクロストラクチャ
「板」「スプレッド」「注文フロー」など、市場の細かい仕組み(注文がどのように価格に反映されるか)を指す。
群れ行動がどの段階で強まるかを分析できる。
オプションのプット/コール・スキュー
プット(売る権利)とコール(買う権利)の需要の偏りを表す指標。投資家心理の「恐怖/強気」のバランスを読み取れる。
スピルオーバー効果
ある市場で起きた動きが、他の市場(先物、他国株式など)に波及する現象。
ブースティング/ランダムフォレスト
機械学習でよく使われるアルゴリズム。多くの説明要因の中から、群れ行動に効いている要素を自動的に選び出すのに役立つ。
ウォークフォワードテスト
機械学習や投資モデルの検証方法のひとつ。過去データで学習し、その後の期間で実際にどのくらい予測できたかを順番に検証する。
HAC誤差(Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Errors)
誤差が「一定でなく偏っている」「系列的につながっている」場合にも、信頼できる検定ができるように補正した標準誤差のこと。
6. まとめ ― 投資家のための「危機時プレイブック」
A. まず群れの発生を早期検知
-
CSAD の非線形性(|Rm| と Rm²の係数)が立ち上がるかをローリングで監視。
-
併せて異常出来高・ETF流入超過・スプレッド拡大をチェック。
-
ニュース/ソーシャルのセンチメント急変(極端語・恐怖語の比率)も補助指標に。
B. 群れが強いセクターでの基本戦術
-
順張りの短期回転:トレンドの走りはじめに乗る(ただし出来高減速・乖離拡大で利確)。
-
逆張りの選別:ファンダに対し過剰に売られた景気敏感でスプレッド縮小・リバウンドを狙う。
-
同業ペアの相対価値:同テーマ内の過熱銘柄を売り、出遅れ品質銘柄を買うペアトレードで群れの歪みを回収。
C. リスク管理はいつもより厚めに
-
ポジションサイズを段階式(ピラミッディングではなく分割入出)。
-
ボラティリティ連動のストップ(ATR 基準)+時間ストップ(ニュースイベント跨ぎを避ける)。
-
ヘッジ手段:セクターETFの反対売買/プットオプションの部分ヘッジでテールを遮断。
-
流動性規律:板の薄い小型は約定影響コストを織り込み、サイズを落とす。
D. 判断の作法
-
「皆が買っている/売っている」ではなく、資金がどこから来てどこへ向かうかを見る。
-
入る理由と出る条件を先に書く(価格・時間・ファンダのいずれかで間違いの証拠を定義)。
-
事後レビュー:群れに“乗れた/飲み込まれた”要因を毎トレードでログ化し、再現と回避のルールに落とす。
セクターごとの群れを定量把握し、順張りは機敏に/逆張りは選別的に、そしていつも以上に流動性とリスクをケアする――これが勝ち残る設計図です。
本記事では、最新のファイナンス研究(SSRNなどの学術論文)を「個人投資家が実務で使える形」で要約・解説しています。ミクロ構造・流動性・市場心理など、価格変動の本質に迫る研究を厳選。 金融・経済論文まとめ:投資家のための最新研究【論文[…]