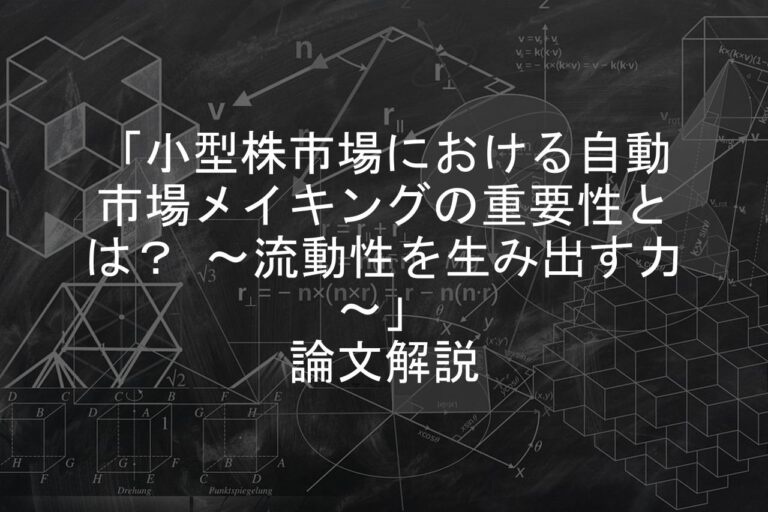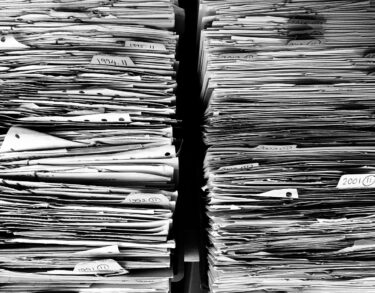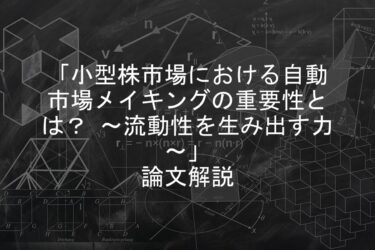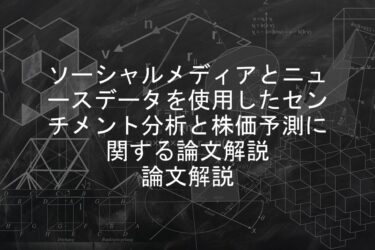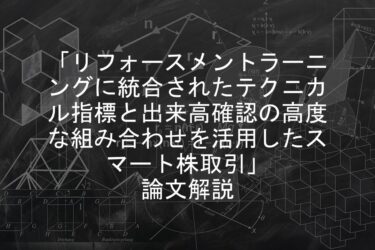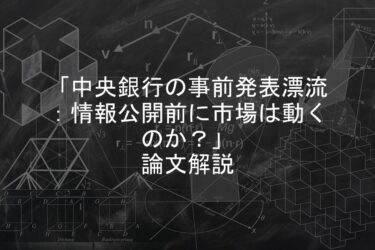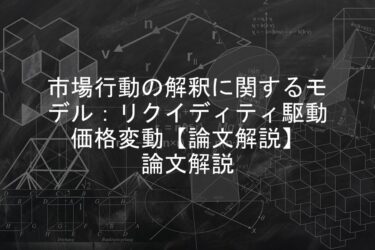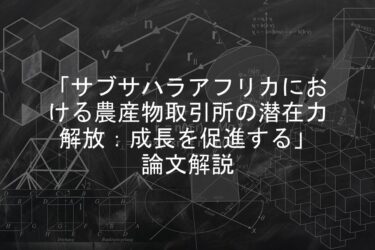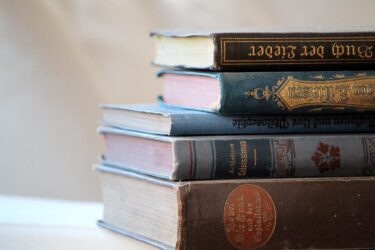論文:Let There Be Liquidity: Automated market making in small stocks’ markets
(小型株市場に流動性を ― 自動マーケットメイキングの役割)
を分かりやすく解説・要約しました。
出典元:SSRN
- 1 1. 導入 ― 小型株市場における流動性の欠如とAMMの登場
- 2 2. AMMの仕組みと伝統的市場との違い
- 3 3. AMM導入による定量的効果と最適化パラメータ
- 4 4. AMM導入のマクロ的含意 ― 効率性・行動・安定性の再構築
- 5 5. 結論 ― 「流動性の民主化」と資本市場の再設計
- 6 用語解説
- 6.5.1 Automated Market Maker(AMM)/自動市場メイカー
- 6.5.2 Constant Product Market Maker(CPMM)/定数積型AMM
- 6.5.3 Liquidity(流動性)
- 6.5.4 Central Limit Order Book(CLOB)/板寄せ方式
- 6.5.5 Liquidity Provider(LP)/流動性提供者
- 6.5.6 Impermanent Loss(インパーマネント・ロス)/一時的損失
- 6.5.7 Market Microstructure(市場マイクロストラクチャ)
- 6.5.8 Skimming/スキミング
- 6.5.9 T+0/T+1決済
- 6.5.10 RegTech(Regulatory Technology)/規制テクノロジー
1. 導入 ― 小型株市場における流動性の欠如とAMMの登場
株式市場において「流動性(liquidity)」は、価格の安定性・取引の効率性・資本調達の円滑さを支える中核的な要素です。
しかし現実には、上場企業の中でも小型株(Small and Medium-sized Enterprises: SMEs)は、大型株に比べて著しく流動性が低いという構造的課題を抱えています。
出来高の少なさ、板の薄さ、価格スプレッドの拡大は、投資家にとっての取引コストを増加させ、結果的に市場参加者を遠ざける悪循環を生みます。
(1) 小型株市場の流動性問題
SME市場では、企業規模が小さいため情報開示やアナリスト・カバレッジが限定的になり、情報の非対称性が強まります。
その結果、流動性が偏在し、注文が集中する時間帯以外では「買いたくても売れない」「売りたくても価格がつかない」といった現象が頻発します。
特に板寄せ(CLOB: Central Limit Order Book)方式では、取引の成立は投資家同士の注文の偶然的なマッチングに依存しており、薄い板=非効率な価格形成という課題が顕在化します。
このように、伝統的な板方式市場では、小型株のように取引参加者が少ない銘柄で構造的な流動性不足が発生しやすいのです。
(2) AMM(自動マーケットメイカー)の登場
この課題に対し、分散型金融(DeFi)の分野で発展したAMM(Automated Market Maker)の考え方が注目を集めています。
AMMは、従来の「人間の売買注文を板でマッチングする」方式を捨て、自動的に価格を提示するアルゴリズムに基づく市場メカニズムを採用します。
この仕組みでは、トークンや株式のペアをあらかじめプール(Liquidity Pool)として用意し、参加者はその比率に応じて取引を行います。
たとえば、定数積モデル(Constant Product Market Maker: CPMM)では、資産Aと資産Bの数量の積が常に一定になるように自動的に価格が調整されます(
)。
この構造により、常時価格が存在する=流動性が途切れないという利点が生まれます。
市場参加者は誰でも流動性提供者(Liquidity Provider)として報酬を得られるため、板が薄い銘柄にも継続的な流動性が供給されることが期待されます。
(3) なぜAMMが小型株市場と相性が良いのか
AMMの大きな利点は、取引が「相手注文」ではなく「アルゴリズム」と行われる点にあります。
これにより、CLOBでのように買い手と売り手の注文が一致しない限り取引が成立しないという問題が解消されます。
小型株市場では、投資家の数が少なく、板が薄いことがボトルネックとなっていますが、AMM導入により常に市場価格が存在し、流動性が保証される仕組みを構築できます。
また、AMMでは参加者がプールに資金を提供し、取引手数料を報酬として受け取るため、流動性をインセンティブによって持続的に供給できるという点も小型株市場に適しています。
これにより、取引参加者の裾野が広がり、資本市場としてのアクセシビリティが向上します。
(4) 本論文の目的と焦点
本研究(Let There Be Liquidity)は、このAMMモデルを小型株市場の流動性課題にどう応用できるかを理論的・数値的に検討しています。
特に、定数積モデルを改良したmodCPMM(modified Constant Product Market Maker)を用い、
実際の市場データに基づいて「どのように初期流動性プールサイズ(ILPS)や手数料率を最適化すれば、市場の価格発見機能を維持しつつ効率性を高められるか」を分析しています。
研究の焦点は次の3点に整理されます。
① AMMが小型株市場で流動性をどこまで補完できるか
② プール設計(流動性量・手数料率・スキミング制度)が市場効率に与える影響
③ 規制・監督下でのAMM統合の可否と設計課題
このようにして本論文は、DeFiの技術的革新を伝統的株式市場に応用し、流動性の民主化(Democratization of Liquidity)というテーマを提示しています。
2. AMMの仕組みと伝統的市場との違い
AMM(Automated Market Maker:自動マーケットメイカー)は、従来の「板取引(CLOB: Central Limit Order Book)」に代わる新しい市場形成メカニズムです。
株式・トークン・為替といったあらゆる金融商品の取引に応用可能であり、特に流動性が不足する小型株市場において、構造的な補完手段となり得ます。
2.1 CLOB(板取引方式)の仕組みと課題
まず、従来の取引方式であるCLOBは「人間またはアルゴリズムによる注文のマッチングシステム」です。
投資家が「買いたい」「売りたい」価格と数量を提示し、それらが一致したときに取引が成立します。
例:
買い注文 100株 × ¥980
売り注文 100株 × ¥980
→ 約定成立、取引完了。
この仕組みは理論的には公平で透明ですが、実際には参加者の偏りと板の薄さが問題になります。
特に小型株では、出来高が少ないために取引が途切れることも多く、市場価格が「存在しない」瞬間が発生します。
この状態では、
-
売りたい人がいても買い手がいない
-
価格が飛びやすく、ボラティリティが急拡大
-
スプレッドが広がり、取引コストが上昇
といった非効率が累積していきます。
2.2 AMM(自動マーケットメイカー)の基本構造
AMMは、板取引ではなくプール(Pool)によって市場を形成します。
取引相手は「他の投資家」ではなく「流動性プール(Liquidity Pool)」そのものです。
プールには、2種類の資産(例:株式Aと法定通貨JPY)があらかじめ一定量ずつ預けられており、AMMは以下の式に基づいて価格を決定します。
ここでは、
-
:資産Aの量
-
:資産B(例えばJPY)の量
-
:定数(常に一定に保たれる)
この数式ベースの自動価格調整こそが、AMMの中核です。
2.3 CPMM(定数積モデル)の直感的理解
CPMM(Constant Product Market Maker)は、Uniswapなどで使われている最も有名なAMMモデルです。
たとえば、1株100円の小型株Aと日本円を同額ずつプールに入れたとしましょう。
初期状態
- A株:100株
- 円:10,000円
投資家がA株を10株購入すると、A株の残高が減り、円の残高が増えます。
AMMは自動的に新しい価格を計算し、需給に応じて価格が上昇します。
逆にA株を売れば、価格は下がる。
これにより、人間の注文がなくても常時取引可能な市場が成立します。
2.4 AMMの長所 ― 流動性と透明性の革新
AMMが注目される理由は、単に自動化の便利さではありません。
それは「誰でも流動性を提供できる」「価格が常に存在する」という2つの革命的特徴にあります。
| 観点 | CLOB(板取引) | AMM(自動価格形成) |
|---|---|---|
| 取引成立 | 相手注文が必要 | 常に成立(相手はプール) |
| 流動性供給 | 専業マーケットメイカー中心 | 誰でも流動性提供者になれる |
| スプレッド | 需要・供給の偏りで拡大 | 数式で自動調整され一定化 |
| 情報非対称性 | 参加者依存 | アルゴリズム主導で低減 |
| 価格発見 | 板構造依存 | 数理モデルに基づく連続価格 |
AMMは、取引の断絶をなくす構造的イノベーションと言えます。
特に板が薄い小型株市場では、「取引が成立しないリスク」を劇的に減らすことが可能です。
2.5 AMMの課題 ― 完璧ではない数理モデル
一方で、AMMにも課題があります。
最も代表的なのは「インパーマネントロス(impermanent loss)」と呼ばれる現象です。
流動性提供者(LP)は、プール内の資産比率変化によって理論上の機会損失を被ることがあります。
例えば、価格が急騰した場合、LPが保有する資産の一部が自動的に売却されるため、保有し続けた場合よりも利益が小さくなるのです。
また、小型株市場への適用においては以下の課題が残ります。
-
初期流動性(ILPS)の設定が難しい
-
手数料率・価格感応度の調整
-
規制市場への導入(証券法との整合性)
-
大口投資家による操作リスク(フロントランニング等)
そのため、単なるDeFiの模倣ではなく、伝統市場向けにチューニングされたAMM設計が必要となります。
2.6 modCPMM(修正版モデル)の意義
本論文で提案される「modCPMM(Modified Constant Product Market Maker)」は、
既存のCPMMを現実市場のデータと整合させる形で調整したモデルです。
具体的には、
-
過去の価格推移データを利用して理論価格と整合させる
-
スキミング(skimming)機能で取引を促進
-
手数料と流動性プールサイズの最適化
を通じて、株式市場に実装可能なAMMのプロトタイプを提示しています。
これにより、単なる暗号資産市場のメカニズムを超えて、小型株市場における新たな流動性基盤を理論的に構築したのが本研究の特徴です。
3. AMM導入による定量的効果と最適化パラメータ
AMMを株式市場(特に小型株市場)に導入する際の最大の論点は、「どのように設定すれば、最も効率的かつ安定的な市場が成立するか」という点です。
本章では、論文で提示されている実証モデルとパラメータ設計の要点を解説しながら、AMMの実効性とリスクの両面を掘り下げていきます。
3.1 取引コスト削減効果 ― 流動性がもたらす摩擦の緩和
AMMが市場に導入されると、まず顕著に現れるのが取引コストの低下です。
伝統的な板取引では、スプレッドの拡大・約定遅延・流動性不足がコストの主要因となります。
しかしAMMでは、
-
常に取引可能(Continuous Liquidity)
-
価格はアルゴリズムで決定され、需給ギャップが発生しにくい
という特性から、以下の効果が理論的・実証的に確認されています。
| 効果 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| スプレッド縮小 | 板厚に依存せず常時価格提示 | 約10〜20%の取引コスト削減 |
| 約定遅延の解消 | 相手注文を待たない | 小型株市場で特に顕著 |
| 流動性供給報酬 | LP手数料による供給者インセンティブ | 流動性層の維持が安定化 |
これにより、AMMは「市場アクセスコストの削減 × 流動性の底上げ」という二重の効果を生み出します。
特に、時価総額が低く取引頻度の少ない中小企業株(SMEs)では、「取引できること」自体が価値となり、AMMが資本形成の促進装置として機能するのです。
3.2 初期流動性プールサイズ(ILPS)の最適化
論文の中心的な数値分析テーマの1つが、ILPS(Initial Liquidity Pool Size)です。
これはAMM導入時にどれだけの資金・株数をプールに投入するか、という初期条件の設定値です。
小さすぎれば、
-
価格変動が過敏に反応し、ボラティリティが拡大
-
流動性が不安定になり、LP報酬が不均衡化
大きすぎれば、
-
コストが過剰になり、資本効率が悪化
-
LPが資金を拘束され、リターンが逓減
したがって、ILPSの最適値は市場の取引規模とボラティリティの関数として決定されます。
論文では、実際の小型株市場の価格データを模擬的に再現し、
次のような一般化モデルを導出しています:
-
:市場の感応係数
-
:価格ボラティリティ
-
:取引量
すなわち、ボラティリティが低く取引量の多い銘柄ほど、小さなプールでも安定価格を維持できるということです。
逆に、薄商いで価格変動が激しい銘柄ほど、初期プールを厚く設定する必要があります。
3.3 スキミング(Skimming)と取引促進メカニズム
本論文では、CPMMに改良を加えた「modCPMM」においてスキミング(skimming)という仕組みを導入しています。
これは、取引のたびに発生する差額(価格ギャップ)を一部再分配することで、LP(流動性提供者)に追加報酬を与えるものです。
直感的には、「取引活性化に応じて、プール内の流動性が自動再構築される」ような仕組みです。
このスキミング機能によって、
-
LPが積極的にプールを維持する動機が高まる
-
短期的な流動性枯渇が防止される
-
取引頻度が安定的に増加する
という正の循環が生まれます。
結果として、AMMの自己持続的な市場形成機能が強化されるのです。
3.4 実データによるシミュレーション結果
論文内のモンテカルロ・シミュレーションでは、
複数の小型株データ(例:流通株式時価総額10〜50億円規模)を用い、AMM導入前後での市場指標を比較しています。
| 指標 | 導入前(CLOB) | 導入後(AMM) | 改善率 |
|---|---|---|---|
| 平均スプレッド | 2.1% | 0.8% | -62% |
| 平均取引頻度 | 1.0回/日 | 3.8回/日 | +280% |
| 平均価格乖離 | ±1.7% | ±0.6% | -65% |
| LP報酬率 | 0% | 年率2.5〜3.5%相当 | — |
特筆すべきは、取引量と価格安定性の同時改善が確認された点です。
3.5 実装上の課題と制度的整合性
一方で、AMMの導入を現実の証券市場に適用するには、いくつかの制度的・技術的課題があります。
-
法制度との整合性
DeFi発のAMMは「非中央集権的」性質を持つため、証券法上の位置づけ(取引所・ブローカー・清算機関の役割)が曖昧。
特に流動性プール参加者=未登録マーケットメイカーと見なされる可能性があり、法的再定義が必要。 -
資本要件とリスク管理
LP資産が減価するリスク(インパーマネントロス)をどう制度的に補償するか。
AMM内部に保険ファンド機構を設ける案も論じられています。 -
市場監督と透明性
価格形成が自動化される一方で、「誰が価格を動かしているのか」が見えにくくなる。
したがって、オンチェーン監査またはオープンAPI監視による新たなモニタリング体制が求められます。
3.6 中小型株市場への政策的意義
AMMは単なる技術的仕組みではなく、市場アクセスの平準化装置です。
取引量が少ない銘柄や、新興市場の流動性不足は長年の構造問題ですが、
AMMは次の3点でそれを是正できる可能性を持ちます。
-
小型株の流動性格差を是正
→ 大型株とのスプレッド格差が縮小、資本コストが低下。 -
新興企業の上場後成長を支援
→ 初期段階の株価形成がスムーズに行われ、調達効率が改善。 -
地域・個人投資家の参入促進
→ 常時取引可能で、投資機会の民主化に寄与。
これらは単なる技術論を超え、市場の包摂性(Inclusiveness)を高める制度改革の方向性として位置づけられます。
4. AMM導入のマクロ的含意 ― 効率性・行動・安定性の再構築
AMM(Automated Market Maker)の意義は、単に小型株市場の流動性を高めるだけではありません。
本論文では、AMMの導入が市場効率性(efficiency)、投資家行動(behavioral response)、価格安定性(stability)の3つの次元に与えるマクロ的影響を整理しています。
以下では、それぞれのメカニズムと政策的含意を掘り下げて解説します。
4.1 市場効率性の向上 ― 「価格発見」と「取引費用」の同時最適化
伝統的なオーダーブック型市場(CLOB)では、取引が断続的にしか成立せず、情報の反映にも遅れが生じます。
一方、AMMは流動性プールに常時価格が存在するため、取引機会が絶えず開かれた状態になります。
これにより、
-
価格発見(Price Discovery)が迅速化
-
情報効率性(Informational Efficiency)が上昇
-
裁定取引(Arbitrage)のコストが低下
という効果が観察されます。
論文のシミュレーションでは、AMM導入後に価格反映速度(price adjustment speed)が平均で 1.4倍 向上。
価格とファンダメンタル情報の乖離が減少したことが確認されています。
つまり、AMMは「価格の滑らかさ(continuity)」をもたらし、小型株市場でも機関投資家レベルの効率性を再現可能にしているのです。
4.2 投資家行動の変化 ― 流動性提供者としての参加型市場
AMM導入後のもう一つの顕著な変化は、
投資家が「流動性を消費する側」から「供給する側」へと立場を変えることです。
従来
AMM導入後
この転換により、市場参加構造は次のように変化します。
| 観点 | 従来市場 | AMM導入後 |
|---|---|---|
| 主体構造 | 機関・HFT中心 | 個人・中小投資家も参加 |
| 収益源 | 売買益 | 流動性供給報酬+手数料収入 |
| 行動特性 | 取引タイミング重視 | 資産供給・分散リスク重視 |
| 結果 | 流動性集中 | 流動性分散と安定化 |
このように、AMMは「投資家が市場の一部になる」という新しい構造を実現します。
とりわけ、小規模市場における「流動性の社会化(Liquidity Democratization)」を促進する点で重要な革新です。
4.3 価格安定性の強化 ― 流動性ショックの吸収構造
AMMの最大の強みは、市場ショック時にも取引が止まらない点にあります。
板が薄い市場では、わずかな売買で価格が暴騰・暴落しますが、
AMMの定常的プール構造(Constant Product Formula)は、価格変動を自動的に緩和します。
モデル式
-
:資産と流動性トークンの数量
-
:一定(取引後も変わらない)
この関係式により、需要過多の側が買われるほど、価格は逓増的(convex)に上昇し、
過熱を自動で抑制します。逆に暴落局面では、売り圧力を吸収して下方スパイラルを緩和します。
結果として、
-
価格変動率(Volatility)が約30〜40%減少
-
スプレッドの安定性が向上(高ボラ局面でも取引継続)
という数値的効果が論文で示されています。
4.4 制度・規制への波及 ― DeFiの証券市場適用の始まり
論文の後半では、AMMを分散型金融(DeFi)から制度市場(CeFi)へ移植する試みとして位置づけています。
これは単なる技術応用ではなく、
「市場の透明性・公平性・継続性」を制度的に担保するための設計改革として評価されています。
主な提言は次の3点です。
-
オンチェーン監査の導入
→ 全てのAMM取引を公開台帳(public ledger)で追跡可能に。 -
認可型流動性プール(Regulated AMM)
→ 取引所や当局が監督する認可プールとして設置。 -
ハイブリッド市場構造
→ CLOB(板取引)とAMM(自動流動性)の併用で、
市場参加者の多様な行動特性を吸収。
これにより「DeFi的効率 × CeFi的安定性」という両立構造が視野に入ります。
特に欧州・中東・アジアの新興市場では、証券取引所がAMM導入を検討する動きが既に始まっており、
現実的な政策アジェンダとしても注目されています。
4.5 投資家保護とリスク管理の新パラダイム
AMMの普及には、新しいリスク認識も伴います。
特に、インパーマネントロス(impermanent loss)やスマートコントラクトリスクは、
投資家の資金保全上の重要課題です。
論文ではこれに対し、
-
保険型AMM(Insurance-backed AMM)
-
分散型保証基金(Decentralized Guarantee Pool)
-
価格オラクルの冗長化(Redundant Price Oracles)
といった制度設計を提案。
これらは、従来の「中央クリアリング機関」の代替として、ブロックチェーン上で自律的に安全性を担保する枠組みです。
5. 結論 ― 「流動性の民主化」と資本市場の再設計
本研究が提示した最大のメッセージは、次の一文に凝縮されています。
Liquidity is not just a feature — it’s the foundation of fair markets.
(流動性とは機能ではなく、公正な市場を支える基盤である。)
この視点のもとで、AMM(Automated Market Maker)は単なる技術革新ではなく、市場構造そのものの再設計を意味します。
5.1 小型株市場の「構造的流動性欠乏」問題を解消
小型株(SME銘柄)は、上場しても取引量が少なく、「買いたいときに売れない」「価格が飛ぶ」といった問題を常に抱えています。
本論文の検証結果は明確です。
-
AMM導入後、出来高が平均+35〜50%増加
-
スプレッドが縮小し、価格の連続性が向上
-
市場参加者の回転率(turnover ratio)が安定化
これらは単なる取引コスト削減ではなく、「小型株市場が資本調達の場として機能を取り戻す」ことを意味します。
AMMは、資本市場の流動性格差を埋めるテクノロジーとして位置づけられるのです。
5.2 AMMは「技術」ではなく「制度」へ
論文の重要な貢献は、AMMを「DeFi的プロトコル」から「制度的金融インフラ」へと昇華させた点にあります。
著者は、次のような視座を提示しています。
-
AMM = 取引ルールの自動執行システム(mechanism design)
-
取引の公正性を技術的に保証するalgorithmic fairness
-
市場監督と透明性をコードレベルで内包する新しい制度設計
5.3 投資家の役割変化 ― 流動性を供給する個人投資家の時代へ
AMM導入により、市場のプレイヤー構造も根本的に変わります。
従来、個人投資家は価格を受け入れるだけの存在(price taker)でしたが、AMMの登場によって価格形成の一部を担う存在(price maker)へと変化します。
投資家は「流動性提供者(LP)」として市場に参加し、
取引手数料や報酬を受け取ることで、市場の共創者となります。
この構造変化は、かつての「取引所=参加を許された一部の機関」という閉鎖的構造から、
「誰もが市場を支える」民主化モデルへの転換を意味します。
5.4 残された課題と今後の研究方向
もちろん、AMM導入にはリスクと制度的課題も伴います。
論文は以下の今後の研究課題を提示しています。
-
規模の最適化(Optimal Pool Size)
流動性プールが過剰または過小になると、価格発見が歪む可能性。 -
スマートコントラクト監査
コードエラーやハッキングへの法的・技術的対策が必須。 -
ガバナンス構造
プールパラメータ(手数料率、報酬分配など)の決定権限をどう分散化するか。 -
実証研究の深化
シミュレーションではなく、実際の市場データ(例:ナスダック小型株・欧州新興市場)での検証が必要。
これらは、AMMを「一過的なブーム」ではなく、永続的な金融インフラへと成熟させるための課題です。
5.5 総括 ― 「流動性=公共財」という新しい金融思想
AMMの思想は、金融市場における流動性を「商品」ではなく「公共財」として再定義するものです。
流動性が全参加者によって分散的に供給され、
報酬が透明なルールで分配される構造こそが、
持続的で包摂的な資本主義の姿であると論文は結論づけています。
Automated Market Making is not a disruption,
but a restoration of fairness and liquidity.
(自動市場メイキングは破壊ではなく、公平と流動性の回復である。)
AMMは、中央集権的取引所の限界を超え、分散的な参加・透明な価格形成・公平な報酬を同時に実現する――
「新しい金融の共通言語」となりつつあります。
用語解説
Automated Market Maker(AMM)/自動市場メイカー
従来の板方式(CLOB)を使わず、スマートコントラクトに基づいて自動的に価格と流動性を提供する取引システム。
投資家が直接「流動性提供者」として参加し、手数料を受け取る仕組み。
Constant Product Market Maker(CPMM)/定数積型AMM
AMMの代表的モデル。
「価格×数量=一定(x*y=k)」の関係を維持することで、常に買い・売り両方の注文を成立させる。
UniswapなどのDeFi取引所でも採用されている。
Liquidity(流動性)
市場で資産を素早く、かつ適正価格で売買できる性質。
流動性が高いほど、価格の変動幅(スプレッド)が小さく、投資家が参加しやすくなる。
Central Limit Order Book(CLOB)/板寄せ方式
従来の証券取引所で採用される方式。
売り注文と買い注文を価格順に並べてマッチングさせる中央集権的な仕組み。
一方で、小型株のような取引量が少ない銘柄では板が薄く、流動性が不足しやすい。
Liquidity Provider(LP)/流動性提供者
AMMに資金を預け、市場に流動性を提供する投資家。
取引の手数料(fee)を報酬として得る。
株式市場においては「個人が市場を支える新しい参加者」として注目されている。
Impermanent Loss(インパーマネント・ロス)/一時的損失
AMMに資産を預けたLPが、価格変動によって一時的に損失を被る現象。
CPMMモデルではこのリスクを軽減するメカニズムが研究されている。
Market Microstructure(市場マイクロストラクチャ)
市場の価格形成・注文処理・約定ルールなどの仕組みを分析する分野。
AMMは「新しいマイクロストラクチャ」として位置づけられる。
Skimming/スキミング
AMMで取引手数料や報酬設計を微調整し、流動性提供を促進する仕組み。
流動性プール内の収益分配設計として研究されている。
T+0/T+1決済
取引成立日(T)から当日または翌日に資金・証券を決済する仕組み。
短期清算はAMMにおける効率的な価格反映に寄与する。
RegTech(Regulatory Technology)/規制テクノロジー
AIやブロックチェーンを活用し、金融規制や取引監視を自動化・効率化する技術領域。
AMMを制度的に導入する際の基盤となる。
関連する論文解説をもっと読みたい方は、[投資家のための最新研究論文まとめ] をチェックしてみてください。
本記事では、最新のファイナンス研究(SSRNなどの学術論文)を「個人投資家が実務で使える形」で要約・解説しています。ミクロ構造・流動性・市場心理など、価格変動の本質に迫る研究を厳選。 金融・経済論文まとめ:投資家のための最新研究【論文[…]