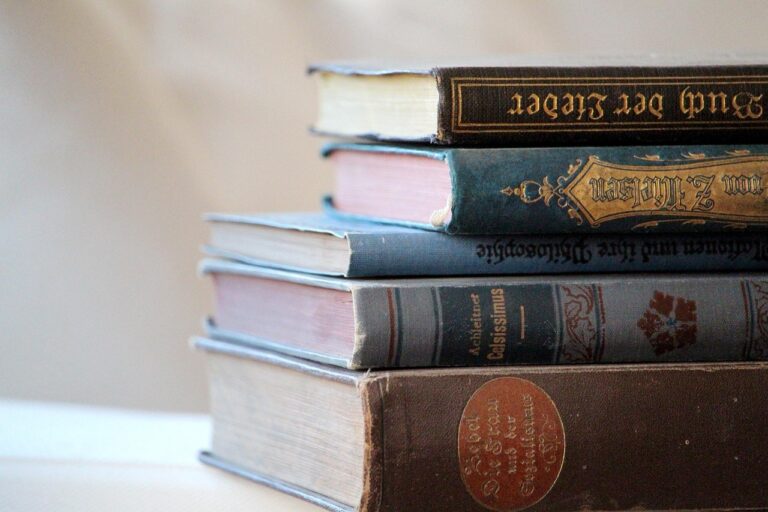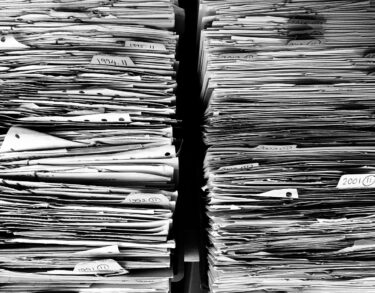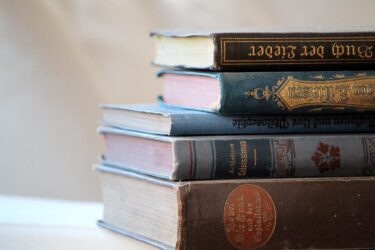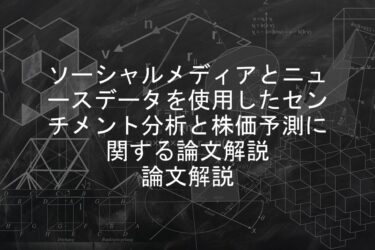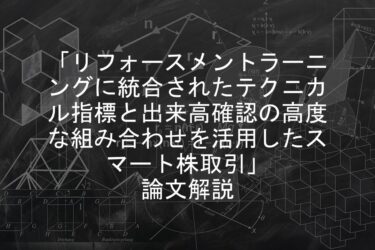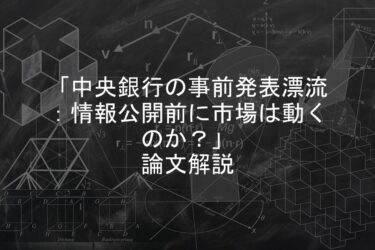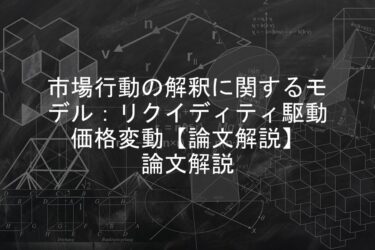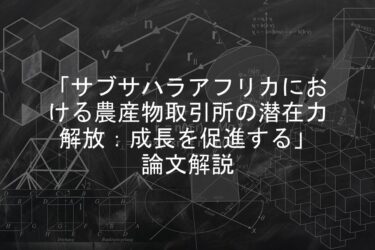論文:Supervision And Enforcement Of Professional Ethics Standards Of Securities Companies And Individuals Practicing Securities: A Case Study Of Vietnam
(ベトナムにおける証券業の職業倫理の監督と遵守体制)
を分かりやすく解説・要約しました。
出典元:SSRN(2025/04/07掲載)
- 1 第1章 導入 ― 「倫理」が市場インフラになるとき
- 2 第2章 監督モデルの多層構造 ― 自律と独立のバランス
- 3 第3章 規制監督とコンプライアンス ― 国家レベルの枠組み
- 4 第4章 企業内部での倫理文化形成 ― コードと教育の役割
- 5 第5章 個人責任と説明責任 ― 専門職の自律と制裁メカニズム
- 6 第6章 国際協調と今後の展望 ― 倫理のグローバル標準化
- 7 用語解説
- 7.6.1 職業倫理(Professional Ethics)
- 7.6.2 SSC(State Securities Commission)/国家証券委員会
- 7.6.3 SRO(Self-Regulatory Organization/自主規制機関)
- 7.6.4 倫理コード(Code of Ethics)
- 7.6.5 コンプライアンス(Compliance)
- 7.6.6 利益相反(Conflict of Interest)
- 7.6.7 説明責任(Accountability)
- 7.6.8 ピア・スーパービジョン(Peer Supervision)
- 7.6.9 RegTech(Regulatory Technology)
- 7.6.10 IOSCO(国際証券監督者機構)
- 7.6.11 Ethical Human Capital(倫理的人的資本)
- 8 総括 ― 「倫理」を制度から文化へ、文化から信頼へ
第1章 導入 ― 「倫理」が市場インフラになるとき
1) 何を問題にしている論文か
この論文が出発点に置くのは、証券会社と証券実務者の専門倫理が「市場の信頼」「投資家保護」「持続的な発展」を支える制度的土台だという事実です。
とりわけベトナム市場を事例に、倫理を規制・自律・教育・テクノロジーでどう担保・執行するかを体系的に整理します。
2) 専門倫理とは何か(論文が置く基本線)
論文は、専門倫理を次の軸で捉えます。
-
公正・誠実・透明性:虚偽表示や誇大広告の禁止、価格形成の公正。
-
顧客本位:利益相反の把握と管理、顧客資産の分別管理、情報の秘密保持。
-
規律と説明責任:社内規程の整備、教育・訓練、違反時の是正・懲戒。
3) なぜ「導入」でこのテーマが重要なのか
導入章で著者は、倫理が不足すると市場の透明性が毀損され、結果的に資本調達コストの上昇や投資家離れにつながる、と整理します。
逆に、倫理を制度化すれば、
-
不正の予防(ルールと教育)
-
早期発見(監視と通報)
-
迅速な是正(懲戒と再発防止)
という三位一体のプロセスが回り、市場の信頼が増す――これが導入部で示される問題意識です。
4) 研究の射程(何を明らかにするか)
導入で示される本論文の主要な論点・問いは以下です。
-
監督モデル:SRO(自主規制)/独立監督/協調監督は、倫理の実効性にどう効くか。
-
規制監督の運用:監督当局(ベトナムの事例)によるモニタリングや制裁を、どう効率化・高度化するか。
-
企業内部統制:倫理コード・研修・通報制度など、社内の“文化”と“手続”をどう設計するか。
-
個人の責任:ブローカーやアナリスト等の専門職に、どのような自律と説明責任を求めるか。
-
投資家保護:リテラシー向上と情報開示で、投資家自身の防衛力をどう高めるか。
-
国際連携と技術:国際機関との協調や、監督のデジタル化(RegTech/ブロックチェーン等)をどう位置づけるか。
5) 方法とスタンス(ベトナムの事例研究として)
本論文は、ベトナムの制度・実務をケーススタディとして俯瞰し、
-
監督機関の役割
-
業界団体の機能
-
企業内コンプライアンスの要素
-
倫理教育/投資家教育
-
技術活用の方向性
を記述的・規範的に整理します。
数量的因果推定や違反件数の統計比較が中心ではなく、枠組み設計の全体像を描くスタイルです。
6) 本論文の位置づけ(導入で示す貢献)
導入部が明示する貢献は、次の三点に集約されます。
-
概念の統合:専門倫理を「規制・自律・内部統制・教育・技術」にまたがる統合フレームで提示。
-
運用への落とし込み:監督と執行をプロセス(予防・発見・是正)として設計し直す視座を提示。
-
国際化とデジタル化:国際協調とRegTech/ブロックチェーン等を倫理の実効性を高める実装手段として位置づけ。
導入の結論はシンプルです。
倫理は努力目標ではなく市場インフラである。
その前提に立てば、監督・社内統制・教育・技術を束ねる設計図が要る――この設計図を、ベトナム事例で具現化して示すのが本論文です。
第2章 監督モデルの多層構造 ― 自律と独立のバランス
1. 倫理監督の必要性 ― 市場の「信頼装置」としての制度
論文の第2章がまず強調するのは、「倫理の実効性は制度設計によって決まる」という点です。
どれほど優れた倫理規定があっても、監督体制が弱ければ遵守は形骸化します。
そのため、証券業界では各国が「監督モデル」を複層的に組み合わせ、内部・外部・協調的にモニタリングを行う構造をとっています。
著者はこの章で、監督構造を3つのモデルに分類し、ベトナムの制度がそれらを組み合わせたハイブリッド型であることを示しています。
2. モデル①:自主規制機関(SRO: Self-Regulatory Organization)モデル
SROモデルは、業界自身が自らを監督・指導する仕組みです。
証券取引所や証券業協会が中心となり、会員企業に対して次のような取り組みを行います。
-
倫理ガイドラインの策定と共有
-
会員行動のモニタリング
-
違反時の注意・勧告・会員資格停止
-
倫理研修や再教育の実施
この仕組みの利点は「現場を知る者が現場を律する」スピード感と柔軟性にあります。
ベトナムの場合、SROは市場参加者に近い立場で早期是正の役割を果たしています。
ただし、論文では同時に次のような課題も指摘されます。
SROは同業者間の監督であるため、業界内の癒着や規律の甘さが生じやすい。
公的監督機関との連携がなければ、抑止力は限定的になる。
3. モデル②:独立監督(Independent Supervision)モデル
独立監督とは、国家レベルの監督機関が直接モニタリング・制裁を行う制度です。
ベトナムでは国家証券委員会(State Securities Commission, SSC)がこの役割を担っています。
SSCの主な権限は以下の通り、
-
証券会社や個人の登録・免許付与
-
倫理・行動規範の監督および違反時の制裁(罰金・営業停止など)
-
定期・臨時の監査実施
-
金融安定性・投資家保護に関する規制発出
SSCは政府機関として独立した権限を持ち、業界から距離を保つことで客観性と強制力を確保しています。
著者はこの体制を「公的正統性(public legitimacy)」の観点から評価しています。
一方で、課題として指摘されるのが、行政手続きの硬直性と現場対応の遅れです。
監督情報が中央に集約されることで、リスク対応のタイムラグが生まれるという構造的問題があります。
4. モデル③:協調監督(Coordinated Supervision)モデル
この章の中心となるのが、SROとSSCを組み合わせた協調型(hybrid)モデルです。
ベトナムはこの方式を採用しており、両者の機能を明確に分担・連携させています。
| 監督レイヤー | 主体 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 自主規制層 | 取引所 | 倫理教育・内部監督・勧告 |
| 公的監督層 | SSC(国家証券委員会) | 法的監督・処分・制度整備 |
| 連携層 | 協議会・ワーキンググループ | 情報共有・違反対応・基準整合 |
この「三層モデル」により、内部の柔軟性+外部の強制力+横断的連携が確保され、倫理遵守を「単発の取締り」ではなく、制度循環(継続的改善)として運用できるようになります。
5. モデル比較の要点(論文の分析結果)
著者はこの3モデルを比較した上で、以下の3点を結論づけています。
-
SRO単独では限界がある
自律的取組は機動的だが、制裁権限が弱い。 -
独立監督単独では硬直的になる
行政機関によるトップダウン型は現場対応が遅れる。 -
協調モデルが最も現実的で実効的
倫理の遵守を「文化・法・制度」の三面から支える枠組みを作れる。
さらに論文は、ベトナムにおけるこの協調モデルが、東南アジア地域での「規範モデル」になりつつあることも指摘しています。
6. 本章の意義 ― 倫理を制度で守るという発想
この章の結論は明確です。
「倫理を守る」のではなく、「倫理が守られる仕組みを作る」ことが重要。
つまり、個人の良心や企業文化に依存せず、監督モデルという構造的安全装置を設計することが、市場全体の信頼を支える。
ベトナムの事例は、倫理を文化から制度へ移行させる転換点として評価されています。
第3章 規制監督とコンプライアンス ― 国家レベルの枠組み
1. 規制監督の中核 ― 国家証券委員会(SSC)の役割
この章で論文は、ベトナムの国家証券委員会(State Securities Commission, SSC)を中心に、
倫理監督とコンプライアンス(法令遵守)をどのように制度的に運用しているかを詳しく分析しています。
SSCはベトナム証券市場の最高監督機関であり、次のような権限を持っています。
-
証券会社および証券業務従事者の登録・免許管理
-
倫理・行動規範に関するガイドラインの策定
-
市場取引・内部統制・財務報告の監査
-
不正行為の調査および行政処分(罰金・免許停止・取消)
-
投資家保護・市場安定化のための規制発出
SSCは、証券市場を単なる「経済活動の場」ではなく、公共的な信頼を維持する制度空間とみなし、倫理規範の監督をその中心任務の一つとして位置づけています。
2. 倫理遵守を支える実務インフラ ― 「監視・報告・是正」の三段階モデル
論文では、SSCが採用する倫理監督体制を三段階のプロセスモデルとして整理しています。
これは倫理を単に罰するのではなく、継続的にモニタリングして改善する構造です。
第1段階:監視(Monitoring)
-
オンラインモニタリングシステムによって、証券会社の取引活動・報告データを常時監視。
-
アルゴリズム分析で異常な価格変動や自己取引を自動検知。
-
内部統制報告や顧客苦情データも統合し、リアルタイムでリスクを可視化。
第2段階:報告(Reporting)
-
各証券会社は四半期・年次で倫理遵守報告書をSSCに提出。
-
内容には「内部監査結果」「教育実施状況」「違反処理実績」などが含まれる。
-
報告データはSSCの中央データベースで比較分析され、異常値を自動抽出。
第3段階:是正(Enforcement)
-
違反行為が確認された場合、SSCは制裁(行政処分)と改善命令を発出。
-
悪質な事案は免許停止・登録取消・刑事移送に至る。
-
軽度の違反は「教育・再研修」措置で再発防止を促す。
この三段階システムにより、倫理監督が「静的な罰則運用」ではなく、
動的なPDCA(Plan–Do–Check–Act)サイクルとして機能する仕組みが整っています。
3. テクノロジーの導入 ― デジタル監督への転換(RegTech)
著者は特に、SSCが進めている「デジタル監督(RegTech)化」の流れを強調しています。
これは、AI・データ解析・自動検知を用いた新しい監督の形です。
主な施策
-
オンラインモニタリングプラットフォーム:証券会社のリアルタイムデータを自動収集。
-
アラート通知システム:異常な取引や内部統制違反を自動検知し、即時通知。
-
電子通報システム(e-Whistleblowing):匿名での内部通報を受け付ける電子窓口。
-
デジタル証拠管理:監査記録・処分履歴をブロックチェーン的に改ざん防止保存。
4. コンプライアンスの文化化 ― 企業側の義務と支援
SSCによる外部監督に加え、論文は「企業内部でのコンプライアンス文化の定着」を重視します。
その背景には、倫理の実効性は法の外部圧力だけでは不十分という認識があります。
SSCは証券会社に対して以下の義務を課しています。
-
倫理・行動規範(Code of Ethics)の制定と公開
-
全社員向けの年次倫理研修の実施
-
内部監査部門による定期的な遵守点検
-
倫理違反の社内通報制度の設置
-
取締役会レベルでのコンプライアンス責任者(CCO)任命
これらを通じて、「外からの規制」ではなく「内からの自律」を促進する狙いがあります。
著者はこれを「エシカル・ガバナンス(Ethical Governance)」と呼び、倫理を企業統治の正式な構成要素として制度化することの重要性を強調しています。
5. 制裁と透明性 ― 信頼を維持するための最後の防壁
論文では、倫理違反への制裁を「抑止」ではなく「信頼回復」の手段として位置づけています。
SSCは制裁を三段階に分類しています。
-
行政警告・罰金(軽度)
-
業務停止・資格停止(中度)
-
免許取消・刑事訴追(重大違反)
特筆すべきは、SSCがすべての制裁情報をオンライン公開している点です。
この「制裁データベース」は、投資家や他の市場参加者が企業倫理の実態を確認できる透明性インフラとして機能しています。
6. 章の結論 ― 「倫理を監督する」から「倫理で監督する」へ
この章の最後で著者は、次のように結論づけています。
「規制監督は倫理を外部から押し付けるものではない。倫理そのものが、監督の正統性と持続性を保証する基盤である。」
つまり、倫理基準は「企業が守るルール」であると同時に、監督機関が自らの行為を正当化する「鏡」にもなる――。
ベトナムのケースは、倫理を制度的に内面化した監督モデルの成功例として示され、
今後の新興国市場にも応用可能な「規範的モデル」として提示されています。
第4章 企業内部での倫理文化形成 ― コードと教育の役割
1. なぜ「内部倫理」が必要なのか
論文の冒頭で著者はこう述べています。
「倫理は外から課される規則ではなく、組織の中で日常的に実践される習慣である。」
つまり、国家や監督機関(SSC)がどれほど厳格な規制を整備しても、企業の内部に倫理意識が根づかなければ、実効性は限定的です。
この章は、企業レベルで倫理を「文化として根づかせるプロセス」を、制度設計・教育・評価・コミュニケーションの4軸で詳しく分析しています。
2. 「倫理コード(Code of Ethics)」の位置づけと目的
● 倫理コードとは
ベトナムでは、すべての証券会社に倫理および行動規範(Code of Professional Ethics and Conduct)の策定が義務づけられています。
これは単なる社内マニュアルではなく、会社の価値観・判断基準を明文化した指針です。
主な目的は次の3点です。
-
行動の一貫性を保ち、組織の信頼を維持する
-
利益相反・内部取引・顧客不利益行為を未然に防ぐ
-
倫理違反が発生した際の責任範囲を明確化する
● コードの具体的な構成要素
著者は典型的なベトナム証券会社の倫理コードを分析し、以下の要素が共通していると述べています。
-
誠実性(Integrity):虚偽表示・不正取引の禁止
-
公平性(Fairness):顧客間の優先順位・情報の非差別管理
-
透明性(Transparency):報告・説明責任の徹底
-
守秘義務(Confidentiality):顧客情報の漏洩防止
-
職業責任(Professional Responsibility):専門性維持と継続的学習
-
社会的責任(Social Responsibility):市場全体の健全性への配慮
つまり、倫理コードは「禁止事項の集まり」ではなく、どう行動すべきかを定義した職業人の行動哲学なのです。
3. 社内教育と啓発 ― 「知識」から「習慣」へ
論文が特に強調するのは、倫理教育を一度きりの研修に終わらせないこと。
SSCのガイドラインに従い、企業は以下のような教育体系を整備しています。
● 教育の3層構造
-
新入社員研修(入門)
証券取引の基礎倫理・顧客対応・情報管理のルールを学ぶ。 -
定期研修(更新)
年1回以上、法改正や最新事例を踏まえた再教育を実施。 -
専門職向け教育(深化)
アナリスト、ブローカー、ファンドマネージャーなどの専門職が、
利益相反管理・内部統制・報告義務を中心にケーススタディを行う。
● 教育の特徴
-
ケースベース学習(事例研究)を重視
実際に起こった違反事例を分析し、「どこで判断を誤ったか」を討議。 -
対話型研修
上司・部下・監査担当者がディスカッション形式でリスク意識を共有。 -
Eラーニング導入
SSCのオンライン教育ポータルと連携し、進捗を中央管理。
このように教育は「ルールを覚える」段階から「倫理的判断を習慣化する」段階へ進化しています。
著者はこれを「institutional moralization(倫理の制度化)」と呼んでいます。
4. コミュニケーションと透明性 ― 倫理を見える化する
倫理を形骸化させないためには、日常的な情報共有と対話が不可欠です。
論文は、企業内でのコミュニケーション構造を次のように整理しています。
-
内部告発制度(Whistleblower System)の整備
匿名での倫理違反報告を可能にし、報復から通報者を保護。 -
倫理委員会の設置
取締役会直轄の委員会が苦情・違反報告を審査し、改善勧告を発出。 -
年次倫理報告書の公表
企業が倫理教育実施状況・違反件数・是正措置を毎年公開。
この透明性の確保が、社員の意識向上と同時に、投資家への信頼形成につながるとしています。
5. 倫理文化の定着 ― トップマネジメントの責任
著者は、「倫理文化の成否は経営層の姿勢にかかっている」と明言します。
倫理はCompliance Departmentの仕事ではなく、トップマネジメントの経営課題です。
経営陣に求められる行動として次が挙げられています。
-
企業理念と倫理方針を明確にし、全社員に繰り返し伝える
-
自ら率先して倫理行動を実践(tone from the top)
-
不正を見逃さない「ゼロ・トレランス」文化を示す
-
倫理を評価制度・報酬制度に組み込む
倫理文化とは、上から命令されるものではなく、上から体現されるもの。
この姿勢が社内の信頼を支え、外部からの評価にも直結すると結論づけています。
6. この章のまとめ ― 倫理を文書から文化へ
第4章のまとめとして、著者は次のように記しています。
「倫理とは、企業の外にある監督対象ではなく、企業そのものの存在理由(raison d’être)である。」
つまり、
-
倫理コードは「紙のルール」ではなく、「企業の人格」
-
教育は「一時的イベント」ではなく、「文化の浸透手段」
-
経営者は「統制者」ではなく、「倫理文化の体現者」
この三つが揃って初めて、倫理は企業のDNAとして根づく――
これが本章の最も重要なメッセージです。
第5章 個人責任と説明責任 ― 専門職の自律と制裁メカニズム
1. 専門職倫理の本質 ― 「自由」と「責任」の両立
本章の冒頭で著者は次のように述べています。
「証券市場の倫理は、制度によって守られるだけでなく、各専門家が自ら律する力を持つことで初めて完成する。」
つまり、制度による外部統制(監督・罰則)と、専門職による内面的な倫理自覚(moral autonomy)が両輪となるべき、という立場です。
証券会社の社員、とりわけ証券ブローカー・アナリスト・ファンドマネージャーのような専門職は、
市場への影響力が大きく、1つの不正行為が即座に市場の信頼失墜につながるリスクを持っています。
そのため、著者は「職業上の自由」と「倫理的拘束」をセットで捉え、専門職倫理の自律的遵守構造を提示しています。
2. 専門職の倫理責任 ― 職能ごとの行動基準
論文では、ベトナム証券市場における主要な職種を3分類し、それぞれの倫理的義務を次のように整理しています。
(1) 証券ブローカー(Broker)
-
顧客の利益を最優先に行動する「fiduciary duty(受託者責任)」を負う
-
顧客の注文を恣意的に操作したり、先回り取引(front running)を行ってはならない
-
投資勧誘時には「虚偽・誇張・誤解を招く表現」を使用してはならない
(2) 証券アナリスト(Analyst)
-
企業調査・レポート作成において独立性と客観性を維持する
-
自身や所属企業の保有ポジションが調査結果に影響しないよう管理する
-
レポートの推奨意見と、実際の売買行動の整合性を確保する
● (3) ファンドマネージャー・投資顧問(Portfolio Manager / Advisor)
-
投資判断に際し、適合性(Suitability)を確認する義務
-
顧客のリスク許容度・投資目的を尊重したポートフォリオ設計を行う
-
自己勘定と顧客資金の明確な分離(Chinese Wall)を維持する
3. 制裁メカニズム ― 倫理違反への対応プロセス
ベトナムの証券市場では、個人の倫理違反に対しても明確な懲戒・制裁プロセスが制度化されています。
論文ではこれを「4段階制裁モデル」として整理しています。
第1段階:発覚・通報
違反行為が内部監査、顧客苦情、またはSSC(国家証券委員会)の監視によって発覚。
内部通報制度(whistleblower system)経由の報告も増加傾向。
第2段階:調査・確認
倫理委員会または社内監査部門が事実確認を行い、
必要に応じてSSCへ報告・調整を行う。
調査は独立性の高い第三者チームが担当することが望ましいとされています。
第3段階:処分・教育
違反の性質に応じて、以下の制裁が段階的に適用される。
-
軽度:警告・再研修の命令
-
中度:資格停止・一定期間の業務制限
-
重度:資格剥奪・刑事訴追・業界登録抹消
処分と同時に、「倫理再教育プログラム」への参加を義務化することで、
再発防止と意識改革を両立させる構造が整えられています。
第4段階:公開・透明化
制裁情報はSSCの公式ポータルに掲載され、一般投資家にも閲覧可能。
これにより、「透明性の高い懲戒」が市場全体の信頼維持に寄与しています。
4. 自律的遵守を促す「ピア監督」メカニズム
著者が特に注目するのは、「ピア・スーパービジョン(peer supervision)」という概念です。
これは、業界団体や専門協会が、
会員同士で倫理を監督・指導し合う仕組みです。
具体的には、
-
各専門職ごとの倫理委員会が、行動基準や判断事例を共有
-
定期的な倫理ワークショップを開催し、会員が相互に改善点を議論
-
再発リスクのある会員企業に対して「倫理指導プログラム」を勧告
この「横のつながりによる監督」は、
外部からの規制だけでは届かない現場レベルの意識改革を促します。
5. 投資家との関係 ― 「説明責任(Accountability)」の実践
個人の倫理は、投資家とのコミュニケーションの質にも直結します。
論文では、説明責任を果たすための3原則を挙げています。
-
情報の完全開示(Full Disclosure)
投資判断に影響を与えるすべての情報を、正確かつタイムリーに開示。 -
誤解の防止(Clarity)
専門用語を多用せず、顧客の理解度に合わせた説明を行う。 -
追跡可能性(Traceability)
顧客との取引履歴・助言内容を文書化し、後日検証できる状態を保つ。
これにより、投資家が不利益を被った場合でも「どの段階で・誰が・どの判断をしたか」を明確にできる。
倫理の最終的な目的は「透明な信頼関係の維持」である、と著者は強調します。
6. この章のまとめ
第5章の締めくくりで、著者は次のように述べています。
つまり、
-
制裁は罰ではなく信頼を取り戻すプロセス
-
自律は個人の自由ではなく職業的責任の表れ
-
倫理の最終形は「監督されなくても正しく行動する状態」
という、内面化された倫理の重要性を説いています。
この章で描かれるのは、単なる規制の遵守ではなく、「倫理をプロフェッションの本質として体現する」段階への到達です。
第6章 国際協調と今後の展望 ― 倫理のグローバル標準化
1. 倫理の国際化 ― ベトナム市場が直面する課題
著者はまず、ベトナムの証券市場が急速な国際化の中で直面している現実を指摘します。
市場が拡大し、外国投資家の参入が進むにつれ、国内だけで完結する倫理基準では国際的な信頼水準を維持できないという課題が浮かび上がっているのです。
とくに、外国証券会社やファンドがベトナム市場で活動する際、それぞれの国際的な倫理基準(例:IOSCO、OECD、IFAC)との整合性が問われる場面が増えています。
著者はこの状況を「ローカル・エシックスからグローバル・エシックスへの転換期」と呼び、ベトナム市場が持続的に発展するためには、
国際的な監督協力と共通倫理基準の採用が不可欠だと強調しています。
2. 国際機関との連携 ― IOSCOと地域間協調の枠組み
論文は、ベトナム国家証券委員会(SSC)が国際的に採用している「IOSCO(国際証券監督者機構)」の枠組みを中心に解説しています。
IOSCOの基本原則
IOSCOは、証券市場の監督当局が加盟する国際組織であり、
加盟国が共通して遵守すべき倫理・透明性・監督・執行の原則を定めています。
SSCはこの原則に基づき、
-
市場監督と制裁の相互協力体制を強化
-
不公正取引の国際的情報共有を推進
-
倫理教育プログラムの国際連携(トレーニング交流)を実施
著者は、これらの取り組みがベトナムの倫理監督を「ローカル実務」から「国際基準」へと押し上げる基礎になっていると述べています。
3. 国際的な倫理基準の参照モデル
論文では、ベトナム市場が今後参照すべき代表的な国際倫理モデルとして、
次の3つを紹介しています。
-
OECD(経済協力開発機構)企業統治原則
→ コーポレート・ガバナンスと倫理的経営の整合性を重視。 -
IFAC(国際会計士連盟)職業倫理規範
→ 監査・会計分野での誠実性・客観性・専門能力を強調。 -
CFA Institute Code of Ethics
→ 金融専門職としての独立性・忠誠・誠実性・公正性を基礎原則とする。
SSCはこれらを参考に、ベトナム独自の証券倫理基準を国際互換性のある形で再設計する方向性を提示しています。
著者は、「倫理を国際言語化すること」が今後の競争力の鍵であると指摘しています。
4. テクノロジーと倫理監督 ― RegTechとBlockchainの導入
近年、倫理監督の分野でもRegTech(Regulatory Technology)やブロックチェーンの応用が進んでおり、
論文でもその先進事例とベトナムへの応用可能性が議論されています。
RegTechによる監視効率の向上
-
AIを活用して取引パターンをリアルタイムで監視
-
データ異常を自動検知し、即時通報
-
違反検出率と監督コストの両面で大幅な改善が可能
ブロックチェーンによる透明性の強化
-
証券取引・報告・監査データをブロックチェーン上に記録し、改ざん不可能な監査証跡を確立。
-
投資家が企業の倫理履歴を直接確認できるトレーサブル市場の実現へ。
著者は、このようなテクノロジー主導の倫理監督(Tech-driven Ethics Supervision)が今後の国際標準になると述べています。
5. 倫理教育の国際展開 ― 専門人材の育成
倫理は制度だけでなく「人材」によって運用される。
そのため、教育の国際連携も重要なテーマとして論じられています。
SSCは現在、次のような取り組みを進めています。
-
海外監督当局(シンガポール、韓国、マレーシアなど)との研修交換
-
大学・研究機関と連携した倫理カリキュラムの導入
-
国際資格(CFA、FRM、CPA)保有者の倫理教育の義務化
これにより、
倫理を理論として学ぶだけでなく、実践的判断として習得できるプロフェッショナルの育成を目指しています。
著者は、これを「Ethical Human Capital(倫理的人的資本)」と呼び、持続可能な市場形成の核心要素だと位置づけています。
6. 結論 ― 倫理の制度化から文化化へ
最終節で著者は、こう結論づけています。
「倫理の遵守は法的義務ではなく、国際社会の信頼を得るための共通言語である。」
つまり、ベトナムの事例は単なる国内制度改革ではなく、グローバル市場における信頼構築のプロセスなのです。
-
国家:規制の国際整合性を確保し、透明な市場基盤を維持
-
企業:内部統制と倫理文化を融合させ、倫理的経営を推進
-
個人:職業倫理を自律的に体現し、社会的信頼を築く
この三層構造の連携があって初めて、「倫理に基づく市場競争」という新しい段階に進むことができます。
著者は最後に次のように締めくくっています。
「倫理とは、市場を制御するための枠ではなく、市場を進化させるための核である。」
用語解説
職業倫理(Professional Ethics)
― 金融・証券業界における誠実性、公正性、透明性、責任感などの行動基準。
企業の利益や顧客の利益が衝突する状況でも、正しい判断を行うための道しるべとなる。
SSC(State Securities Commission)/国家証券委員会
― ベトナムの証券市場を監督する国家機関。証券会社や個人トレーダーの登録・監督、違反の処分などを担う。
倫理基準の策定や教育の推進にも関与している。
SRO(Self-Regulatory Organization/自主規制機関)
― 証券取引所や業界団体など、業界自身が倫理と行動規範を定めて運営する仕組み。
国家監督を補完する「自律的な内部監視機構」として機能する。
倫理コード(Code of Ethics)
― 証券会社などが定める倫理的行動規範の文書。
誠実性・透明性・顧客保護などを定義し、社員行動の判断軸を明文化する。
コンプライアンス(Compliance)
― 法令や規制だけでなく、倫理や社会的規範を遵守する文化を意味する。
「法に触れなければよい」という最低基準ではなく、「信頼される行動」を基準にする考え方。
利益相反(Conflict of Interest)
― 顧客の利益と自社(または個人)の利益が対立する状態。
倫理コードでは、これを未然に防ぐための明確なルールと報告義務が定められている。
説明責任(Accountability)
― 投資家や上位機関に対して、判断理由や行動の正当性を明確に示す責任。
「正しいことをした」だけでなく、「なぜそれをしたか」を説明できることが倫理の要。
ピア・スーパービジョン(Peer Supervision)
― 同業者・業界団体による相互監督のこと。
同じ職種同士が“倫理上の視点で支え合う”文化であり、規制よりも柔らかく、文化的に根づく監督手法。
RegTech(Regulatory Technology)
― AIやデータ分析技術を使って、規制・監督・リスク管理を効率化する仕組み。
倫理監督では、不正検知や異常行動モニタリングに利用される。
IOSCO(国際証券監督者機構)
― 世界の証券監督機関が加盟する国際組織。
倫理・透明性・市場監督の国際原則を定め、加盟国が調和的に市場を監視できるよう指針を提供している。
Ethical Human Capital(倫理的人的資本)
― 倫理的判断力と専門性を兼ね備えた人材。
単に資格を持つ専門職ではなく、「倫理を文化として体現できる職業人」を意味する。
総括 ― 「倫理」を制度から文化へ、文化から信頼へ
この論文が明らかにした核心は、「倫理は法で命じられるものではなく、信頼を生み出す市場インフラである」という点にあります。
1. 制度としての倫理
ベトナムは発展途上市場でありながら、SSC主導で倫理規範・監督体制・制裁メカニズムを体系的に整備。
これにより、形式的な規制遵守(compliance)を超えた、行動基準としての倫理制度化を進めてきました。
2. 組織文化としての倫理
企業レベルでは、「倫理コード」と「倫理教育」が根幹を成します。
定期的な研修・内部告発制度・経営層の倫理リーダーシップ(tone from the top)を通じ、倫理を日常の意思決定文化へと転換する努力が見られます。
3. 個人責任としての倫理
個々の専門職は、自身の行動が市場全体に信頼を与えることを自覚し、違反防止・説明責任・誠実な顧客対応を徹底する。
制裁制度も“懲罰”ではなく、再教育と信頼回復のプロセスとして設計されている点が特徴的です。
4. 国際化への展開
SSCはIOSCO・OECD・CFA Instituteなどの国際倫理基準と整合性を取りながら、グローバル標準と国内事情を調和させた倫理枠組みを模索。
さらにRegTech・ブロックチェーンなどの技術を監督システムに統合し、「透明で改ざん不能な倫理監督」の未来像を提示しました。
5. 結論:信頼こそ最大の資本
最終的に、著者は次のように締めくくります。
「倫理は市場の枠組みを保つための制限ではなく、市場の成長と信頼を支える土台である。」
誠実さ・透明性・説明責任を組織文化として内面化した企業ほど、長期的には投資家の信頼を獲得し、市場での持続的な成功を収める。
この論文は、ベトナムという新興国のケースを通じて、「倫理の制度化 → 文化化 → 国際標準化」という進化プロセスを提示し、
金融倫理の次の段階を示した重要な実証的研究といえます。
関連する論文解説をもっと読みたい方は、[投資家のための最新研究論文まとめ] をチェックしてみてください。
本記事では、最新のファイナンス研究(SSRNなどの学術論文)を「個人投資家が実務で使える形」で要約・解説しています。ミクロ構造・流動性・市場心理など、価格変動の本質に迫る研究を厳選。 金融・経済論文まとめ:投資家のための最新研究【論文[…]