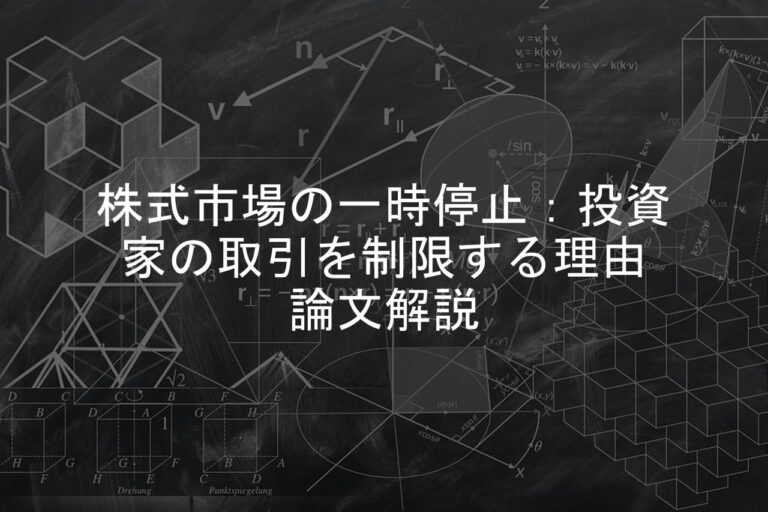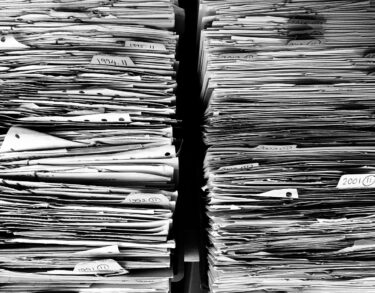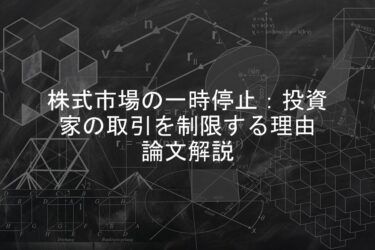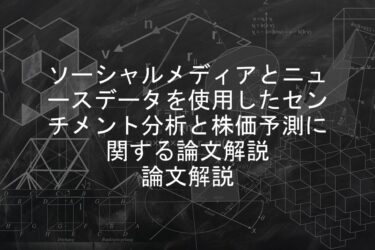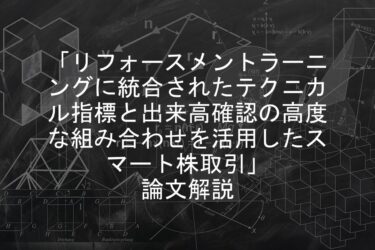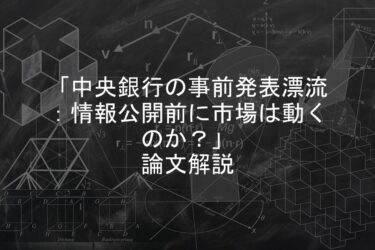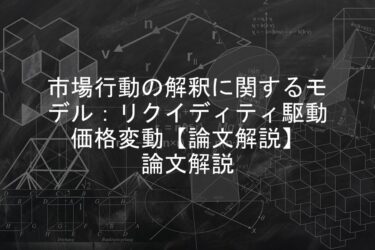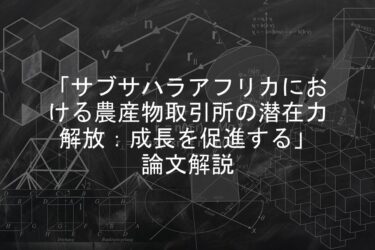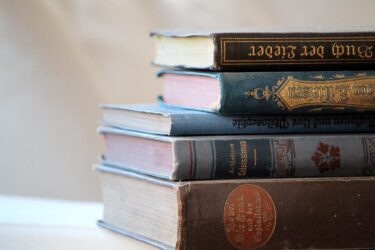論文:Closing the Stock Market: Why Keep Investors from Trading?
(株式市場を閉じる理由:なぜ投資家の取引を止めるのか?)
を分かりやすく解説・要約しました。
出典元:SSRN(2024/11/7掲載)
【論文解説】株式市場はなぜ閉鎖されるのか? ― 戦争・危機・パニックと取引停止の歴史的背景
1. はじめに ― 市場を止めるという異例の判断
株式市場は「常に開いているべき」と思われがちですが、歴史的には戦争や革命、金融危機の際に取引所そのものが閉鎖された事例が存在します。
本稿で取り上げる論文は、株式市場閉鎖の理由とその影響について、過去の事例を基に解説しています。
市場を止める判断は、投資家の自由を制限する一方で、パニック売りによる暴落を防ぐセーフティーネットという側面も持っています。
では、どのような状況で市場が閉ざされてきたのでしょうか?
2. 第一次世界大戦中の閉鎖 ― グローバル市場の分断と長期的影響
1. 戦争勃発と取引所閉鎖の連鎖
1914年7月、第一次世界大戦が勃発すると、欧州主要都市(ロンドン、パリ、ベルリンなど)の株式取引所は一斉に閉鎖されました。
投資家が保有資産を一斉に売却しようとしたことで、株価の暴落が現実味を帯び、各国政府・取引所は市場の混乱を防ぐために「取引停止」という極端な措置を取ったのです。
2. 下限価格の導入
取引が再開された後も、「株価が一定以上下がらないように下限を設定」する措置が導入されました。
これは、投資家のパニック売りを抑制するための苦肉の策であり、自由な価格形成という資本市場の基本原則を制限するものでした。
3. 戦後に残された深い爪痕
戦争が終結すると、各国の金融市場は再建を迫られましたが、閉鎖の影響は長期的に残りました。
-
国際資本取引の縮小:戦前はロンドンを中心に国際資本が自由に流れていましたが、戦争と閉鎖によって国境を越える投資は大幅に縮小。
-
所有権の制限:戦時中に「敵国資産」の没収や制限が行われ、多くの外国人投資家が株式・債券の所有権を失いました。
-
市場の停滞:国際的な株式・債券市場の活力は失われ、戦後も数十年にわたって縮小基調が続きました。
3. 第二次世界大戦中の閉鎖 ― 戦争と体制転換が市場を止めた
第二次世界大戦は、世界の株式市場に深刻な影響を及ぼしました。
第一次大戦と同様に、戦時の不確実性と資本流出を防ぐため、取引所の閉鎖が広範囲で実施されましたが、その後の影響はより大きく、政治体制や経済システムそのものを揺るがすものでした。
1. ナチス占領下での取引停止
ナチス・ドイツが侵攻した欧州各国では、金融インフラの多くが停止しました。
証券取引所も例外ではなく、占領地の市場は閉鎖され、投資家の資産は事実上凍結されました。特にフランスやオランダなどでは、市場機能が完全に麻痺し、戦時経済の枠組みに取り込まれていきました。
2. 戦後の共産主義体制による市場消滅
戦後、東欧諸国では共産主義体制が確立され、資本主義的な市場メカニズムは排除されました。
証券取引所は廃止され、株式や債券といった資本市場そのものが存在意義を失いました。
ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアなどでは、国有化政策の一環として企業の所有権が国家に移転。
株式市場の再開は冷戦後の1990年代まで待たねばなりませんでした。
3. 西側諸国の例外
一方で、アメリカやイギリスといった西側諸国では、戦争中も取引所は完全閉鎖には至りませんでした。
短期的な取引制限や規制は導入されたものの、市場機能そのものは維持され、戦後の資本主義経済の基盤を守ることに成功しました。
こうしてみると、第二次世界大戦期の市場閉鎖は「国によって意味が異なる」ことが浮かび上がります。
-
占領国では「外部から強制された閉鎖」
-
共産国では「体制転換による市場の消滅」
-
西側諸国では「部分的制限で市場機能を維持」
この違いは、その後の金融システムの再建や資本市場の発展に大きな分岐をもたらしました。
4. 現代市場と閉鎖の可能性 ― 「完全停止」から「一時制御」へ
1. 技術進展による変化
21世紀の金融市場は、電子取引・自動化・グローバルな接続性によって、第一次・第二次世界大戦時のような 数か月規模の全面閉鎖 はほぼ想定されません。
市場が止まれば、その国の信用や資本流入が一気に途絶えるため、現代では「長期閉鎖=自国経済の自滅」となりやすいからです。
2. サーキットブレーカー制度の導入
代わりに広く普及しているのが サーキットブレーカー制度 です。
-
市場指数が一定割合下落すると、売買を一時停止
-
数分から数十分間の「冷却期間」を設けることで、投資家のパニック売りを抑制
-
米国ではS&P500の下落率に応じて、7%、13%、20%の3段階が設定されている(2020年3月のコロナショックでは複数回発動)
3. 依然として残る「想定外リスク」
とはいえ、地政学リスクや金融システム障害が発生した場合、部分的な制限以上の措置が取られる可能性は否定できません。
-
サイバー攻撃で市場インフラが機能不全に陥る
-
地政学的リスク(戦争・制裁)による一時的な資本規制
-
極端な金融危機で、外国人投資家の資金流出を止めるための売買制限
5. 投資家にとっての実務的示唆
-
過去の教訓:市場は「常に開いている」とは限らない。第一次世界大戦の閉鎖は数か月に及び、流動性を失った投資家が多数存在した。
-
現代への応用:市場閉鎖はレアケースだが、部分的停止(サーキットブレーカー)は日常的なリスク管理策として発動し得る。
-
投資戦略への影響:緊急時には「売りたいときに売れない」状況もあり得る。特に長期投資家は、このリスクを無視せず、流動性確保(現金・安全資産の割合)を戦略に組み込む必要がある。
予期せぬ制限が起きる前提で、資産配分やリスク管理を組み立てることが、実務的な教訓といえるでしょう。
6. まとめ ― 市場は「常に開いている」とは限らない
株式市場は、戦争・革命・金融危機といった非常事態において実際に閉鎖された歴史があります。
第一次・第二次世界大戦では取引所が数か月規模で停止され、戦後の金融システムに長期的な影響を与えました。
現代では、テクノロジーとグローバル化により長期閉鎖のリスクは大幅に低下しています。
しかしその代わりに、サーキットブレーカー制度 のような「部分的な停止」が制度化され、短期的なパニックを抑える仕組みが稼働しています。
投資家にとっての実務的教訓は以下の通りです:
-
「市場は常に開いている」という前提は危うい
-
サーキットブレーカーは日常的に発動し得るリスク
-
有事には売りたいときに売れない可能性もある
したがって、長期投資家であっても 流動性リスク(市場が止まるリスク) を意識し、キャッシュポジションや安全資産を確保することが重要です。
この研究は、投資家に「市場の継続性を当然視しない」視点を与え、予期せぬ制限に備えた資産戦略の必要性を教えてくれます。
関連する論文解説をもっと読みたい方は、[投資家のための最新研究論文まとめ] をチェックしてみてください。
本記事では、最新のファイナンス研究(SSRNなどの学術論文)を「個人投資家が実務で使える形」で要約・解説しています。ミクロ構造・流動性・市場心理など、価格変動の本質に迫る研究を厳選。 金融・経済論文まとめ:投資家のための最新研究【論文[…]