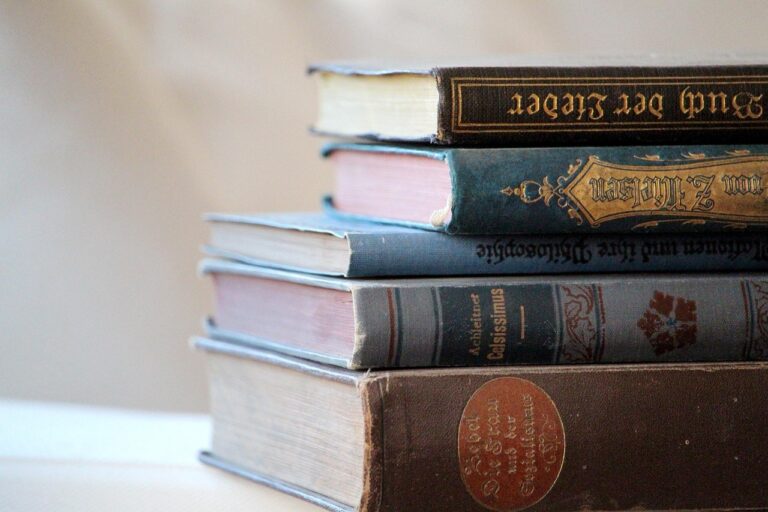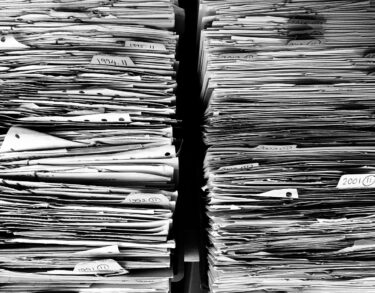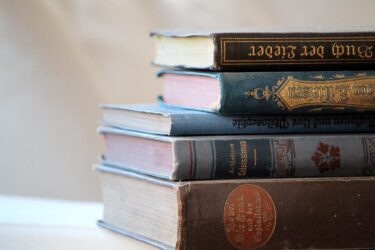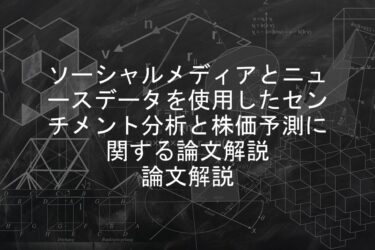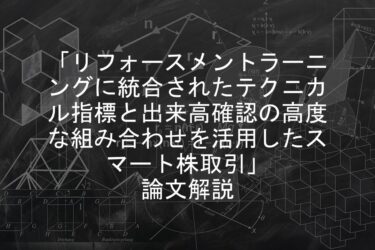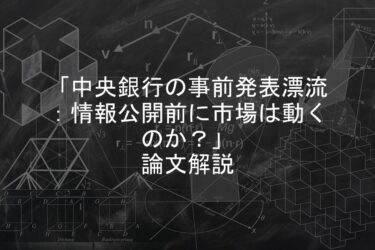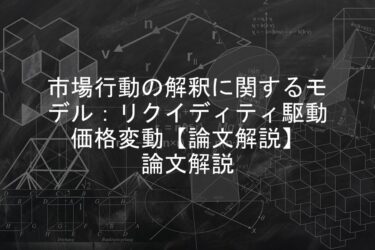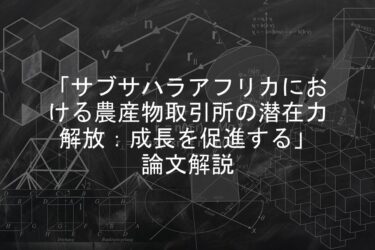論文:Mean Field Equilibrium Asset Pricing Model Under Partial Observation: An Exponential Quadratic Gaussian Approach
(不完全情報下の平均場型資産価格モデル ― 指数二次ガウス過程による解析)
を分かりやすく解説・要約しました。
出典元:SSRN(2025/11/18掲載)
- 1 1. 導入 ― 「部分観測」と「平均場理論」が交わる資産価格モデル
- 2 2. モデル概要 ― 平均場均衡と部分観測の融合
- 3 3. 部分観測下の最適戦略 ― フィルタリングと動学最適化
- 4 4. 均衡価格の導出と動学特性 ― 情報不完全性が市場価格に与える影響
- 5 5. モデル拡張と今後の研究方向 ― ジャンプ・非線形フィルタ・実証へ
- 6 用語解説
- 6.9.0.1 平均場均衡(Mean Field Equilibrium)
- 6.9.0.2 部分観測(Partial Observation)
- 6.9.0.3 指数二次ガウス(Exponential Quadratic Gaussian)モデル
- 6.9.0.4 ブラウニアン運動(Brownian Motion)
- 6.9.0.5 リスクプレミアム(Risk Premium)
- 6.9.0.6 ノンリニア・フィルタリング(Nonlinear Filtering)
- 6.9.0.7 市場クリアリング条件(Market Clearing Condition)
- 6.9.0.8 ジャンププロセス(Jump Process)
- 7 総括 ― 「不完全情報下の均衡」が意味するもの
1. 導入 ― 「部分観測」と「平均場理論」が交わる資産価格モデル
資産価格理論では、一般に投資家はすべての情報を完全に把握している(完全情報仮定)という前提のもとで、リスクとリターンの均衡関係が導かれます。
しかし、現実の金融市場では、投資家が把握できる情報はごく一部にすぎません。
たとえば、将来のリスクプレミアム(risk premium)や期待収益率は直接観測できず、投資家は過去の株価やボラティリティなど「限られたシグナル」からそれを推定して行動します。
このような状況を部分観測(partial observation)と呼びます。
1.1 平均場理論(Mean Field Theory)の登場
さらに現代の金融市場では、無数の投資家が同時に行動するため、各投資家の判断は他の参加者の平均的行動(集団のトレンド)に影響されます。
このような「多数のエージェントの相互作用」を記述するために用いられるのが、平均場理論(Mean Field Theory)です。
平均場均衡モデル(Mean Field Equilibrium Model)では、
-
個々の投資家の最適行動(ミクロ行動)と、
-
市場全体の価格形成(マクロ均衡)
を同時に整合的に決定します。
1.2 本研究の焦点 ― 部分観測下の均衡形成
本論文が挑戦するのは、「投資家がリスクプレミアムを直接観測できない状況で、どのように市場均衡が成立するか」という問題です。
具体的には以下のような設定が考えられます。
-
投資家は株価
のみを観測し、
背後にあるリスクプレミアムを確率的に推定(フィルタリング)する。
-
各投資家は自らの推定結果に基づき最適投資比率を決定。
-
すべての投資家の総需要が市場で釣り合うことで、均衡価格とリスクプレミアムが内生的に決まる。
このような「観測不完全 × 多数エージェント × 内生的リスク構造」という三重の複雑性を持つモデルは、従来の完全情報下モデルでは扱えなかったリアルな市場の不確実性構造を再現します。
1.3 Exponential Quadratic Gaussian(指数二次ガウス)アプローチの意義
この研究で採用されるExponential Quadratic Gaussian(EQG)アプローチは、部分観測問題を解析的に扱うための数理的手法です。
EQG構造を用いることで、投資家の効用関数(リスク回避度を表す指数型効用)とリスクプレミアムの確率過程が整合的に表現でき、
さらに線形ガウス型のフィルタリング理論(例:カルマンフィルタ)を適用する余地を残します。
このアプローチの強みは、確率制御理論・最適化・均衡条件を統一的に扱える点にあります。
結果として、部分観測下でも閉形式での解構造(解析的な均衡式)を導出できることが本論文の大きな貢献です。
1.4 研究の目的と意義
本研究の目的は、
にあります。
この枠組みは、単なる理論的抽象にとどまらず、以下のような応用的示唆を持ちます。
-
情報の非対称性が資産価格やボラティリティ構造に与える影響の定量化
-
市場心理(平均行動)がリスクプレミアムをどう内生化するかの分析
-
最適制御理論 × ファイナンスの統合モデルとしての応用(ポートフォリオ選択・リスク管理)
まとめ
投資家がすべての情報を知っているとは限らない。
不確実性の中で、彼らがどう推測し、どう動き、どんな価格を作るか――
本論文は、そのダイナミクスを「平均場理論 × 部分観測 × EQG構造」という新しい数理フレームで解明しようとしています。
2. モデル概要 ― 平均場均衡と部分観測の融合
本章では、論文の核となる「部分観測下の平均場均衡モデル(Mean Field Equilibrium under Partial Observation)」の構造を整理します。
このモデルは、多エージェントの相互作用と観測情報の制約を同時に扱う拡張型の資産価格理論です。
2.1 モデルの基本設定
市場には、無数の投資家(エージェント)が存在します。
各投資家
は、次のような2種類の資産に投資できます。
-
リスク資産(株式):価格
が確率的に変動
-
無リスク資産(債券):一定利率
で成長
ただし、重要なのは以下の点です。
各投資家は、株価
は観測できるが、背後のリスクプレミアム(μ_t)は直接観測できない。
つまり、投資家は「観測ノイズを含む不完全情報下」で最適行動を決定する必要があります。
このとき、株価のダイナミクスは一般に次の確率微分方程式で表されます。
:リスクプレミアム(非観測状態変数)
-
:ボラティリティ(既知の定数)
-
:標準ブラウニアン運動
2.2 部分観測と情報構造
投資家が直接観測できるのは、株価パス
のみ。
よって、非観測の
については「条件付き期待値」に基づいて推定する必要があります。
各投資家が保有する情報は、観測可能な過去の価格系列により生成されるフィルトレーション
この情報制約下で投資家は、リスクプレミアムの推定値
を用いて最適化を行います。
この「フィルタリング」構造が、部分観測モデルの中心的要素です。
2.3 投資家の目的関数と効用最大化
各投資家は、指数型効用関数(exponential utility)を持ちます。
ここで
はリスク回避度を表します。
投資家は、次の最適制御問題を解きます。
与えられた初期資産
のもとで、最終時点
における期待効用
を最大化するようにポートフォリオ比率
(株式への投資比率)を決定する。
ただし、資産の進化は
の形で与えられます。
ここで投資家は観測できない
の代わりに、推定値
を使って意思決定します。
2.4 平均場(Mean Field)相互作用
投資家は多数存在するため、各個人の行動は他者の平均的な行動に依存します。
この「他者の平均的ポジション」を平均場(mean field)として表します。
たとえば、全投資家の平均的投資比率を
とすれば、
リスクプレミアムは市場均衡条件によって内生的に決まります。
すなわち、投資家が推測するリスクプレミアムは、
「他の投資家がどれくらいリスク資産を保有しているか」
によって動的に変化するという構造です。
この設定により、
2.5 EQG(Exponential Quadratic Gaussian)アプローチによる解法
部分観測と平均場相互作用を同時に扱うと、最適制御問題は通常の解析では解けません。
そこで本研究では、指数二次ガウス(EQG)アプローチを用いて閉形式の均衡を導出します。
EQGアプローチのポイントは次の通り。
-
効用関数が指数型 → 対数線形化が可能
-
状態変数がガウス過程 → フィルタリング(カルマン型推定)が適用可能
-
最適投資比率
と推定リスクプレミアム
が解析的に結びつく
結果として、部分観測下でも明示的な均衡式が得られます。
投資家の行動と市場均衡を同時に記述することができるのが、このモデルの革新点です。
2.6 本モデルの位置づけ
このモデルは、以下の3つの研究分野を架橋します。
| 領域 | 対応する理論 | 本研究での位置づけ |
|---|---|---|
| 情報構造 | 部分観測理論(Filtering Theory) | 観測ノイズ下でのリスクプレミアム推定 |
| 集団行動 | 平均場ゲーム(Mean Field Game) | 多数投資家の相互作用をモデル化 |
| 最適化 | 確率制御理論(Stochastic Control) | 効用最大化問題としての行動決定 |
この三層統合により、現実的な不完全情報市場を理論的に再現する資産価格モデルが完成します。
第2章まとめ
本モデルは、投資家がリスクプレミアムを直接観測できないという「現実的制約」を導入しつつ、
それでも市場がどのように均衡を保つかを数学的に説明するフレームワークである。
EQGアプローチによって、解析的な均衡価格と最適戦略の導出が可能となった。
3. 部分観測下の最適戦略 ― フィルタリングと動学最適化
本章では、投資家がリスクプレミアムを直接観測できない状況下で、どのように最適な投資戦略を決定するのかを解説します。
鍵となるのは、「観測可能な株価」から「非観測のリスクプレミアム」を推定する」というフィルタリングの仕組みと、それを最適化理論に結びつける方法です。
3.1 情報制約と推定問題
投資家は、株価プロセス
を観測しますが、リスクプレミアム
は直接には見えません。
よって、投資家の意思決定は「部分観測(partial observation)」の問題となります。
このとき、投資家が活用できる情報は、
という、株価の過去履歴から生成されるフィルトレーション(情報の流れ)です。
しかし、リスクプレミアム
の背後には、
経済ファンダメンタルズや投資家の集団行動など、観測不可能な要因が存在します。
この「見えない要素」をどのように扱うかが、部分観測モデルの中心課題です。
3.2 条件付き期待値としてのフィルタリング
非観測のリスクプレミアム
の推定値を、次のように定義します。
これは、カルマンフィルタに相当する構造で、
投資家は「過去の価格の動き」から「現在のリスクプレミアム」を最適に推定します。
この推定値
は、将来の期待リターンの代理変数として機能します。
つまり、投資家は「見えない真のリスクプレミアム」ではなく、「推定された期待収益率」をもとに投資比率を決定するのです。
3.3 最適制御問題の定式化
投資家の目的は、最終資産
の期待効用を最大化すること
ただし、資産プロセスは次のように進化します。
観測できない
の代わりに、推定値
を使って制御方程式を書き換えると、
ここで
は「観測ノイズを含む修正ブラウニアン運動」であり、
投資家がアクセスできる情報セットに基づいた確率過程です。
3.4 最適化の解 ― Exponential Quadratic Gaussian (EQG) 構造
指数型効用関数とガウス過程の組み合わせ(EQG構造)により、
この最適化問題は解析的に解くことが可能になります。
最適投資比率
は、次のように導出されます。
この式は、ミーントリッヒ(mean–variance)構造を保ちながら、
「観測可能な推定リスクプレミアム
」を使って最適ポジションを決定する点が特徴です。
つまり、投資家は完全情報下の最適戦略に似た形を維持しつつ、
リスクプレミアムを「リアルタイムで学習しながら」動的にポートフォリオを調整します。
3.5 フィルタリングの動学方程式(更新則)
推定値
は固定ではなく、
観測データの更新によって時間とともに修正されます。
この動きを表すフィルタリング方程式(カルマン型)は、
-
:リスクプレミアムのドリフト構造
-
:カルマンゲイン(観測誤差と推定誤差のバランス係数)
この式は、「新しい価格情報が到着するたびに、推定リスクプレミアムを修正する」仕組みを表しています。
すなわち、投資家の行動は静的ではなく、常に学習(learning)プロセスとして動的に更新されるのです。
3.6 市場均衡条件との統合
平均場均衡の観点からは、すべての投資家の平均行動が市場のリスクプレミアムを内生的に決定します。
均衡条件は次のように書けます。
ここで
は、すべての投資家の平均的投資比率。
つまり、個々の最適行動が集まることで、リスクプレミアムが自己整合的に決まるという構造です。
この関係により、部分観測・推定・最適化・均衡がすべて連動します。
3.7 理論的含意
本章の結果から、次の重要な含意が導かれます。
-
部分観測下でも市場均衡は成立し得る。
情報制約は行動を遅らせるが、推定を通じて均衡は回復可能。 -
リスクプレミアムは「観測による学習結果」として内生化される。
つまり、市場参加者の学習行動自体が価格形成に組み込まれる。 -
完全情報モデルの特例を自然に包含。
リスクプレミアムが観測可能な場合、となり、古典的均衡モデルを再現する。
第3章まとめ
部分観測下では、投資家はリスクプレミアムを「推定」しながら行動する。
EQGアプローチにより、推定値に基づく最適投資比率が解析的に導出され、
さらに全体の平均行動を通じてリスクプレミアムが内生的に決定される。
情報の不完全性を含めた動的均衡の枠組みが、ここで初めて体系化された。
4. 均衡価格の導出と動学特性 ― 情報不完全性が市場価格に与える影響
本章では、部分観測下で導かれる均衡価格と、情報の不完全性が価格形成に及ぼす動学的効果を分析します。
平均場均衡(Mean Field Equilibrium, MFE)の枠組みの中で、個々の投資家の学習行動がどのように市場価格へ反映されるのかが核心です。
4.1 均衡の定義と基本条件
まず、平均場均衡の基本構造を確認します。
各投資家
は、推定されたリスクプレミアム
に基づき最適な投資比率を選択します。
市場全体でのリスクプレミアム
は、全投資家の平均行動により決定されます:
ここで「平均場」仮定により、投資家数
の極限を考えると、
各投資家の最適行動の平均が市場全体を代表するようになります。
結果として、均衡リスクプレミアムは次の固定点条件で特徴づけられます。
すなわち、投資家の推定行動が自己整合的に市場価格へ反映されるという構造が成立します。
4.2 部分観測による「学習ノイズ」の影響
投資家はリスクプレミアム
を正確には知らず、観測可能な価格系列からフィルタリングによって近似します。
このとき、推定誤差(学習ノイズ)が生じ、均衡価格に動的なゆらぎをもたらします。
モデル上、価格ダイナミクスは以下のように表されます。
この式において、
は投資家の主観的推定であり、真のリスクプレミアム
と必ずしも一致しません。
その差
が、「情報の不完全性」がもたらす価格変動要因(学習ノイズ)です。
結果として、市場全体のリターン構造は次のように分解できます。
この「誤差成分」
は、価格のボラティリティ増幅や一時的な乖離の要因として機能します。
4.3 均衡価格の解析的表現
指数二次ガウス(Exponential Quadratic Gaussian, EQG)アプローチの利点は、
このような非線形な均衡条件でも、価格関数が解析的に導ける点にあります。
株価
の対数変換
をとると、
のダイナミクスが線形ガウス過程に従うため、
のように明示でき、結果として
もガウス分布に従います。
したがって、均衡価格の期待値と分散は閉形式で表現可能です。
この結果は、部分観測のもとでも市場が確率的に安定した形で均衡を保つことを示しています。
4.4 情報構造が価格変動に与える影響
情報の非対称性(部分観測)は、次の2つのチャネルを通じて価格ダイナミクスを歪めます。
-
短期的な過大反応(Overreaction)
新しい情報が入るたびに、投資家の推定が急変し、
株価が一時的に過剰変動を起こす。 -
長期的な過少反応(Underreaction)
本質的なリスクプレミアムの変化が完全に伝わらず、
価格調整が遅れる。
これらは、部分観測市場の特徴であり、行動ファイナンスの「情報遅延効果」にも通じます。
本モデルは、この現象を合理的期待下の学習メカニズムとして理論的に再現しています。
4.5 情報不完全性のマクロ的影響
平均場均衡の視点で見ると、投資家の推定誤差が累積的に市場全体に波及します。
すなわち、個々の学習ノイズが平均化されず、むしろ集団行動を通じて価格のボラティリティを押し上げる可能性があるのです。
定常状態における分散の導出結果は次のようになります。
つまり、観測誤差(
)が残る限り、
市場全体の変動性は「真のリスクプレミアムの分散+情報誤差の分散」として上乗せされます。
この点が、完全情報モデルとの定量的な乖離です。
4.6 理論的含意 ― 「情報の不完全さ」は市場の本質
本章の知見は、次のようにまとめられます。
-
情報制約下でも市場は均衡し得るが、その均衡は確率的(stochastic equilibrium)である。
-
リスクプレミアムは、推定・学習を通じて内生的に決定される変数になる。
-
部分観測がもたらす「ノイズ」は、価格変動・ボラティリティの自然な源泉である。
これにより、従来の「完全情報・静的均衡」モデルでは説明できなかった、
市場の不安定性や短期的な過熱現象の理論的基盤が明示されました。
第4章まとめ
部分観測下では、価格は情報更新とともに常に修正される「動的均衡過程」として形成される。
情報の不完全性がボラティリティや過剰反応の源泉となり、
平均場均衡における「確率的安定性」の理論的裏付けを提供した。
-
ドリフトや価格にポアソンジャンプを追加(強度・ジャンプ分布は状態依存可)。
-
部分観測下では、ジャンプタイミング自体が観測ノイズと絡むため、フィルタに補正項(ジャンプ検出の尤度更新)が必要。
- 拡張カルマン(EKF)/無香料カルマン(UKF)で二次近似。
- 粒子フィルタで非ガウス・非線形を直接サンプリング。
- 平均場側はマッキーン–ヴラソフ型SDEに拡張し、分布進化をFokker–Planckで近似。
- フィルタは生存確率を逐次更新。
- 均衡条件は「生存条件付き」期待に変換。
- ショック後の再均衡(市場クリアリング)を構造化できる。
-
動機:現実の市場は制約下で価格が形成され、学習も歪む。
-
モデル化:最適化に不等式制約(空売り不可、レバ制限)、目的関数に取引費用(一次・二次)を追加。
-
含意:最適比率はバンド制御に変わり、平均場の固定点は補題条件付き(KKT)で決まる。部分観測の誤差が広がると、取引バンドに滞留しやすくなり、ボラの粘着性が上がる。
- 識別:観測(価格)と状態(真のリスクプレミアム)を分離するため、高頻度リターンの実現ボラ、アナリスト改訂・ニュース頻度など情報到来代理変数、オプション由来のインプライドモーメントを併用。
- 推定:EM(E-step: フィルタ/スムーザ、M-step: パラメータ更新)、粒子EM、ベイズMCMC等。
- 安定化:状態空間の再スケール、パラメータの事前分布で過学習を抑制。
-
横断面:推定リスクプレミアムでFama–MacBethを行い価格付け可能性を検証。
-
時系列:ニュース/決算周辺での過大反応→反転の強度を再現できるか。
-
オプション:リスク中立 vs 実世界の乖離(variance risk premium)を整合。
-
学習速度:流動性・出来高・銘柄カバレッジでフィルタ利得がどう変わるか(銘柄特性との相関)。
-
リスク配分:推定誤差の分散を独立のリスク予算として管理。
-
ニュース対応:ショック直後はフィルタ誤差が拡大、取引バンド拡張や一時的デレバでオーバートレードを回避。
-
ヘッジ:ボラとジャンプに分解した二層ヘッジ(例:ボラ・スワップ + プットテール)。
-
モデルリスク:フィルタ・パラメータの線形近傍頑健化(worst-case ドリフトに対するロバスト制御)。
-
可解性 vs 現実性:EQGの強み(解析性)は、非線形・非ガウス化で薄れる。
-
識別難:価格だけでは学習ノイズと真のドリフトの分離が難しい(補助データ必須)。
-
平均場近似:有限投資家数・大口主体の存在で戦略的相互作用が強いと近似が崩れる。
平均場均衡(Mean Field Equilibrium)
多くの投資家が相互に影響し合う状況を、代表的な「平均的エージェント」の行動で近似して分析する手法。
人数が非常に多い市場(例:無数の投資家が存在する株式市場)で、全体の動きを合理的に簡略化して表現できる。
部分観測(Partial Observation)
投資家が市場の全情報(例えば、リスクプレミアムの真値)を直接観測できず、株価など一部の情報から間接的に推定して行動する状況。
現実の市場参加者は、将来のリターンやリスクを完全には把握できないため、より現実的な前提。
指数二次ガウス(Exponential Quadratic Gaussian)モデル
数理ファイナンスで用いられる構造の一種で、リスクや効用を指数関数的に扱い、分布をガウス(正規分布)で近似する枠組み。
このモデルを使うと、解析的な(数式で解ける)均衡解を導出しやすい。
ブラウニアン運動(Brownian Motion)
確率的に連続変化する過程。株価や金利のランダムな変動を数学的に表す基本モデル。
金融数理における「ノイズ」や「不確実性の源」として用いられる。
リスクプレミアム(Risk Premium)
投資家がリスクを取ることに対して追加で求める報酬(超過リターン)。
このモデルではリスクプレミアムを観測できない潜在変数(latent variable)として扱い、投資家が市場価格から推定する。
ノンリニア・フィルタリング(Nonlinear Filtering)
観測データから隠れた確率過程(ここではリスクプレミアム)を推定する数学的手法。
この研究では将来的な拡張方向として、より現実的な非線形動学を検討している。
市場クリアリング条件(Market Clearing Condition)
市場全体で「需要=供給」が一致する条件。すなわち、全投資家の最適行動が合計されて、市場が均衡状態にあることを意味する。
ジャンププロセス(Jump Process)
価格やリターンに突発的な変動(ショック)を導入する確率過程。
将来の拡張研究では、デフォルトや突発イベントをこのプロセスでモデル化することが想定されている。
-
投資家は、リスクプレミアムの真値を直接は知らず、観測できる株価からその動きを学習する。
-
その不確実性の中でも、各投資家が最適行動を取り、市場全体で価格が内生的に決まる。
-
その結果として得られる「平均場均衡(Mean Field Equilibrium)」は、 学習・期待形成・市場反応が同時に噛み合った、より現実的な資産価格の姿を描き出している。
-
現代金融市場は「不確実性の下での知覚の市場」である
— 投資家は価格を通じて学び、他者の行動を通じて市場を推定している。 -
リスクプレミアムは外生的ではなく「市場内部から生まれる」
— 個々の投資家の期待形成が集合して市場価格に反映される。 -
解析的均衡(Exponential Quadratic構造)は、数理モデルと行動的現実の橋渡しを可能にする
— 数式上の扱いやすさを保ちながら、行動的・情報的制約を導入できる。
-
ジャンプを伴う非連続的市場動学:危機・デフォルトを取り入れた現実的リスク構造の導入。
-
非線形フィルタリング:投資家がリスク推定を誤る状況をモデル化。
-
摩擦や制約を含む市場設計:取引コストや情報非対称の影響を内生的に組み込む。
本記事では、最新のファイナンス研究(SSRNなどの学術論文)を「個人投資家が実務で使える形」で要約・解説しています。ミクロ構造・流動性・市場心理など、価格変動の本質に迫る研究を厳選。 金融・経済論文まとめ:投資家のための最新研究【論文[…]