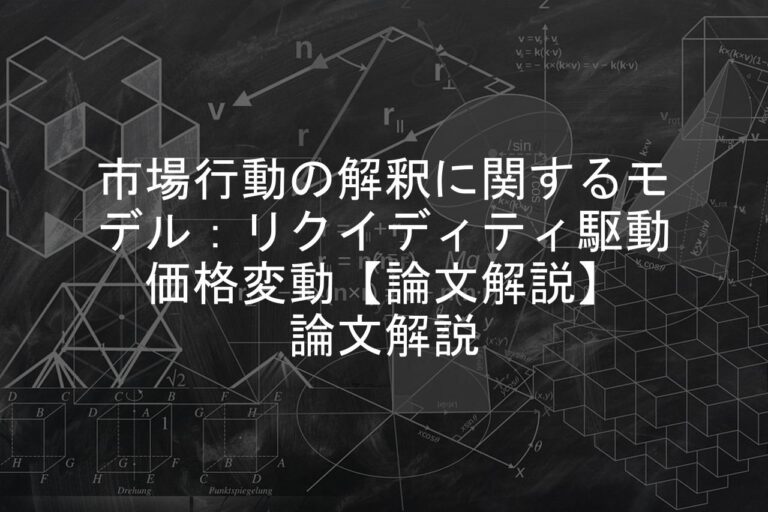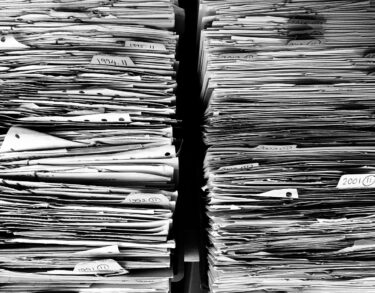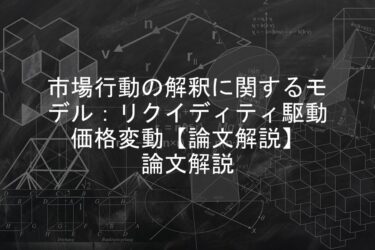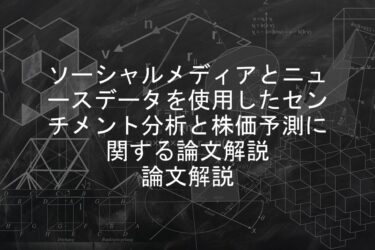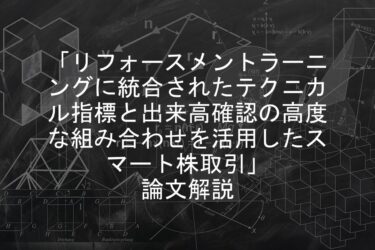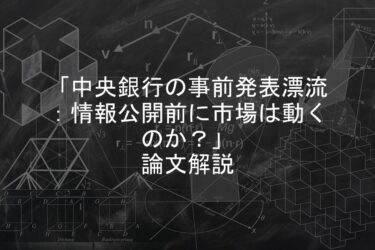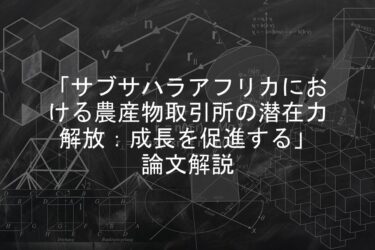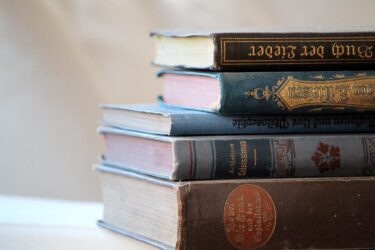株価の動きは「ニュース」ではなく「流動性」で決まる──
本記事では、SSRN掲載の最新論文「Liquidity-Driven Price Action(流動性駆動モデル)」をもとに、
VWAP・出来高・リクイディティゾーンを組み合わせて大口投資家の呼吸を読む手法を解説します。
テクニカル指標では見えない「流動性の偏り」を可視化することで、
デイトレ・スイング双方で勝てる価格帯を見抜く実践フレームワークが見えてきます。
論文:Liquidity-Driven Price Action: A Model for Interpreting Market Behaviour
(流動性に基づく価格変動モデル:市場行動の解釈枠組み)
出典元:SSRN(2025/8/12掲載)
リクイディティ駆動価格アクション:市場行動を読み解く新モデルと投資戦略への応用
1. はじめに ― 価格はニュースではなく「流動性」で動く
株価を動かす本質はニュースではない。
「どの価格帯に、どれだけの注文が溜まっているか」──それが市場を動かす力です。
従来の株価分析は、移動平均線やRSI、ボリンジャーバンドなどの指標を利用してきました。
しかし近年は、「価格そのものの動き=プライスアクション」に注目が集まっています。
本研究が示す「リクイディティ駆動モデル(Liquidity-Driven Model)」は、
-
大口注文が集中するゾーン(リクイディティゾーン)
-
VWAP(出来高加重平均価格)
-
T2モメンタム(独自の短期モメンタム指標)
を組み合わせ、機関投資家や大口トレーダーの動きを反映した市場行動の解釈を試みたものです。
2. 背景 ― なぜリクイディティゾーンが重要か
-
機関投資家は「まとめて売買」するため、価格が過去の高値/安値に近づくと注文が集中する
-
この集中が「一時的な壁」や「急なブレイク」のトリガーとなる
-
個人投資家にとっては「大口の呼吸」を読むための重要な手掛かり
3. モデルの仕組み
ステップ1:リクイディティゾーンの特定
-
前回の高値・安値
-
出来高が急増した価格帯
-
VWAPに近い水準
ステップ2:技術指標との組み合わせ
-
VWAP:当日の「平均取引コスト」。価格がVWAPを超えるかどうかは、大口投資家が損益どちらに傾いているかを示す
-
Pivot Point/サポレジ:短期反転の候補
-
T2モメンタム:急激な勢いを数値化し、エントリー判断に利用
ステップ3:売買判断ロジック
買いサイン例
-
価格がリクイディティゾーンに接触
-
VWAPを上抜け
-
RSIやT2が強気シグナル
売りサイン例
-
価格がリクイディティゾーン上で反転
-
VWAP割れ
-
T2が急低下
4. 実証結果のポイント
検証対象:NSE(インド証券取引所)の主要銘柄
確認された傾向
-
リクイディティゾーン付近での価格反応が有意に高い
-
VWAP+T2モメンタムを組み合わせると「ダマシシグナル」が減少
-
デイトレでもスイングでも有効性を維持
5. 投資家への実務的示唆
デイトレード応用
-
「リクイディティゾーン+VWAP」を当日の指標に設定
例:VWAP上抜け+出来高増 → ロングエントリー
スイングトレード応用
-
小型株や高ボラ株で「リクイディティゾーン反発」を数日スパンで狙う
-
損切りはリクイディティゾーン下抜け、利確は次のサポレジライン
アルゴリズム取引応用
-
リクイディティゾーンを数値化してバックテスト可能
-
「リクイディティ薄いゾーン」は取引回避フィルタとして利用できる
6. 実務応用 ― 日本株・米国株での使い方
デイトレード戦略(日本株)
-
前日高値・安値+出来高急増ゾーンを「リクイディティゾーン」として設定
-
寄り付き後、VWAPを上抜けたタイミングでエントリー
-
出来高バーが増加している場合、短期上昇の勢い(T2)を確認
-
VWAP割れ=即撤退、ゾーン下抜けで損切り徹底
この戦略は特にマザーズ/グロース市場の中小型株で有効。
個人投資家の売買が板に反映されやすく、リクイディティゾーンの視覚的判定がしやすいためです。
スイングトレード戦略(2〜5日)
-
高ボラ銘柄で、直近リクイディティゾーン反発後の2本目を狙う
-
利確は次のサポレジ到達時(リスク対リワード=1:2が理想)
-
出来高が減少する局面では仕掛けず、「流動性回復」を待つ
米国株・大型株への応用
米国市場では、流動性が高いためVWAP基準の反転パターンが有効。
特にFOMC前後や決算発表時の「流動性空白(gap liquidity)」を観測し、VWAP再接触=短期の戻りポイントとして利用できます。
7. 日本市場での注意点とモデルの限界 ― 板構造の違いと実務上の限界
買い条件
-
前日高値付近で出来高急増
-
当日VWAPを上抜け
-
RSI 40〜60 → 中立圏から上昇中
売り条件(利益確定)
-
当日高値更新後にVWAP接触で半分利確
-
サポレジライン到達で全利確
損切り条件
- エントリー後にVWAP割れ(即撤退)
また、日本市場は海外勢が寄与する割合が高いため、流動性のタイムゾーン変動(昼休み・欧州開場前後)にも注意が必要です。
板構造とデータ特性への注意
-
東証は約定単位が細かく、VWAPの反応が遅れやすい。
→ 5分足VWAPよりも1分足VWAPを基準にした方が機能的。 -
出来高が少ない銘柄ではリクイディティゾーンが形成されにくい。
→ 目安は「日出来高10万株以上」。それ以下は誤シグナルが多発。 -
寄り付き直後(9:00〜9:10)の乱高下ではVWAPの信頼性が低い。
→ 初動5分を除外し、VWAPが安定する9:15以降を基準にする。
流動性のタイムゾーン変動
日本市場は海外投資家の影響が大きく、流動性は時間帯によって明確に変化します。
-
昼休み(11:30〜12:30)は流動性が急減
-
欧州勢参入(15:00前後)で再び板が厚くなる
このため、「時間帯ごとの流動性リズム」を意識した売買が有効です。
モデルの限界
-
出来高が少ない銘柄では機能しづらい
-
寄り付き直後やイベント直後はノイズが増える
-
アルゴ化する場合、VWAP算出の遅延や板厚の扱いが課題
それでも、VWAPとリクイディティゾーンを組み合わせることで、
相場の構造的ゆがみを可視化する有効なアプローチであることは間違いありません。
関連研究
板の厚みや約定単位(ティックサイズ)がどのように株価変動に影響するかは、
ティックサイズ変更が株価クラッシュリスクに与える影響
の研究でも詳しく検証されています。
⇒ ティックサイズ(最小値幅)が広がると、小型株では「板が厚くなり下落耐性が上がる」ことが示唆されています。
9. まとめ
「リクイディティ駆動価格アクションモデル」は、価格の動きを心理ではなく構造で捉える新しい視点です。
市場参加者の行動心理=注文集中ゾーンを基盤に、流動性の偏りから相場の呼吸を読み取ります。
-
デイトレでは「VWAP+リクイディティゾーン」で勝負ポイントを特定
-
スイングでは「反転ゾーン」を基準にリスクリワードを改善
-
アルゴでは「ノイズ相場の回避フィルタ」として活用可能
万能ではないものの、移動平均やRSIなど既存のテクニカルと併用することで、リスク調整後リターンの改善につながる有効な実務ツールになると考えられます。
この3点を理解すれば、相場は偶然ではなく構造として読めるようになります。
デイトレでもスイングでも、まず見るべきはニュースではなく流動性。
これが本論文の伝える、最も実務的で本質的なメッセージです。
関連する論文解説をもっと読みたい方は、[投資家のための最新研究論文まとめ] をチェックしてみてください。
本記事では、最新のファイナンス研究(SSRNなどの学術論文)を「個人投資家が実務で使える形」で要約・解説しています。ミクロ構造・流動性・市場心理など、価格変動の本質に迫る研究を厳選。 金融・経済論文まとめ:投資家のための最新研究【論文[…]