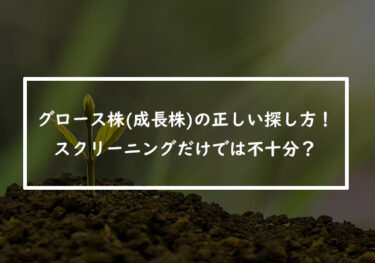株式投資の世界では、「安い株を見つける」「成長企業を見抜く」ための数字の読み方が欠かせません。
その基礎となるのが「ファンダメンタル分析」です。
PER・PBR・ROEといった基本指標から、EPS・ROA・自己資本比率・営業利益率などの財務分析まで──。
どの指標をどんな目的で使うのかを理解しておくことで、数字を感覚ではなく根拠で判断できるようになります。
本記事では、初心者から中級者までが知っておくべきファンダメンタル分析の全23指標を体系的にまとめました。
それぞれの「意味」「見方」「目安」「注意点」まで一括で学べる決定版です。
これを読めば、企業分析の地図が手に入るはずです。
このページで解説する全20指標(カテゴリ別)
- 1 ファンダメンタル分析とは?
- 2 PER・PBRなどの割安性指標
- 3 ROE・ROA・ROICなどの収益性指標
- 4 自己資本比率・負債比率などの安全性指標
- 5 EPS・売上高成長率などの成長性指標
- 6 効率性・回転率指標
- 7 株主還元・配当関連の指標
- 8 まとめ
ファンダメンタル分析とは?
株式投資の世界では、「企業の価値を数字で見抜く力」が求められます。
この力を鍛えるための基本が ファンダメンタル分析(Fundamental Analysis) です。
ファンダメンタル分析とは、企業の業績・財務・成長性などの中身を数字で評価する手法のこと。
ニュースや株価の動きに振り回されるのではなく、企業の実力に基づいて「その株が今いくらの価値を持つか?」を見極めることを目的としています。
テクニカル分析との違い
株式分析には、大きく分けて「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」の2つがあります。
| 分析手法 | 目的 | 見る対象 | 向いている投資スタイル |
|---|---|---|---|
| ファンダメンタル分析 | 企業の実力を評価 | 決算・財務・業績・指標 | 中長期投資 |
| テクニカル分析 | 株価の流れを読む | チャート・出来高・移動平均 | 短期・デイトレード |
ファンダメンタル分析は「企業の実力を測る」ための分析。
テクニカル分析は「投資家の心理を読む」ための分析。
つまり、ファンダメンタル分析は「株を買うべき理由」を教えてくれ、
テクニカル分析は「いつ買うべきか」を教えてくれる、と言えます。
「企業の中身」を数字で可視化する考え方
ファンダメンタル分析では、決算書(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)をベースに、
企業の利益・資産・負債・成長率・株主還元などを数値化して評価します。
たとえば──
-
利益をどれだけ効率よく生み出しているか(ROE・ROA)
-
財務体質は健全か(自己資本比率・負債比率)
-
成長が持続しているか(売上高成長率・EPS成長率)
-
株価は割高か割安か(PER・PBR)
このように、1つひとつの指標が企業の健康診断書のような役割を果たします。
株価の上下だけを追うのではなく、「なぜ上がったのか」「なぜ下がったのか」を数字で説明できる力がつくのです。
なぜ初心者こそファンダメンタルを理解すべきか
株式市場には、短期的なニュース・思惑・イベントがあふれています。
しかし、長期的に見れば株価は最終的に企業の実力(=ファンダメンタル)に収束します。
つまり、
「短期の波に乗るテクニカル」よりも、「土台を理解するファンダメンタル」のほうが再現性が高いのです。
初心者がいきなりチャート分析に飛び込むより、まずは企業の数字を読むことから始めると、投資判断のブレがなくなります。
まとめ:ファンダメンタル分析は「企業を理解する最初のステップ」
ファンダメンタル分析は難しそうに聞こえますが、
実際は「企業がどれだけ儲かっていて」「どれだけ安全で」「どれだけ成長しているか」を順番に確認していくだけのシンプルな作業です。
数字を「暗記」するのではなく、「意味」を理解すること。
それができれば、PERやROEのような指標は単なる数字ではなく企業の物語として見えてきます。
PER・PBRなどの割安性指標
ファンダメンタル分析の中でも、株価が割安か・割高かを判断するための代表的な指標が「PER」と「PBR」です。
これらはどちらも「現在の株価が企業の実力に対して適正かどうか」を知るための出発点。
投資判断の入り口として最もよく使われる数値です。
PER(株価収益率)|株価が利益の何倍で取引されているか
PER(Price Earnings Ratio)は、株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)で求められる指標です。
企業の利益に対して株価がどの程度の水準にあるかを示します。
計算式
例:株価1,000円、EPSが100円なら、PER=10倍
PERの目安と考え方
| PERの範囲 | 判断の目安 | 投資家の解釈 |
|---|---|---|
| 10倍以下 | 割安 | 利益に対して株価が安い |
| 10〜20倍 | 適正水準 | 多くの企業の平均値 |
| 25倍以上 | 割高 | 成長期待が織り込まれている |
ただし、
成長企業ではPERが高くても問題なし
成長性の高い企業(AI・半導体・クラウドなど)は、将来の利益を織り込んで株価が上昇します。
そのためPERが高くても、「期待先行型」として投資妙味があるケースもあります。
業績の伸びが続くなら、高PER=強気相場のサインにもなります。
PBR(株価純資産倍率)|企業の資産に対して株価は高いか?
PBR(Price Book-value Ratio)は、株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)で求められます。
企業の「純資産(資本金+利益剰余金−負債)」と株価を比較することで、解散価値に対して株価が高いか安いかを示す指標です。
計算式
PBRの目安と考え方
| PBRの範囲 | 判断の目安 | 意味 |
|---|---|---|
| 1倍未満 | 割安 | 株価が純資産を下回る(解散価値以下) |
| 1〜2倍 | 適正水準 | 多くの安定企業がこの範囲 |
| 3倍以上 | 割高 | 成長性やブランド価値が織り込まれている |
PBRが1倍を下回る企業は、「資産に対して株価が安い=割安」と見られやすいですが、
PBRが高い企業の特徴
ブランド力・特許・ITサービスなど、「目に見えない資産(無形資産)」を多く持つ企業はPBRが高くなる傾向があります。
たとえばAppleやトヨタのように、企業ブランドそのものが利益を生み出す構造では、PBR2〜3倍でも割高とは限りません。
PEGレシオ|PERに成長率を組み合わせた新しい見方
PERは便利な指標ですが、「成長スピード」を考慮していないという弱点があります。
それを補うのがPEGレシオ(Price Earnings to Growth Ratio)です。
計算式
例:PER20倍・利益成長率20% → PEG=1.0
→「株価と成長率が釣り合っている」状態。
| PEG値 | 評価 |
|---|---|
| 1.0以下 | 割安(成長に対して株価が安い) |
| 1.0〜2.0 | 適正 |
| 2.0以上 | 割高(株価が期待先行) |
PEGを使えば、「成長性を加味したPER比較」が可能になります。
グロース株(AI・半導体・ITなど)の分析に特に有効です。
EV/EBITDA倍率|企業全体の実力値を見る
PERやPBRが「株主目線の指標」だとすれば、EV/EBITDA倍率は企業全体を買収した場合の価値を測る指標です。
計算式
-
EV(Enterprise Value)=時価総額+有利子負債 − 現金
-
EBITDA=税引前利益+支払利息+減価償却費
この指標は、業種を超えて企業を横並びで比較できるのが強み。
M&A(企業買収)や海外投資家の分析でもよく使われます。
| 値の目安 | 解釈 |
|---|---|
| 5〜10倍 | 適正水準 |
| 10倍超 | 割高(成長期待) |
| 5倍未満 | 割安 or 業績不振 |
EV/EBITDA倍率は、「企業を丸ごと買うならいくら?」という観点での評価。
実質的なキャッシュ創出力を示すため、利益の変動が大きい企業でも比較的安定した分析が可能です。
計算式
企業の「売上」に対して、現在の株価(時価総額)がどの程度の水準にあるかを示します。
つまり、「この会社の1円の売上に対して、投資家がいくらの価値をつけているか」を表す指標です。
▶ PSRの目安と解釈
| PSR水準 | 評価 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1倍未満 | 割安 | 売上に対して株価が安い(低評価) |
| 1〜3倍 | 適正 | 一般的な上場企業の範囲 |
| 5倍以上 | 割高 | 高成長期待・グロース株によく見られる |
たとえば、SaaS企業やクラウド関連株では、利益よりも「売上成長率」に市場が注目するため、
PSRが10倍以上でも投資家が評価しているケースは珍しくありません。
その場合、「割高=悪い」ではなく、「将来の利益拡大を織り込んだ株価」と理解します。
▶ PSRが活きるケース
-
利益が出ていない成長企業(PERが計算できない)
-
売上拡大フェーズにあるIT・SaaS業界
-
収益性よりシェア拡大を優先する企業
PERが意味を持たない場合でも、PSRを使えば「市場がどれだけ将来を期待しているか」を把握できます。
▶ 注意点と落とし穴
-
利益率の違いを反映しないため、営業利益率が低い企業はPSRが高くても危険。
-
売上=質の高い成長とは限らない(販管費増加や広告費依存の成長は一時的)。
-
同業比較が前提:PSRは業界平均と比較して初めて意味が出る。
まとめ:PER・PBRは「入り口」、EV/EBITDAは「本質」、PSRは「利益が出ていない企業を見るためのレーダー」
PER・PBRは、初心者でも理解しやすい割安性指標。
ただし、それだけに頼ると「成長率」や「負債構造」を見落とす危険があります。
これが、上級者が行う「2段構えの分析法」です。
ROE・ROA・ROICなどの収益性指標
投資の世界では「企業の利益をどう生み出しているか」を見抜く力が重要です。
どれだけ売上が大きくても、効率的に利益を出せていなければ長期的な成長は望めません。
そこで注目されるのが、ROE・ROA・ROICといった「収益性指標」です。
これらは、企業がどれだけの資産・資本を使って利益を生み出しているかを数値化したもの。
つまり、「効率よく稼げている会社」かどうかを見極める基準となります。
ROE(自己資本利益率)|株主のお金でどれだけ利益を出しているか
ROE(Return on Equity)は、株主が出資した自己資本をどれだけ効率よく増やしているかを示す指標です。
計算式
ROEが高いほど、「株主が預けたお金をうまく増やしている」会社ということになります。
ROEの目安と評価
| ROE水準 | 評価 | 企業タイプの例 |
|---|---|---|
| 5%未満 | 効率が悪い | 資産型・成熟企業 |
| 5〜10% | 平均水準 | 多くの上場企業 |
| 10〜15% | 優秀 | 成長企業・製造業など |
| 15%以上 | 高収益 | 外資・IT・金融など |
それを上回る企業は「資本効率の高い優良株」として注目されます。
ROEの注意点:負債が多くてもROEは上がる
ROEは「自己資本」を分母にするため、借金(負債)を増やせばROEが高く見えることがあります。
そのため、ROEだけで判断せず、ROA(総資産利益率)とセットで見るのが重要です。
こちらの記事で徹底解説しています。
ROE(自己資本利益率)とは?|高ROE企業の見方と落とし穴
ROA(総資産利益率)|会社全体の資産をどれだけ活かして利益を出しているか
ROA(Return on Assets)は、企業が持つすべての資産(現金・在庫・設備など)をどれだけ有効に使って利益を上げているかを表します。
計算式
ROAが高いほど、資産を効率的に使って稼げていることを意味します。
たとえばROAが8%の企業は、「会社の資産100円で8円の利益を出している」状態です。
ROAの目安と評価
| ROA水準 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 3%未満 | 効率が悪い | 在庫・固定資産が多い業種 |
| 3〜7% | 平均水準 | 一般的な製造業 |
| 8〜10%以上 | 優秀 | サービス・IT・金融など軽資産企業 |
ROAは、借入金を含む企業全体の資産効率を測るため、「経営のうまさ」を見るには最適な指標。
特に同業他社と比べると、経営効率の差が明確に出やすいです。
ROE = ROA ×(総資産 ÷ 自己資本)
ROIC(投下資本利益率)|本業でどれだけ稼げているか?
ROIC(Return on Invested Capital)は、事業に使っている資本(負債+自己資本)からどれだけ利益を生み出しているかを測る指標です。
より実践的で、機関投資家やファンドが重視する経営効率の最重要指標です。
計算式
ROEやROAが最終利益ベースであるのに対し、ROICは「営業利益」ベースなので、本業の収益力が直接反映されます。
ROICの目安と考え方
| ROIC水準 | 評価 | 意味 |
|---|---|---|
| 5%未満 | 効率が低い | 資本過多・成長鈍化 |
| 5〜10% | 平均的 | 通常の事業構造 |
| 10%以上 | 高効率 | 成長企業・グローバル企業 |
ROICが高い企業ほど、借金を使っても効率よく利益を生み出しており、「経営の上手さ」が数値に現れます。
とくに、ROIC > WACC(資本コスト)である企業は「資本を有効活用している理想的な状態」です。
ROE・ROA・ROICの違いを整理
| 指標 | 計算対象 | 視点 | 評価軸 |
|---|---|---|---|
| ROE | 自己資本 | 株主視点 | 株主が得るリターン |
| ROA | 総資産 | 経営全体視点 | 資産効率・経営効率 |
| ROIC | 投下資本 | 事業視点 | 本業の稼ぐ力・資本効率 |
粗利率(売上総利益率)|ビジネスの強さを示す利益の基礎体力
粗利率(Gross Profit Margin)とは、売上高から売上原価を引いた「売上総利益(=粗利)」が、売上全体の中でどれだけの割合を占めているかを表す指標です。
つまり、「売った分のうち、どれだけ利益が残っているか」を示すもので、企業の価格競争力・ブランド力・コスト構造の強さを見抜くために欠かせません。
| 粗利率 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 50%以上 | 非常に高収益 | IT・ソフトウェア・ブランド産業など |
| 30〜50% | 良好 | 製造・サービス業の平均水準 |
| 10〜30% | 低水準 | 小売・飲食など原価率の高い業種 |
| 10%未満 | 要注意 | コスト構造に課題がある可能性 |
▶ 解釈と活用ポイント
-
粗利率が高い=価格支配力がある企業。
独自ブランド・高付加価値商品を持つ企業ほど粗利率が高い傾向にあります。 -
粗利率が安定している企業=コスト管理が優秀。
原材料費や人件費の変動に左右されにくい構造を持っている可能性があります。 -
売上が増えても粗利率が下がる企業=値引き競争中。
成長に見えるが、利益の質が悪化しているサインなので要注意。
▶ 粗利率と営業利益率の違い
| 指標 | 対象 | 意味 |
|---|---|---|
| 粗利率 | 売上 − 原価 | 商品・サービスの売る力 |
| 営業利益率 | 売上 − 経費(販管費含む) | 経営全体の“稼ぐ力” |
粗利率は「商品力」や「コスト構造」の評価、
営業利益率は「経営効率」や「マネジメントの巧さ」を見るために使い分けます。
まとめ:ROE・ROA・ROICを組み合わせてこそ本質が見える
ROEが高い=優良企業とは限りません。
ROAで資産の使い方を、ROICで事業の収益力を確認して初めて、企業の本当の強さが見えてきます。
① ROEで収益性を確認
② ROAで経営効率を比較
③ ROICで事業の実力を測定
自己資本比率・負債比率などの安全性指標
―「潰れない企業」を見抜くための数字―
どんなに利益を出している企業でも、資金繰りが悪化すれば一瞬で経営危機に陥ることがあります。
だからこそ、投資家にとって「企業の財務体力」を見極めることは欠かせません。
ここでは、企業の安定性・倒産リスクを判断するうえで重要な3つの指標、自己資本比率・負債比率・流動比率(+当座比率) を中心に解説します。
自己資本比率(Equity Ratio)|どれだけ自分のお金で経営しているか
自己資本比率とは、企業がどの程度、自己資金で事業を運営しているかを示す指標です。
「安全性を見るなら、まずコレ」と言われるほど基本中の基本。
計算式
意味と見方
自己資本比率が高いほど、借入金に頼らず安定した経営をしている企業と言えます。
一方、比率が低い企業ほど、外部からの借入(負債)に依存している状態です。
目安の基準
| 自己資本比率 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 40%以上 | 優良 | 借金に頼らない安定経営 |
| 20〜40% | 普通 | 多くの上場企業がこの水準 |
| 20%未満 | 要注意 | 借入依存・リスク高め |
サービス業・ITなど軽資産企業では50%以上を目指すのが理想です。
負債比率(Debt Ratio)|借金の割合を可視化する
負債比率は、自己資本に対する負債の割合を表す指標で、「どれだけ借金に頼っているか」を確認できます。
計算式
見方とポイント
負債比率が高いほど、借入金の割合が大きく、返済負担が重くなります。
ROE(自己資本利益率)を高めるために負債を利用する企業もありますが、
リスクコントロールが甘いと、景気悪化時に資金繰り破綻の恐れがあります。
目安の基準
| 負債比率 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 100%未満 | 健全 | 借入依存が少ない |
| 100〜200% | 普通 | 設備型企業に多い |
| 200%超 | 要注意 | 借入リスク高・利払い負担大 |
負債でROEを上げているケースも多いので、ROEと負債比率はセットで確認すること。
流動比率(Current Ratio)|短期的な支払い能力を測る
流動比率は、企業が1年以内に返済しなければならない負債を、どれだけの流動資産で賄えるかを示す指標です。
つまり「目の前の支払いに耐えられるか」を判断するもの。
計算式
見方と目安
| 流動比率 | 評価 | 状況 |
|---|---|---|
| 200%以上 | 非常に健全 | 現金余裕あり・好財務 |
| 100〜200% | 標準的 | 多くの上場企業 |
| 100%未満 | 注意 | 資金繰りリスクあり |
特に中小企業やベンチャーでは、この指標が資金繰りリスクのバロメーターになります。
当座比率(Quick Ratio)|即金性を重視した安全性指標
当座比率は、流動資産の中でも現金化しやすい資産(現金・預金・売掛金など)だけを対象にした指標。
「今すぐ支払いが来ても耐えられるか?」を測る、より厳しい安全性テストです。
計算式
目安
| 当座比率 | 評価 |
|---|---|
| 150%以上 | 非常に健全 |
| 100〜150% | 標準的 |
| 100%未満 | 資金繰りに注意 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(Interest Coverage Ratio)
「利息をどれだけ余裕を持って払えるか」を測る安全性指標インタレスト・カバレッジ・レシオ = 営業利益 ÷ 支払利息
インタレスト・カバレッジ・レシオとは、企業が借入金の利息をどれだけ余裕を持って支払えているかを示す指標です。
単に借金の量を見るだけでなく、「稼ぐ力に対して返済負担が重すぎないか?」を判断できる、実践的な財務健全性チェックの1つです。
計算式
▶ 意味と解釈
この数値が高いほど、「営業利益で利息を余裕を持って賄えている」状態を意味します。
逆に、1倍を下回ると、営業利益では利息も払えない=財務リスクが高い状態です。
| カバレッジ倍率 | 評価 | 状況 |
|---|---|---|
| 10倍以上 | 非常に健全 | 利息支払いに余裕があり、財務安定性が高い |
| 5〜10倍 | 安定水準 | 一般的な上場企業の範囲 |
| 1〜5倍 | 注意水準 | 景気悪化で赤字転落リスクあり |
| 1倍未満 | 危険水準 | 利払いすら営業利益で賄えない状態 |
▶ チェックのポイント
-
ROEやROAが高くても、利息負担が重いと危険。
借入で成長を加速させている企業は、必ずこの数値も確認しましょう。 -
金利上昇局面では特に重要。
支払利息が増えるとレシオが急低下し、資金繰りに直結します。 -
営業利益ではなくEBIT(利息・税引前利益)を使う場合もある。
海外企業や英語表記では「Interest Coverage Ratio=EBIT ÷ Interest Expense」として開示されています。
▶ 補足:黒字でも倒産する企業の典型例
営業利益が出ていても、借入金の利払い負担が大きいと、キャッシュフローが枯渇することがあります。
このため、インタレスト・カバレッジ・レシオは「黒字倒産を防ぐための指標」とも言われています。
まとめ:安全性分析は攻める前の守り
自己資本比率・負債比率・流動比率を押さえることで、
「利益は出ているけど財務的に危ない企業」を見抜くことができます。
「収益性を見る前に、安全性を確認する。」
ROEやPERで伸びる企業を探す前に、まずは潰れない企業をスクリーニングする。
それが長期投資の第一歩です。
EPS・売上高成長率などの成長性指標
―「これから伸びる企業」を見抜くために―
どれだけ財務が安定していても、企業に成長がなければ株価は上がりません。
株価の本質は「将来の利益期待」であり、投資家は常に未来を先読みして売買しています。
ここでは、企業の成長力を判断する3大指標
EPS(1株あたり利益)・売上高成長率・営業利益率を中心に解説します。
EPS(Earnings Per Share)|1株あたりどれだけ儲かっているか
EPS(1株当たり利益)は、企業が株主1人あたりにどれだけ利益をもたらしているかを示す指標。
PERやROEと並んで株価分析の基礎三本柱のひとつです。
計算式
見方と活用法
EPSが上昇している=企業の利益が順調に増加しているサイン。
株価が一定でもEPSが伸びていれば、実質的には割安化(PER低下)していることになります。
| EPSの変化 | 株価 | PER | 解釈 |
|---|---|---|---|
| EPS上昇 | 変わらず | 低下 | 割安化・成長中 |
| EPS低下 | 変わらず | 上昇 | 割高化・減益懸念 |
売上高成長率(Revenue Growth Rate)|企業の勢いを数字で測る
売上高成長率は、企業の売上が前年に比べてどれだけ伸びたかを表す指標です。
企業のビジネスモデルが市場に浸透しているかどうかを判断できます。
計算式
目安と基準
| 成長率 | 評価 | 状況 |
|---|---|---|
| 10%以上 | 高成長企業 | 拡大フェーズ(例:新興IT、AI関連) |
| 3〜10% | 安定成長 | 中堅〜成熟企業 |
| 0〜3% | 停滞 | 成熟・競争激化 |
| マイナス | 減収 | 業績悪化・要注意 |
連続でプラス成長を維持している企業は、ビジネスモデルが強い証拠です。
営業利益率(Operating Margin)|本業の稼ぐ効率を示す
営業利益率は、売上に対してどれだけの営業利益を出せているかを表す指標。
本業の効率性を測るため、ファンダメンタル分析では最も注目される収益性指標のひとつです。
計算式
業界別の目安
| 営業利益率 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 15%以上 | 非常に優秀 | 高収益企業(例:製薬・ITプラットフォーム) |
| 10%前後 | 良好 | 競争力のあるビジネスモデル |
| 5%未満 | 要改善 | 薄利多売・競争過多 |
| 0%以下 | 赤字 | 継続リスクあり |
価格転嫁ができるビジネス(例:ソフトウェア、ブランド産業)は景気に強い傾向があります。
3指標を組み合わせた成長力の見方
成長性を多角的に評価するには、EPS・売上高成長率・営業利益率のトライアングル分析が有効です。
| 状況 | EPS | 売上高成長率 | 営業利益率 | 解釈 |
|---|---|---|---|---|
| ① 高成長・高利益 | ↑ | ↑ | ↑ | 優良グロース企業(例:キーエンス、任天堂) |
| ② 売上伸びるが利益低下 | ↑ | ↑ | ↓ | コスト増・効率低下 |
| ③ 売上横ばい・EPS上昇 | ↑ | → | ↑ | 効率改善・経営努力型 |
| ④ 売上減・EPS減 | ↓ | ↓ | ↓ | 業績悪化・撤退検討 |
一方、売上だけ伸びて利益率が下がる企業は拡大疲れの兆候に注意。
EPS成長率(CAGR)|利益の伸びを年単位で可視化する
EPS成長率(Earnings Growth Rate)は、企業がどれだけのスピードで利益を増やしているかを表す指標です。
「EPSが毎年どれくらい伸びているか?」を見ることで、企業の成長力や経営の一貫性を判断できます。
CAGR(年平均成長率)
計算式
CAGR(%)={(最終年のEPS ÷ 初年度のEPS)^(1/年数) − 1} × 100
→ CAGR=(160 ÷ 100)^(1/5) − 1 ≒ 9.9%
▶ 見方と判断の目安
| EPS成長率(CAGR) | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 15%以上 | 高成長企業 | IT・半導体・新興グロース系など |
| 5〜15% | 安定成長 | 一般的な製造業・サービス業 |
| 0〜5% | 停滞 | 成熟・競争激化セクター |
| マイナス | 減益 | 事業構造の見直しが必要 |
▶ 解釈と活用ポイント
-
EPS成長率が安定して高い企業=利益の再現性が高い。
単発の好決算ではなく、継続的に利益を伸ばしている企業は経営基盤が強い。 -
PERと組み合わせると「PEGレシオ」に発展。
PER ÷ 成長率 = PEGレシオ。
株価が成長力に対して割高かどうかを判断できる。 -
CAGRで見ることでブレを除去。
短期的な業績変動や一時的な特需を平均化し、真の成長トレンドを把握できる。
▶ 具体例
-
A社:EPS(100→200円/5年)→ CAGR=14.9%
→ 長期的な利益成長が続く安定優良株。 -
B社:EPS(100→120円/5年)→ CAGR=3.7%
→ 成熟産業。今後の成長テーマが重要。
まとめ:成長性は未来の株価を先取りする分析
PERやPBRが「現在の評価」だとすれば、成長性指標は「将来の期待値」。
株価は過去の利益ではなく、未来の成長率を織り込みながら動きます。
成長性分析は、今後も伸びる企業をいち早く見抜くレーダーです。
効率性・回転率指標
―「どれだけ少ない資産で利益を生み出しているか」―
企業の成長性や収益性が高くても、それを支える資産の使い方が非効率だと、最終的な利益は伸び悩みます。
つまり、「いかに少ない資産で効率よく稼げるか」が企業経営の本質です。
この章では、総資産回転率・在庫回転率・売掛金回転率など、経営の効率性を可視化する重要指標を解説します。
総資産回転率(Total Asset Turnover)|企業の資産効率を測る基本指標
総資産回転率は、企業が保有する資産をどれだけ効率的に使って売上を上げているかを表す指標です。
計算式
見方と判断基準
| 総資産回転率 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 2.0倍以上 | 優秀 | 軽資産・効率経営(例:小売、外食) |
| 1.0〜2.0倍 | 平均的 | 一般的な製造業水準 |
| 1.0倍未満 | 低効率 | 設備投資負担・在庫過多の可能性 |
一方で、重厚長大型の産業(鉄鋼・電力など)は構造的に低くなる傾向があるため、同業他社比較が必須です。
在庫回転率(Inventory Turnover)|在庫をどれだけ早く現金化できるか
在庫回転率は、在庫がどれくらいのスピードで売れているかを示す指標です。
商品を抱えすぎるとキャッシュフローが悪化し、利益を圧迫します。
計算式
見方と判断のポイント
| 在庫回転率 | 評価 | 状況 |
|---|---|---|
| 高い(10倍以上) | 優秀 | 在庫の流動性が高く、販売好調 |
| 中程度(5〜10倍) | 標準 | 適正在庫を維持 |
| 低い(5倍未満) | 注意 | 在庫滞留・売れ残りリスク |
例
-
アパレル → 3〜5倍
-
コンビニ → 15倍以上
-
家電量販 → 8〜10倍
売掛金回転率(Accounts Receivable Turnover)|回収スピードを見る
売掛金回転率は、販売後の代金をどれだけ早く回収できているかを示します。
特にBtoB企業では、資金繰りの健全性に直結する指標です。
計算式
判断基準
| 売掛金回転率 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 高い(10倍以上) | 回収早い | 資金効率良好・現金化が早い |
| 中程度(5〜10倍) | 標準 | 安定経営 |
| 低い(5倍未満) | 遅い | 回収リスク・取引先依存大 |
特に急成長企業では、売上拡大に伴って回収管理が追いつかず、資金ショートを起こすケースもあります。
固定資産回転率(Fixed Asset Turnover)|設備投資の効率を見る
固定資産回転率は、工場・設備・土地などの資産をどれだけ効率的に使って売上を上げているかを測る指標です。
計算式
業界別の目安
| 固定資産回転率 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| 5倍以上 | 優秀 | 設備軽めの業種(小売・IT) |
| 2〜5倍 | 平均的 | 製造・建設業など |
| 1倍未満 | 低効率 | 設備依存・老朽化リスクあり |
設備投資と売上のバランスを時系列で追うと、経営の質が見えます。
回転率の総合的な見方
複数の回転率を組み合わせることで、企業の経営サイクルを俯瞰できます。
| 指標 | 主な意味 | 改善の方向性 |
|---|---|---|
| 総資産回転率 | 全体の資産効率 | 売上拡大 or 資産圧縮 |
| 在庫回転率 | 在庫の流動性 | 在庫最適化・仕入改善 |
| 売掛金回転率 | 資金回収速度 | 取引条件の見直し |
| 固定資産回転率 | 設備の生産性 | 設備更新・アウトソース化 |
特に、総資産回転率 × 営業利益率 の掛け合わせは「ROA(総資産利益率)」に直結します。
まとめ:効率性指標は経営の筋肉量を測る
売上や利益だけでは見えない企業の「強さ」は、資産をどう動かしているかに表れます。
効率性指標は、まさに企業の筋肉の質を測るようなもの。
成長してもキャッシュが回らない企業は、いずれ息切れします。
健全な成長の裏には、必ず効率の良い資産運用がある。
それを数値で見抜くのが、この第6章の目的です。
株主還元・配当関連の指標
―「企業が株主をどれだけ大切にしているか」を測る数値―
ファンダメンタル分析では、利益を出す力だけでなく、
その利益をどう株主に還元しているかも重要な視点です。
配当や自社株買いは、企業が株主へ「利益を共有します」という意思表示。
特に日本株では、ここ数年で還元姿勢の強い企業が急増しており、
「高配当+増配傾向の銘柄」は安定志向の投資家に人気です。
ここでは、配当関連の主要5指標をわかりやすく整理します。
1. 配当利回り(Dividend Yield)|株主還元の実利を測る
配当利回りは、株価に対してどれだけの配当をもらえるかを示す指標です。
いわば「株の利息」にあたります。
計算式
判断の目安
| 配当利回り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 4%以上 | 高配当銘柄 | 安定・人気セクターに多い |
| 2〜3% | 平均的 | 日経平均の平均水準 |
| 1%以下 | 低配当 | 成長重視(再投資型)の企業 |
継続的に配当を出せているか(=増配トレンド)が大事です。
2. 配当性向(Payout Ratio)|どのくらい利益を還元しているかを見る
配当性向は、企業の利益のうち、どれだけを配当に回しているかを示す指標です。
計算式
判断の目安
| 配当性向 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 50%以上 | 積極的還元 | 安定企業・成熟産業に多い |
| 30〜50% | バランス型 | 配当と成長投資の両立 |
| 30%未満 | 内部留保重視 | 成長投資を優先(新興企業など) |
3. 自社株買い(Share Buyback)|見えない配当とも呼ばれる還元策
自社株買いとは、企業が市場から自社の株式を買い戻すこと。
発行済株式数が減ることで、1株当たり利益(EPS)が上昇し、結果的に株主の価値を高める効果があります。
自社株買いの主な効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| EPS上昇 | 株数が減ることで1株利益が増加 |
| 株価押し上げ | 需給改善・市場からの評価向上 |
| 敵対的買収防止 | 持株比率を高めることで防衛策に |
近年はトヨタやNTTなど大型企業も積極的に実施しています。
4. 総還元性向(Total Payout Ratio)|配当+自社株買いを合わせて評価
総還元性向は、配当金と自社株買いを合計し、
「利益のうちどれだけを株主に返したか」を測る指標です。
計算式
判断の目安
| 総還元性向 | 企業姿勢 | コメント |
|---|---|---|
| 80〜100% | 非常に株主重視 | 成熟企業・安定業界に多い |
| 50〜80% | バランス型 | 日本企業の平均水準 |
| 50%未満 | 内部留保重視 | 成長投資を優先する企業 |
ESG経営やガバナンス改革の流れも、還元強化を後押ししています。
5. 配当貴族・増配銘柄という視点
数字だけでなく、「配当の歴史」を見るのも大事です。
特に、10年以上連続増配している企業は「配当貴族」と呼ばれ、長期投資家から高く評価されます。
日本では
-
花王
-
伊藤忠商事
-
三菱UFJフィナンシャル・グループ
などが代表的な増配企業です。
無理に増配せず、業績とバランスを取りながら長く続けている企業こそ信頼できます。
まとめ:配当は「数字」よりも「姿勢」で見る
株主還元を判断する際の3ステップ
-
配当利回りで「現時点のリターン」を把握
-
配当性向・総還元性向で「企業の姿勢」を確認
-
増配・自社株買いの履歴で「一貫性」をチェック
数字は企業の過去を映しますが、還元姿勢は未来の株主との関係を映します。
配当政策が安定している企業ほど、株価も安定しやすく、長期投資の基盤として理想的です。
まとめ
結論: ファンダメンタル分析は「安い × 強い × 伸びる」企業を数字で特定するための地図。
-
割安性:PER・PBRで入口を絞り、PEG・EV/EBITDAで精査。
-
収益性:ROE・ROA・ROICで「稼ぐ力」を立体的に確認。
-
安全性:自己資本比率・負債比率・流動/当座比率で潰れにくさを担保。
-
成長性:EPS・売上高成長率・営業利益率・営業CFで未来を見通す。
-
効率性:各種回転率でキャッシュが回る体質かを点検。
運用手順(再現性の高い順)
-
スクリーニング:PER・PBRで候補抽出
-
安全確認:自己資本比率・流動/当座比率・負債比率
-
収益性→効率性→成長性の順で“質”をチェック
-
上級精査:PEG・EV/EBITDA・ROIC>WACC
-
株主還元方針(配当性向・総還元性向・自社株買い)で長期適性を判断
落とし穴(必ず回避)
-
低PER=割安 と短絡しない(業績悪化の可能性)
-
高ROEを負債レバレッジの産物と見抜けない
-
単年の数値だけで判断(推移と同業比較が基本)
-
利益≠現金(営業CFで裏取り)
-
指標の定義ゆれ(企業開示の注記を確認)
チェックリスト(保存枠)
-
PER/PBRが業界中央値と比べて妥当
-
自己資本比率≥30%(業種補正あり)、流動比率≥100%
-
ROE≥10%、ROIC≥WACC
-
売上↑・営業利益率↑・営業CF↑(3年平均)
-
総資産/在庫/売掛金回転率が同業並み以上
-
配当性向の方針明確/総還元性向の継続性
【関連記事】
FAQ
-
Q. 低PERと高配当、どっちを優先?
A. まず安全性→収益性→成長性の順で質を確認。配当は結果。 -
Q. ROEとROA、どちらが大事?
A. 両方。ROEは株主視点、ROAは経営効率。乖離は負債で説明されがち。 -
Q. グロース株の適正評価は?
A. PER単体では不十分。PEGとEV/EBITDA、営業CFの伸びを併用。