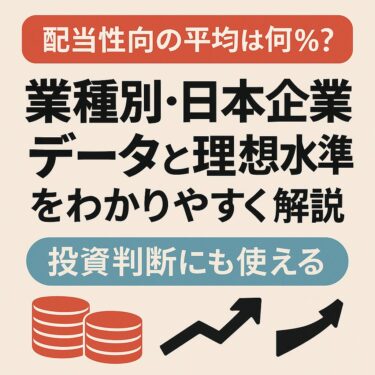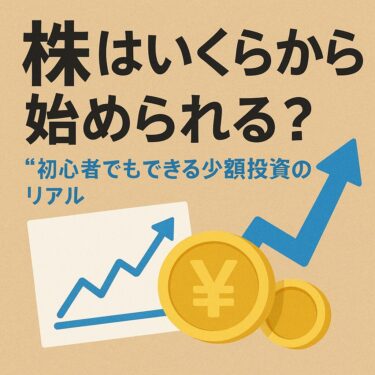株価の上がり下がりには、必ず理由があります。
その理由を数字と企業の中身から読み解くのが「ファンダメンタルズ分析」です。
チャート分析(テクニカル分析)が株価の動きを追うのに対し、ファンダメンタルズ分析は企業の実力を見極めるものです。
「どの企業が長期的に伸びていくのか?」
「今の株価は割安なのか、それとも割高なのか?」
──そんな疑問を解くための最も基本的な分析手法です。
ファンダメンタルズ分析とは?
■ ファンダメンタルズ分析の定義
ファンダメンタルズ分析とは、企業の本質的な価値を数字から評価する方法です。
売上や利益、財務体質、事業の成長性などをもとに、「この会社は今後も安定的に利益を出し続けられるか?」を判断します。
株価は短期的にニュースや思惑で上下しますが、長期的には必ず「企業の実力」に収れんしていくものです。
だからこそ、ファンダメンタルズ分析は長期投資の基盤といえます。
■ テクニカル分析との違い
株式投資の分析手法は大きく分けて「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」の2種類です。
| 分析方法 | 着目点 | 主な目的 | 向いている投資スタイル |
|---|---|---|---|
| テクニカル分析 | 株価や出来高の動き | トレンドやタイミングを把握 | 短期〜中期トレード |
| ファンダメンタルズ分析 | 業績・財務・成長性など企業の中身 | 企業価値を評価し、長期的に保有する | 長期投資・中長期スイング |
テクニカルは「いつ買うか」を判断する手法、ファンダメンタルは「何を買うか」を見極める手法です。
実際の投資ではこの2つを組み合わせることで、高い精度で勝ちやすいポイントを見つけることができます。
■ なぜファンダメンタルズ分析が重要なのか
株価は一時的に上下しても、最終的には業績や企業価値に戻る傾向があります。
たとえば、業績が右肩上がりの企業は、短期的な下落があっても中長期では再び上昇するケースが多い。
逆に、赤字や財務悪化が続く企業は、どんな人気テーマでも一時的な上昇で終わることがほとんどです。
つまり、ファンダメンタルズ分析を理解することは、
補足:どんな人に向いているか
-
チャートだけでは判断に迷う人
-
長期投資で安定的に資産を増やしたい人
-
企業分析や決算を読めるようになりたい人
こうした投資家にとって、ファンダメンタルズ分析は投資判断の羅針盤となります。
ファンダメンタルズ分析で見るべき3つのポイント
「企業の実力を見抜く」といっても、実際に何を見ればよいのか──
ここが初心者が最もつまずきやすい部分です。
まずは、ファンダメンタルズ分析の基礎となる 3つの視点 を押さえましょう。
① 業績(売上・利益・成長性)
企業の今の強さを測るのが業績です。
特にチェックすべきは次の3点。
-
売上高:市場シェアの拡大・縮小を示す
-
営業利益:本業のもうけ
-
経常利益・純利益:最終的な収益力
売上と利益が どちらも右肩上がり であることが理想。
もし売上が伸びているのに利益が減っている場合は、コスト増や競争激化など内部の課題が隠れていることがあります。
例)
トヨタのように、景気変動を受けつつも営業利益率を安定的に維持している企業は、ファンダメンタル的に強い企業の代表例といえます。
② 財務体質(安全性)
どれだけ売上があっても、借金が多ければ経営は不安定になります。
そのため、財務分析では 「自己資本比率」や「有利子負債比率」 が重要です。
-
自己資本比率:50%以上が目安(業界により異なる)
-
現金・預金の保有状況:突発的な赤字にも耐えられるか
財務が健全な企業は、景気後退や為替変動といった外的ショックにも強い。
逆に、成長しているように見えても借金頼みの成長をしている企業は注意が必要です。
補足
ROE(自己資本利益率)やROA(総資産利益率)は、財務と収益性をまとめて見るための代表的な指標です。
→ 詳しくは「ファンダメンタル指標23選まとめ」記事で解説しています。
③ 競争力・将来性
最後に見るべきは「この会社が今後も選ばれ続ける理由があるか」。
これは数字だけでは測れません。
-
ビジネスモデル(安定的な収益構造か)
-
競合との差別化(独自技術・ブランド・シェア)
-
将来テーマ(AI、脱炭素、サステナビリティなど)
たとえばキーエンスは高利益率を維持し続けるビジネス構造そのものが強みです。
一方で、同じ業界でも「価格競争型」の企業は長期的には利益が伸びにくい傾向があります。
まとめ
ファンダメンタルズ分析の第一歩は、「業績」「財務」「競争力」の3本柱をざっくりでも押さえること。
すべてを完璧に理解する必要はありません。
最初はざっくり評価できる目を養うだけで十分です。
企業分析のステップ(初心者向けロードマップ)
では実際に、どんな手順で企業を分析すればよいのか。
ここでは、初心者でも再現できる5ステップを紹介します。
Step1:企業を選ぶ(テーマ・業界から絞る)
まずは自分が興味を持てるテーマから始めましょう。
例
-
AI・ロボット → SMC、ファナック
-
化粧品 → 資生堂、コーセー
-
半導体 → レーザーテック、ディスコ
知っている会社から入ることでニュースや決算の理解がしやすくなります。
Step2:業績を確認する(売上・営業利益の推移)
過去3〜5年の売上と利益の推移をチェック。
数字が 安定して右肩上がり なら好印象です。
一時的な落ち込みがあっても、翌年以降に回復しているならOK。
松井証券「マーケットラボ」や「マネックス証券の決算サマリー」などを活用すると、グラフで視覚的に把握できます。
Step3:財務体質をチェックする(安全性の確認)
自己資本比率や有利子負債を確認します。
-
自己資本比率:高いほど財務健全
-
有利子負債:少ないほど安心
-
現金保有:潤沢な資金=倒産リスクが低い
決算短信の「貸借対照表」を見るだけでも、財務の健全性はざっくり掴めます。
Step4:株価水準を判断する(指標の活用)
株価が割高か割安かを判断するために、PER・PBR・ROE などの基本指標を使います。
たとえば、
-
PERが15倍前後 → 一般的な水準
-
PBRが1倍未満 → 純資産より安い状態
-
ROEが10%以上 → 資本効率が良い企業
ただし指標は業界ごとの平均値と比較するのがポイント。
→ 詳細は【ファンダメンタル指標23選まとめ】で詳しく解説(内部リンク)
Step5:将来性を考える(企業の物語を読む)
数字の奥にある企業の戦略や物語を読み解く段階です。
-
今後の成長分野に参入しているか
-
経営者の発言やIR資料に一貫性があるか
-
過去の戦略がどのように成果に結びついているか
これが理解できるようになると、ニュースや決算内容の意味がわかるようになります。
まとめ
初心者のうちは、最初から完璧な分析をしようとしなくてOKです。
最初は「数字と傾向を見る」→「興味を持った企業を追う」
この繰り返しで、自然と分析力が鍛えられていきます。
初心者がやりがちな3つの失敗パターン
ファンダメンタルズ分析を学び始めると、「PERが低い株を買えばいいんだよね」「ROEが高い会社が優良株」
──そんな風に数字の条件だけで判断してしまいがちです。
けれども、数字だけに頼る投資は危険です。
ここでは、初心者が陥りやすい典型的な3つの失敗を紹介します。
失敗①:指標だけで「割安・割高」を判断する
PERやPBRはあくまで「目安」にすぎません。
たとえば、PERが低くても業績が悪化していれば株価はさらに下がります。
逆にPERが高くても、急成長中の企業なら将来的に“割安”に見えることもあります。
失敗②:人気テーマ株だけを追ってしまう
SNSやメディアで話題になっているテーマ株は、一時的に急騰することがあります。
しかしその多くは短期の材料で終わるケースも多く、
決算内容や財務体質が伴っていない場合は、急落で含み損を抱えるパターンも珍しくありません。
失敗③:決算短信やIRを見ない
多くの投資家がニュース記事や株アプリの数値だけで判断してしまいます。
しかし、本当の情報源は企業が自ら発信するIR資料です。
決算短信、有価証券報告書、決算説明資料──
これらを一度でも読んでみると、数字の裏にある企業の意図が見えてきます。
まとめ:数字は「地図」、企業は「旅の目的地」
数字はあくまで方向を示す地図のようなものです。
最終的に行きたい場所(=企業の未来像)を見失うと、分析は意味を失います。
成功する銘柄選びのコツ
では、どうすれば「数字を活かした正しい銘柄選び」ができるのか?
ここでは、長期的に利益を積み上げていくための5つの実践ポイントを紹介します。
コツ①:業績の「トレンド」を重視する
単年の結果ではなく、3〜5年の推移を見ることが重要です。
売上・営業利益が安定して右肩上がりなら、事業基盤がしっかりしています。
一時的な赤字があっても、翌期でV字回復しているなら問題なし。
流れを読むことが、単なる数字以上の意味を持ちます。
コツ②:ROEと営業利益率をセットで見る
ROE(自己資本利益率)は資本の効率、
営業利益率は本業のもうけを示します。
この2つがそろって高い企業は、経営の質が高い企業です。
特に、
-
ROE:10%以上
-
営業利益率:10%以上
を安定的に維持している企業は要注目です。
コツ③:一過性ではなく構造的成長を見抜く
売上が急増している企業でも、補助金や一時的要因によるものは長続きしません。
一方、業界全体が成長している構造的テーマ”AI・半導体・脱炭素など)は、中長期で株価上昇を支えやすい。
コツ④:テクニカル分析と組み合わせる
ファンダメンタルズ分析は「何を買うか」を決めるもの。
買うタイミングはテクニカル(チャート)で判断します。
たとえば、
-
業績が好調
-
株価が75日移動平均線付近まで押している
このようなときにエントリーすれば、リスクを抑えつつ上昇を狙えます。
まとめ
ファンダメンタルズ分析で大切なのは、
「数字を見て終わり」ではなく、数字を通して未来を想像すること。
数字 × 企業のストーリー × 自分の視点
この3つがそろったとき、あなたの投資判断はブレなくなります。
決算書から何を見る?(数字を読むコツ)
ファンダメンタルズ分析を実践するうえで、避けて通れないのが「決算書(財務諸表)」です。
決算書というと難しく感じるかもしれませんが、実は たった3つの視点 さえ押さえれば、投資判断に必要な情報は十分に得られます。
① 損益計算書(P/L)で「利益の流れ」をつかむ
損益計算書では、企業が どのように利益を生み出しているか を確認します。
| 注目ポイント | 意味 | 見方のコツ |
|---|---|---|
| 売上高 | 企業の稼ぐ力 | 毎期右肩上がりか?前年比で伸び率は? |
| 営業利益 | 本業のもうけ | 安定的に増えているか?営業利益率にも注目 |
| 経常利益 | 本業+金融収支 | 本業以外で支えられていないか? |
| 当期純利益 | 最終的な利益 | 一過性の黒字ではなく継続して黒字か? |
目安:営業利益率が10%前後あれば、業種を問わず優秀な部類です。
② 貸借対照表(B/S)で「財務の健全性」を確認
貸借対照表は、企業の体力 を示す部分。
自己資本比率や現金残高をチェックして、倒産リスクの低い企業を選びましょう。
| 注目ポイント | 見る意味 |
|---|---|
| 自己資本比率 | 高いほど安全(50%以上が理想) |
| 有利子負債 | 借金の多さ。増えていないか要確認 |
| 現金・預金 | 十分な手元資金があるか |
現金が豊富な企業は、景気悪化時でも設備投資や株主還元を続けられます。
逆に、借金が多い企業は利息負担が重く、業績悪化時の株価下落リスクも高めです。
③ キャッシュフロー計算書(C/F)で「資金の動き」をつかむ
最後に、現金の流れをチェック。
-
営業キャッシュフロー(本業で稼いだ現金):プラスが理想
-
投資キャッシュフロー(設備投資など):マイナスでもOK(成長のため)
-
財務キャッシュフロー(借入や配当など):資金繰りを確認
第7章 まとめ:数字の裏にある企業の物語を読む
ファンダメンタルズ分析の目的は、
「数字を読むこと」ではなく、数字の裏にある企業の物語を理解すること です。
-
なぜ売上が伸びているのか?
-
どんな戦略で利益を出しているのか?
-
この企業は、5年後も社会に必要とされているか?
こうした背景を数字から想像できるようになると、
短期の値動きに左右されない「自信のある投資判断」ができるようになります。
投資で勝ち続けるための心構え
-
数字は嘘をつかないが、解釈を間違えると簡単に騙される
-
流行よりも、堅実に利益を積み上げる企業を選ぶ
-
焦らず・慌てず・理解して買う
この3つを意識するだけで、投資の失敗率は大きく下がります。
次に読むべきおすすめ記事
ファンダメンタル分析に使える全23指標まとめ|PER・ROE・自己資本比率まで完全解説
→ 各指標の意味と使い方を徹底解説。初心者が数字に強くなるための決定版です。
松井証券の「マーケットラボ」は、銘柄分析・チャート・四季報・スクリーニングまでを無料で使える高機能ツールです。
本記事では、松井証券マーケットラボの使い方、機能一覧、米国株版との違い、そして他社ツールとの比較までを徹底解説。
初[…]